お年玉をきっかけに考える、お金の3つの使い方
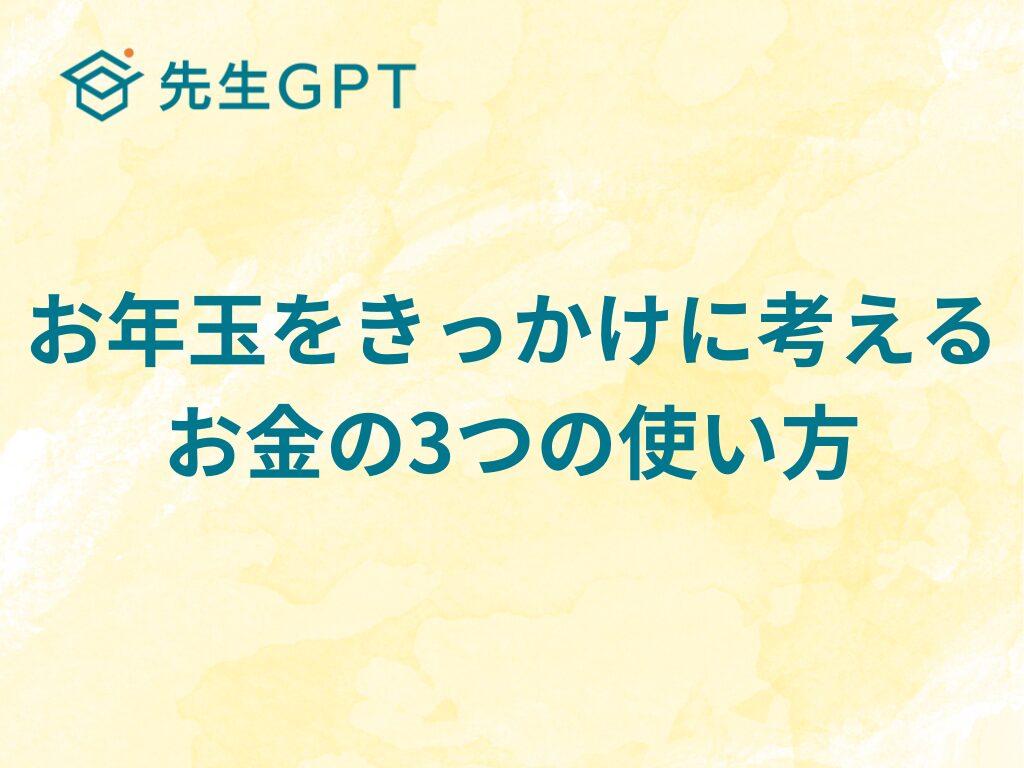
年末年始、お年玉をもらうことは子どもたちにとって楽しみの一つです。
そのお金をどう使うか、考える授業を取り入れてみてはいかがでしょうか?
「使う」「貯める」「与える」という3つの視点でお金の扱い方を学ぶことで、
子どもたちは計画性や思いやりを育むよい機会を得られます。
特に高学年になると、自分で判断する力が伸びてきます。
お年玉をきっかけに、お金との向き合い方を楽しく学べるようにしましょう。
『お金の3つの使い方を考えよう』
【1.使う】欲しいものを買うお金
まずは、「お金を全部使うとしたら、どんなものを買いたい?」と問います。
「ゲームソフト」「お菓子」「マンガの本」など、リアルな意見が出てきます。
ここで、「全部使ってしまった後に新しく欲しいものが出てきたらどうする?」と続けます。
あきらめたり、ねだったり、と方法は考えますが、あまり実効性はありません。
そこで、「お金を使うとき、全体の半分くらいは残しておくといいです」と具体的な目安を伝えます。
「次に欲しいものを買うための計画を立てる」という考え方を「使う」時にセットで話をします。
そうすると、それが結局は自身のためになることを理解できるようになります。
【2.貯める】将来のために残しておくお金
次に、「お金を貯めると、どんなことができると思う?」と問いかけます。
「高いおもちゃを買える」「旅行に行ける」「特別なイベントに使える」など、先を見据えた意見が出てきます。
「貯める」と今までにできなかったことができるようになるという考え方を教えます。
これ、お金以外では学校教育でも日常的に行われていることです。
勉強をし続けると賢くなる。
毎日練習すれば逆上がりができるようになる。
上記のようなことは、考え方としては「貯める」話です。
それがお金にも当てはまると伝えると、分かりやすい学習になります。
この考え方は、概念形成としては難しいのですが、
私が担任していた2年生の子どもたちでも「勉強と一緒」のような発言が多かったので、分かりやすい考え方のようです。
【3.与える】誰かのために使うお金
最後に、「お金を誰かのために使うとしたら、どんなことができる?」と問いかけます。
「友だちの誕生日プレゼントを買う」「家族に感謝の気持ちを込めて何かを買う」といった身近な例が挙がるでしょう。
ここで、「寄付や募金」についても話題を広げます。
「募金をすると、困っている人を助けることができます」「寄付を通じて社会の一員として役立つことができます」と伝えると、
お金を使うことで社会とのつながりを実感するきっかけになります。
【まとめ】
お金の使い方に正解はありませんが、「使う」「貯める」「与える」の3つの視点をバランスよく学ぶことで、
子どもたちは計画的で思いやりのある価値観を育むことができます。
お年玉をきっかけに、お金の扱い方を学ぶ楽しい授業をぜひ取り入れてみてください!
