インフルエンザの予防と対応マニュアル
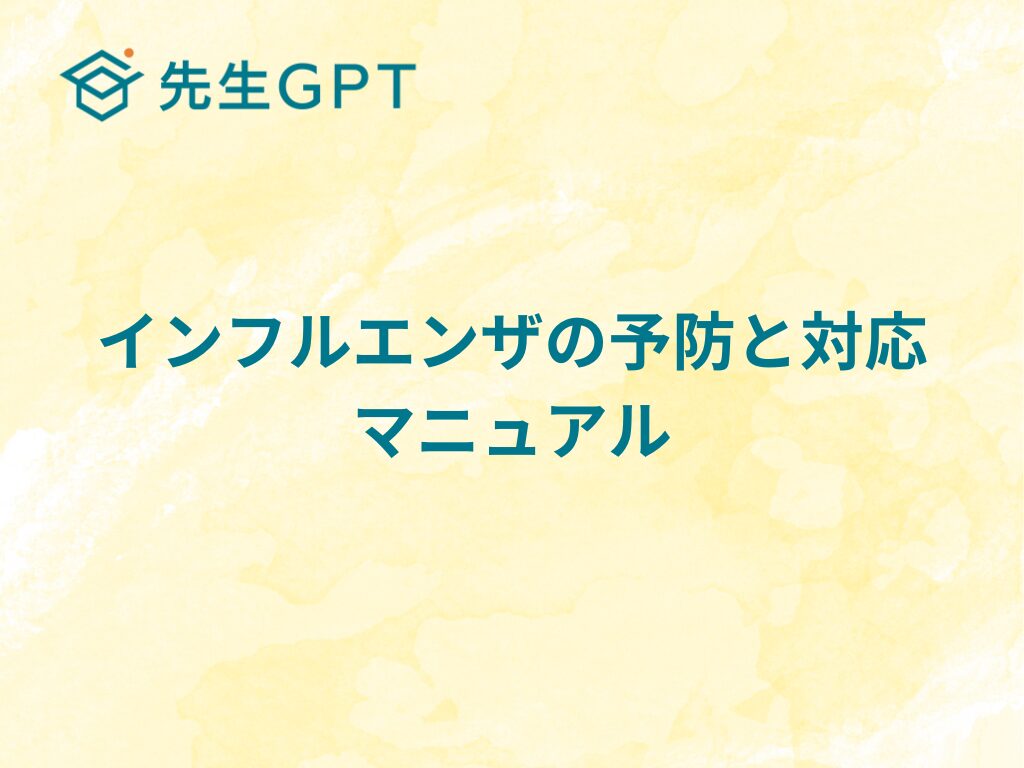
インフルエンザが流行する季節になりました。
今年は少し早いようで2024年の年末から学級閉鎖等の話を聞くことも多かったです。
ネットニュースで見ていると、今月下旬がピークになるという記事も…
学校では、感染予防や迅速な対応が求められます。
今回は、インフルエンザ対策に関する基本情報と具体的な対応策をご紹介します。
というのも、こういう季節性のものは時々見返しておかないと「わかったつもり」になりがちです。
【1】そもそもインフルエンザとは
インフルエンザは、ウイルスによって引き起こされる急性の呼吸器感染症です。
突然の高熱、咳、倦怠感が主な症状で、学校のような集団生活では特に感染が広がりやすい病気です。
【2】学校保健安全法
インフルエンザは学校保健安全法第19条に基づき、「出席停止」の対象となっています。
出席停止期間は以下の通りです。
•解熱後2日(幼児は3日)が経過するまで。
•医師が出席可能と判断した場合は例外があります。
保護者に通知する際は、この基準を明確に伝え、安心して休養できる環境を整えましょう。
学校側も児童の健康状態を適切に把握し、対応に活かしていくことが大切です。
こうした日数って先生でもあやふやです。
ご家庭でしたら尚更ですね。
【3】感染を防ぐためのポイント
1.手洗いやうがいを徹底する
外出後や給食前には、20秒以上かけて石けんを使った手洗いを習慣化しましょう。
手洗いの際は、指の間や爪の間も丁寧に洗うことが重要です。
2.教室内の換気を定期的に行う
換気は1時間に2回以上、5分から10分程度を目安に行いましょう。
冬場は湿度が40%を下回るとウイルスが活発化するため、加湿器などを使用して湿度を50~60%程度に保つことを推奨します。
3.健康管理に注意する
子どもたちには1日7~9時間の十分な睡眠を取るよう指導しましょう。
栄養面では、ビタミンC(みかん、いちごなど)やビタミンD(鮭、きのこ類など)を含む食品を積極的に摂ることで免疫力を高める効果が期待できます。
このような話は朝の会や給食の時間にしてもいいですね。
【4】罹患者が出た場合の対応例
1.教室や共用スペースを消毒する
机や椅子、ドアノブ、スイッチ、手すりなど、接触頻度が高い箇所を重点的にアルコール消毒します。
消毒は1日2回以上を目安に行い、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液(0.05%濃度)を使用します。
清掃時には手袋を着用し、終了後は手洗いを徹底します。
保健室にあることも多いため、養護教諭に聞いて、物品用として使ってもいいかの確認をしましょう。
2.濃厚接触者に注意喚起を行う
罹患者と同じグループ活動をしていた児童や隣席だった児童を特定します。
保護者へは次のような注意喚起文を配布します。
•発熱や咳などの症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診すること。
•家庭内でも手洗い・うがいを徹底し、予防に努めること。
これにより、感染拡大を未然に防ぐ意識を共有します。
こういうのはわかっていても、なかなか行動にまでは移せないケースも少なくありません。
流行り出す前から、準備をしておくといいかもしれません。
3.学級閉鎖の判断をする
学級閉鎖は、1クラスの欠席者が約20~30%に達した場合を基準に検討します。
校長と保健所が連携し、閉鎖期間を最適に設定します(一般的には5~7日程度)。
学級閉鎖に伴う保護者への通知や学級閉鎖期間中の生活指導も重要です。
4.欠席児童への学習支援を行う
欠席中の児童には、以下のサポートを提供します。
•家庭で取り組める課題プリントを用意(国語・算数を中心に)。
•デジタル教材やオンラインツールを利用できる場合はその案内も行います。
•学校の再開後には、学習の遅れを取り戻すための補習時間を設定します。
これらの対応により、感染拡大を防ぐだけでなく、児童の学びの継続を支援する体制を整えます。
【5】学級閉鎖時の保護者への連絡文例
件名
学級閉鎖のお知らせ
本文
○○小学校○年○組の保護者の皆さまへ
平素より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
このたび、○年○組においてインフルエンザの罹患者が増加し、感染拡大を防ぐために学級閉鎖の措置を取ることとなりました。
【学級閉鎖期間】
○月○日(○)~○月○日(○)
【お願い事項】
1.学級閉鎖期間中は、外出を控え、お子さまの体調管理にご留意ください。
2.発熱や咳の症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。
3.登校再開は、医師の診断に基づき、解熱後2日(幼児は3日)が経過してからとします。
本件に関するご質問がございましたら、担任または学校までご連絡ください。
【6】先生GPTで効率化する方法
1.学級閉鎖時の家庭学習資料を先生GPTで作成する。
2.保護者への連絡文を短時間で適切に作成する。
3.インフルエンザ対策に関する校内研修資料を準備する。
これらの活用により、教職員の負担を軽減しながら、迅速で的確な対応が可能になります。
