通知表コメント作成の時短術
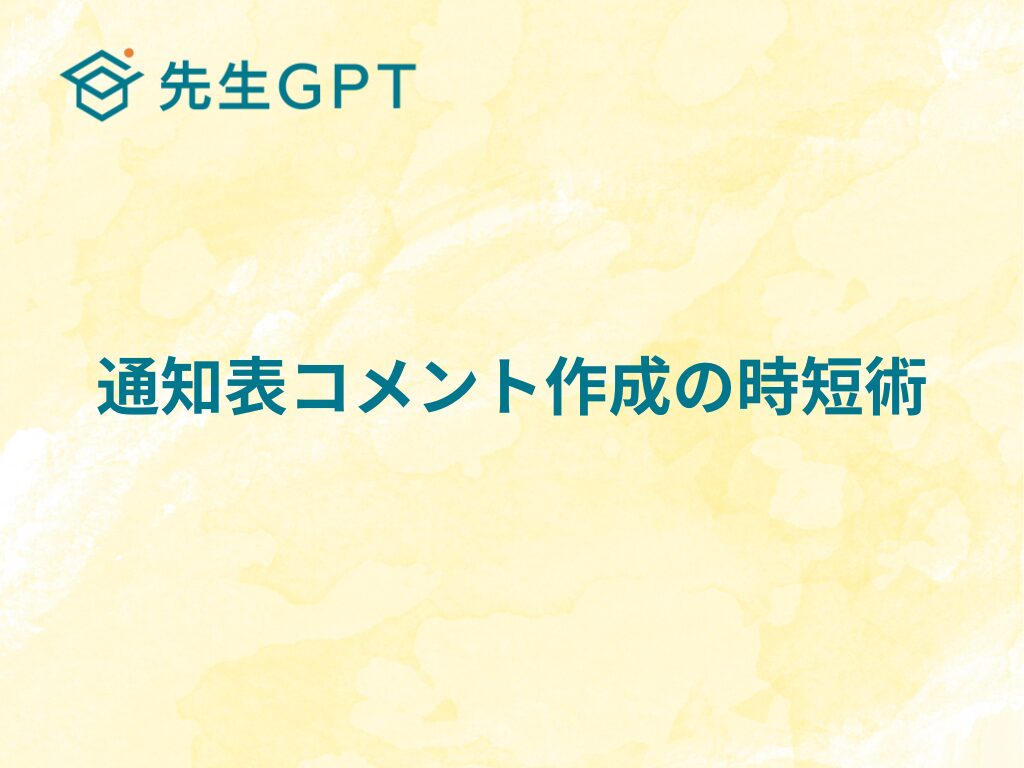
年度末が近づき、通知表のコメント作成に追われる時期がやってきます。
全児童生徒分を作成するには時間と労力が必要で、先生方の負担も大きいですよね。
そこで今回は、通知表コメント作成を効率化する方法と、先生GPTを活用した時短術をご紹介します。
最後にはちょっとした裏技もしていますので、ぜひご覧ください!
【通知表コメント作成をスムーズにする3つのポイント】
1.エピソードを日々記録する
児童生徒の頑張りや行動を日々記録しておくことで、コメント作成時の情報収集がスムーズになります。
よく質問があるのは「どのぐらいの文章量を入力したらよいのか」という質問です。
最低ラインで考えると、10文字程度あれば、1つの項目としては成立します。
「とても優しい」
「よく発言する」
この程度です。もちろん具体的に「友達が消しゴムなどの忘れ物をしている時に、自然と貸す優しさがある」のように入力しておくと、それらを反映していくので、さらによくなります。
2.テンプレートを活用する
各児童の特性に合わせて表現を少し変えるだけで済むよう、共通のテンプレートを用意しておきましょう。
例えば、
•学習面:「〇〇さんは、〇〇の課題に取り組む姿勢が素晴らしく、成長が見られました。」
•生活面:「クラスの友だちと協力し、〇〇の活動を通じてリーダーシップを発揮していました。」
先生GPTなら、基本のテンプレートを元に、児童生徒に合わせたカスタマイズが可能です。
3.入力をポジティブにまとめる
通知表コメントは児童生徒や保護者が目にする重要なメッセージです。
苦手な部分について触れる場合も、ポジティブな表現でまとめるようにしましょう。
例:「計算に取り組む際に慎重さが見られるため、よりスピードを意識して練習を続けることでさらに力が伸びるでしょう。」
【所見が何パターンがあれば終わるケースの場合】
総合や英語、道徳の場合は、全員に対して異なる文章を入力するケースよりも、数パターンを用意して、それらを所見欄に宛てていくことがあるのではないでしょうか?
様々な自治体の事例を伺っていると、生活所見は全員異なる文章を書き込む必要があるが、その他のところは、上記のようにすればよいという学校が時々見受けられます。
そうした場合は、例えば次のようにしてはいかがでしょうか。
①1〜3人分の入力をする。
②それらを元に出力をする。
③リロード(右側の矢印)を押して再生成する。
こうすることによって、様々なパターンの文章を出すことができます。
先生GPTのような生成型AIを使った所見のメリットは、時間がかからないこと、誤字脱字がないこと、過去の全国の先生方が書いた所見事例をもとに現状の児童生徒の所見を書いてくれることなどが挙げられます。
1月から3月に向けた年度末は、本当にあっという間に過ぎていきます。
今から通知表はもちろん指導要録をスタートしておくと、年度末の事務処理が楽になります。
1日5分ずつでも、1週間に1度でも、少しお時間が捻出できるとスムーズです。
