子どもが夢中になる「古墳クイズ」詰め合わせ
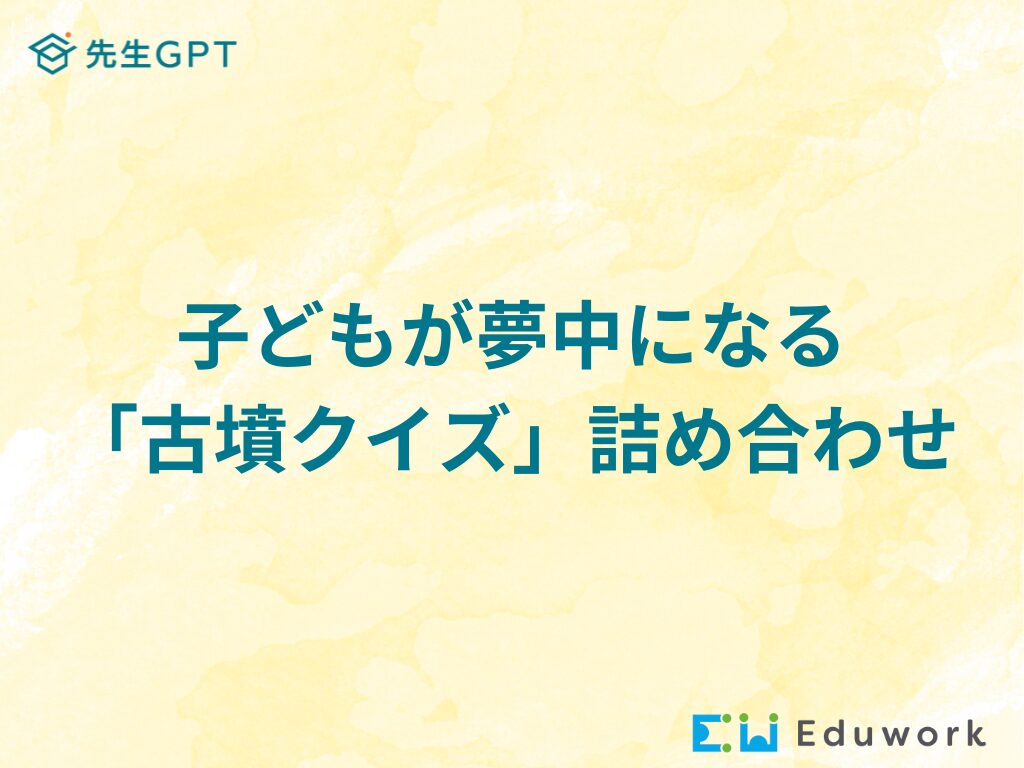
子どもが夢中になる「古墳クイズ」詰め合わせ
私が大学時代に研究室でお世話になった教授が、古墳をめぐっているという話を伺いました。
懐かしいなと思いつつ、そういえば以前、古墳にまつわる原稿を書いたなと思って探し出しました。
来年度、6年生担任でなくても、使える部分があるかもしれません。もしよろしかったら参考にしてみてください。
クイズ形式で出しています。
1.古墳、コンビニ、小学校。最も多いのはどれでしょうか?
→古墳が最も多く、約16万基ある。平均すると、47都道府県にそれぞれ3400基の古墳があることになる。
なお、コンビニが5万、小学校が2万となる。
2.古墳が多い都道府県ベスト3はどこでしょうか? 3つ書きます。
→こうした問題を出す時には、3つのように指定するとよい。数が多いと当てやすいし、子どもたちの活動にもなるため、思考が働きやすい。
正解は、
1位 兵庫県 16,577基
2位 千葉県 13,112基
3位 鳥取県 13,094基
という順になる。
これら3県の古墳は、数が多いが、小さなものが多い。全長が100メートルを超える大型古墳は、大阪、奈良、京都、岡山に集中している。権力者がこの辺に多かったからだと言われている。
3.どの形の古墳が最も多いでしょうか?
A:前方後円墳
B:円墳
C:方墳
黒板に絵を描きながら説明するとわかりやすい。
古墳には様々な形がある。その中で最も多いのが円墳で、全体の8〜9割を占めている。
その次に多いのが方墳だ。
一般的に古墳と言われるとイメージする。前方後円墳は、全国で約5,000基ある。
4.日本全国で1つしかない古墳の形はどれでしょうか?
A:双方中円墳
B:双円墳
C:四隅突出型墳丘墓
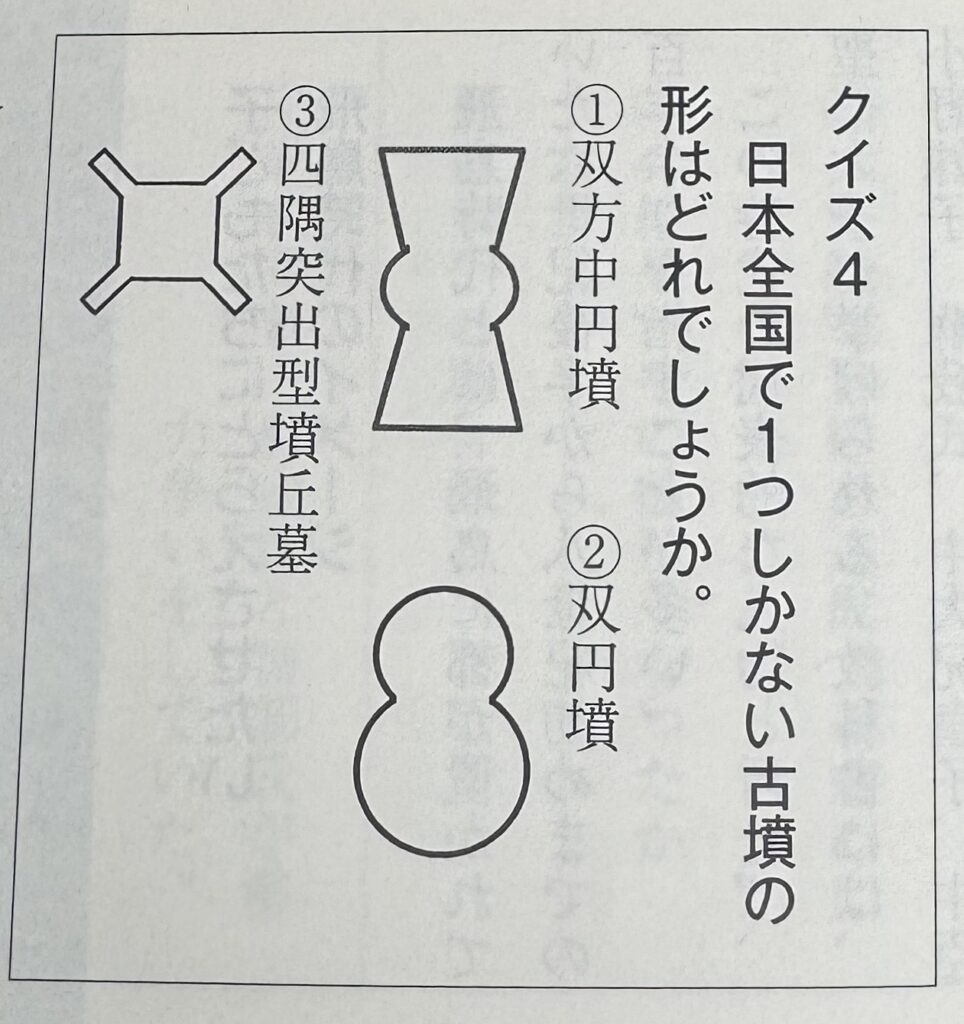
全国に1つしかないのは双円墳だ。大阪の金山古墳がこの形をしている。Aは前方後円墳の変形版ではないかと言われている。また、Cは古墳時代、以前の弥生時代に山陰地方で多く作られた形の古墳だ。この形の墓が作られた時から古墳時代という研究者もいる。
5.世界三大陵墓を線でつなぎましょう
A:大仙陵古墳
B:始皇帝陵
C:ピラミッド
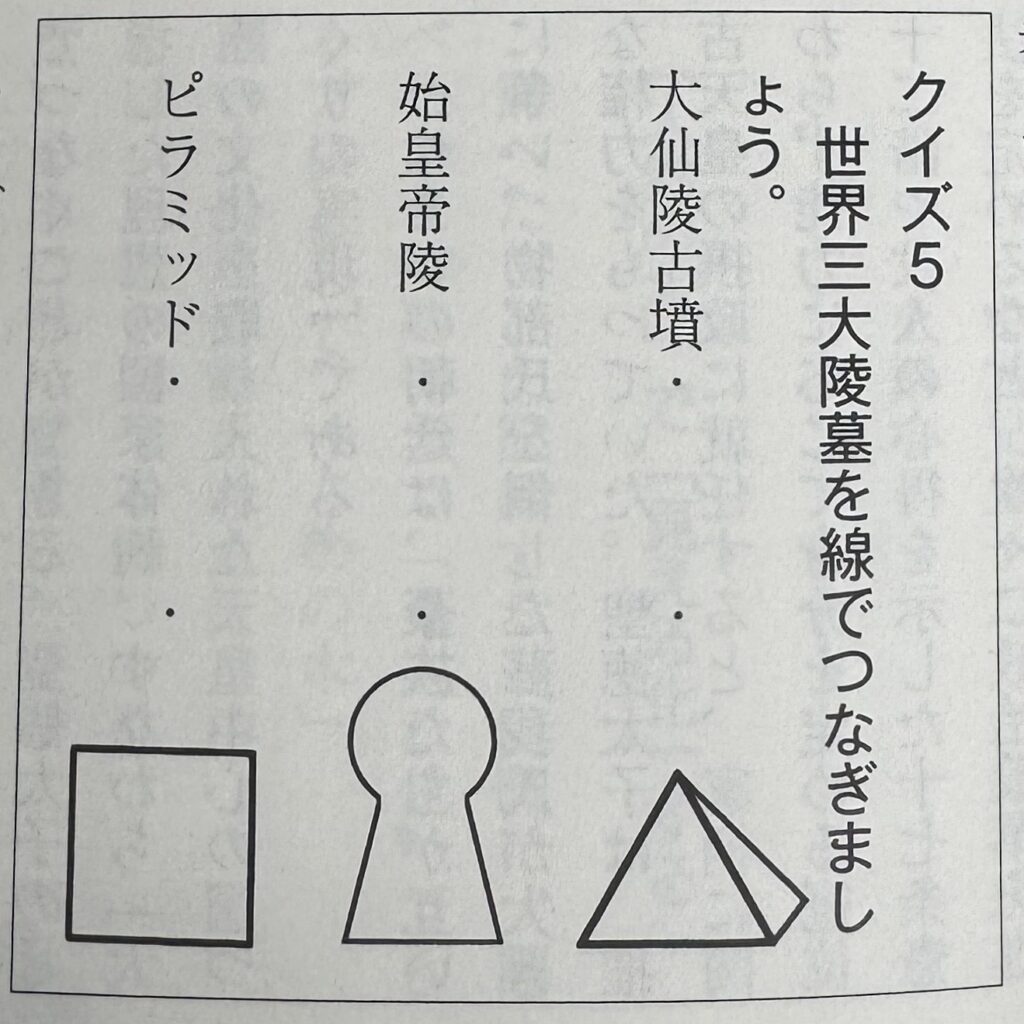
6の広さにつなげる問題とする。
6.世界三大陵墓で最も広いのはどれでしょうか?
7.大仙陵古墳は、小学校のグラウンドのいくつ分ぐらいあるでしょうか?
→広さ(面積)では、大仙陵古墳、体積では始皇帝陵、高さでは、ピラミッドが1位となっている。
また、小学校設置基準では、大規模校のグラウンドの広さは7,200平方メートル以上と定められている。大仙陵古墳は103,410平方メートルだ。二者を比較すると約14倍になる。グラウンドが約14面入る広さの墓となると、すごい大きさのイメージとなる。古墳時代は、これほど多く、大きな古墳が作られたということをクイズから感じさせる。
その後、必要だった材料や費用、人間の数について検討すると、古墳時代をイメージしやすくなる。
