4月1日、学校の仕事が山積みでも“自分の時間”をつくるコツ
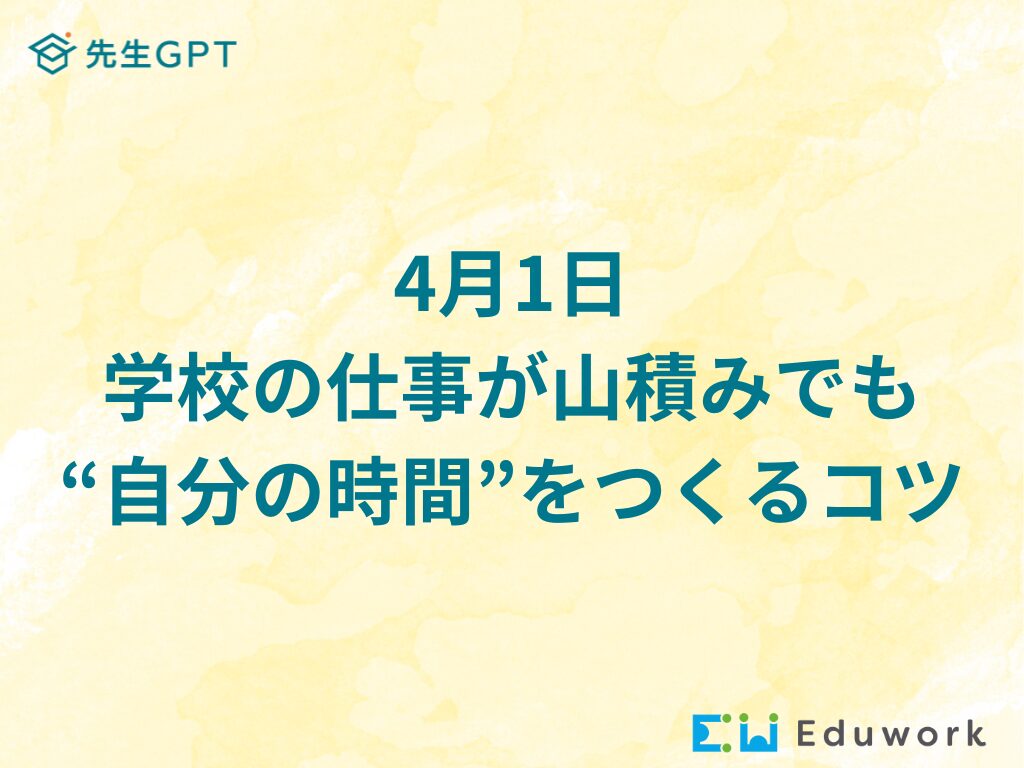
学校の先生にとって、4月1日は、年間を通して最も忙しい1日ではないでしょうか。
異動内示は出ていたものの、改めての人事発表。
すぐに挨拶。
次に職員会議。
歓迎会を兼ねた昼食会があり、午後からも会議。
校務分掌や教科、学年の会議が連続してやってきます。
気づけば夕方。
子どもたちの名前を覚える暇もなく、初日が終了。
不安だから残業しようと思っても、「初日くらいは早く帰りましょう」という声かけで学校を出される。
疲労感だけが残って1日が終わる——。
そんな一日になってしまいがちです。
会議の時間は変えられません。
全体で動く以上、誰かだけが抜け出すことはできません。
では、4月1日から子どもたちが来る“登校初日”までの限られた時間を、どうやって有効に使えばいいのでしょうか。
私の場合は、2つのことを意識していました。
1つは「やるべきことリスト」を作ること。もう1つは「内職をうまく活用すること」です。
【やるべきことリストの作成】
子どもたちが登校するまでにやらなければいけないことを、できるだけ具体的にリスト化します。
例えば、次のような項目です。
1.教室消耗品のチェック
2.児童名の暗記
3.学級通信のタイトル決め
4.学級通信1〜3号までの作成
5.学年だよりの作成
6.教材の発注
7.遠足の下見予定の確認
8.家庭訪問リストの準備
9.教科書のざっとした目通し
10.下駄箱・ロッカー用の名前シール記名
もちろん、学校や役職によって変わってくる部分はあります。
でも、リストにしておくと「あとどれだけやれば終わるのか」が見えやすくなります。
終わりが見えないと、しんどくなりますから。
そうならないためにも、“自分なりの完了ライン”を見える形で用意しておくことが大切です。
【会議中の内職をうまく活用する】
職員会議は、他のことを一切せずに話を聞き続けないといけない、というわけではありません。
会議の内容を理解し、必要な場面で発言し、全体での活動に支障をきたさない範囲であれば、“ちょっとした作業”を進めておくのは、私はありだと思っています。
ただし、音を立ててパソコンを叩いたり、丸つけを始めたりするのは控えた方がよいですね。
空気感を乱さない工夫は必要です。
私が実際にしていた「内職」の優先順位はこんな感じです。
1.職員会議で提案された提出物の作成
学級経営案やクラブ希望調査など、会議で話が出たらその場で作成して、終了後すぐ提出する流れに。
2.学年の仕事
教材リストのたたき台や、遠足下見の確認項目、会計計画など、誰かがやらないといけない仕事を少しずつ先に進めます。
隣の先生からタブレットを覗きこまれても、「ありがたいな」と思ってもらえる内容にしておくのがポイントです。
3.クラスのこと
自分のクラスに関することは最後に。
優先順位をはっきりさせておくと、周囲からの理解も得やすくなります。
時間をただ「使わされる」状態になると、しんどさが残ります。
でも、同じ時間を“自分のために”使う意識を持つだけで、少しずつ前に進めます。
初日。
何も全部終わらせる必要はありません。
でも、何か一つでも「やれた」と思えることがあると、その1日は前向きに終われます。
よいスタートが切れますように。
