4月2日、何から始める?“優先順位で動く”チェックリスト
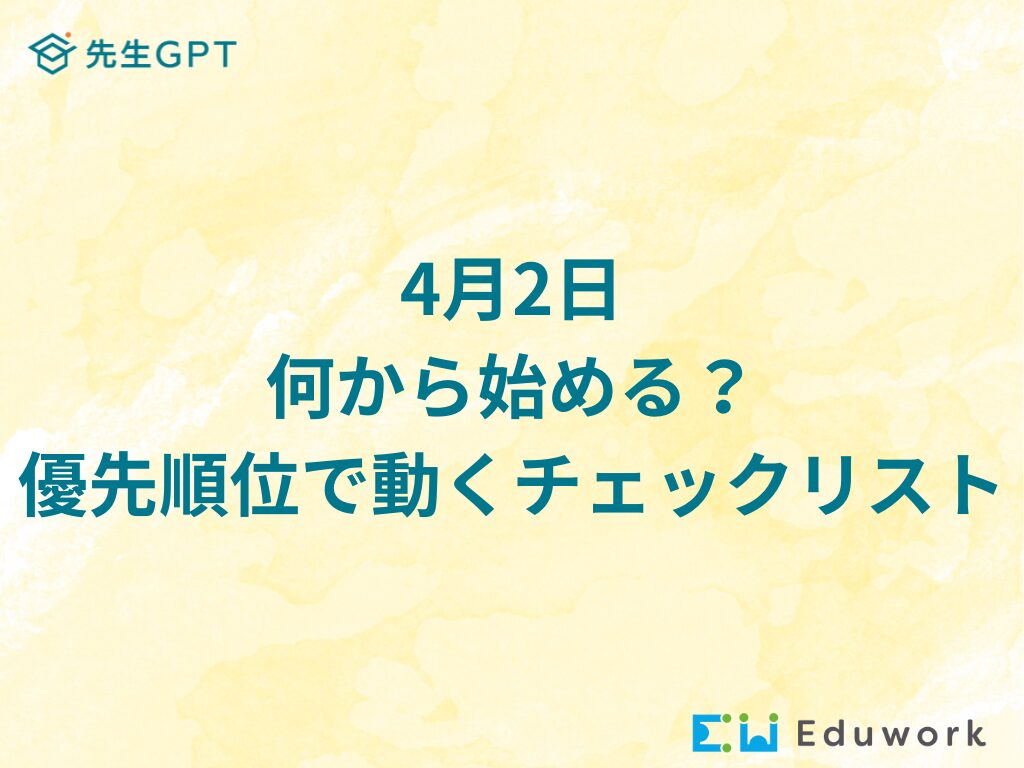
昨日は、異動発表や担任発表があり、怒涛のように過ぎていった一日だったのではないでしょうか?今日からがいよいよ本格的な“準備期間”の始まりです。
とはいえ、やることは山のよう。
どこから手をつけたら…と迷う先生も多いのではないでしょうか?
そんなときは、優先順位で動くのがコツです。
私がいつも意識していた「4月2日にやることチェックリスト」を共有します。
◻︎ 教室の掃除(机・棚・ロッカー)
→机は埃まみれ、ロッカーに前年度の荷物…。前の先生の掃除の仕方が自分自身の中で合格かどうかは分かりません。まずは自分で少しでも掃除をしておくと、気持ちよく新年度を迎えられます。
手間のように思えるのですが、儀式のようなイメージで、私は毎年していました。
◻︎ 名札・下駄箱・ロッカーの名前ラベルの準備
→これのポイントは、ただの作業にしないことです。新年度は時間がありません。その中で、子どもたちの名前を覚えて望みたい。そう考えた時に、この名前ラベルを準備する動きは名前を覚える絶好のチャンスになります。
◻︎ 出欠や連絡帳の運用ルールを確認
→電話、アプリ、連絡帳。学校全体のルールに加えて、自分が混乱しないよう導線をイメージしておきます。昨年と同じ学校の方は、ぜひフォーマットの作成をしてみてください。例えば、欠席の時にはこう書く、お礼の時にはこう書く、のようにです。数パターンを用意しておくと便利です。
これまでは感覚で「欠席の時にはこう返信する」のようにしていたと思います。その感覚で行なっていたものを文章でまとめておきます。
すると、考える行為が減るので、圧倒的に仕事が早くなります。
◻︎ 学級通信のタイトルを考える
→これは意外と時間がかかります。ちなみに私は、
・みんな太陽
・seven colors
・BRAVE
・花鳥風月
などでした。
最初の3号分くらいまでネタだけでもストックしておくと後が楽になります。
◻︎ 家庭訪問の地域や通学路の確認
→日程が近くなって準備を行うと、紙の地図の場合はコピーの順番待ちが大変です。ネットの地図を使う場合でも住所の打ち込みが面倒。あらかじめ少しでも進めておくと、近くなってからがめちゃくちゃ便利です。
期日が近くなってからゼロベースで仕事をするとしんどさが倍増します。そうならないように、10をゴールだとすると、2〜3でスタートをさせるイメージを持っておくと負担感がかなり減ります。
◻︎ 4月の授業参観でやる内容の下準備
→導入だけでも考えておくと、慌てません。
こういうのを学年会で話すと「近くなってから」と返されるケースが多いですが「国語でよいですか?」のように少し確認すると、スムーズになります。
ちなみに私は1回目はよほど事情がない限りは国語でした。漢字、音読、読み取り、百人一首等、1時間の授業で様々な学習内容ができるからです。保護者がご覧になられても飽きにくいので「アタリの先生」に向けての第一歩としての時間を提供できます。
◻︎ 児童の個別支援計画や出席簿の下書き
→過去の資料がそろえば、今年提出する個人関係資料は一年巻分をすべて作成してしまいます。提出する時には、それをいくらか手直しするような感じです。
他にも、出席簿は夏休み前までは一気に作成します。名前の打ち込みや休日の設定は意外に面倒です。それを何回もするよりは一度にやってしまった方が早いです。
◻︎ 教科書チェック・副教材の発注
→配布する教科書の冊数チェック、先生用教科書の確認、副教材の発注は、必須の作業になります。絶対に外せない仕事であれば早めにやってしまった方がよいです。
特に「副教材の発注」は、教材屋さんという相手がいます。業者を待たせてもよいという姿勢の先生も少なくありませんが、お互いが気持ちよく仕事をするためにもぜひ早めに対応しましょう。
このリストは、私自身がベテランの先生から教わったものです。若手の頃からちょっとずつバージョンアップをしたり、学校によって変更しながら実施してきました。
全部をやる必要はありません。
でも、“今やると後が楽”なものが詰まっています。
4月1日で疲れてしまった方も多いと思いますが、今日1日をどう使うかで、始業式以降がぐっと変わります。
できるところから、優先順位をつけて取りかかってみてくださいね。
