【Q&A】まだ始まっていないのに不安…その気持ちは子どもと同じです
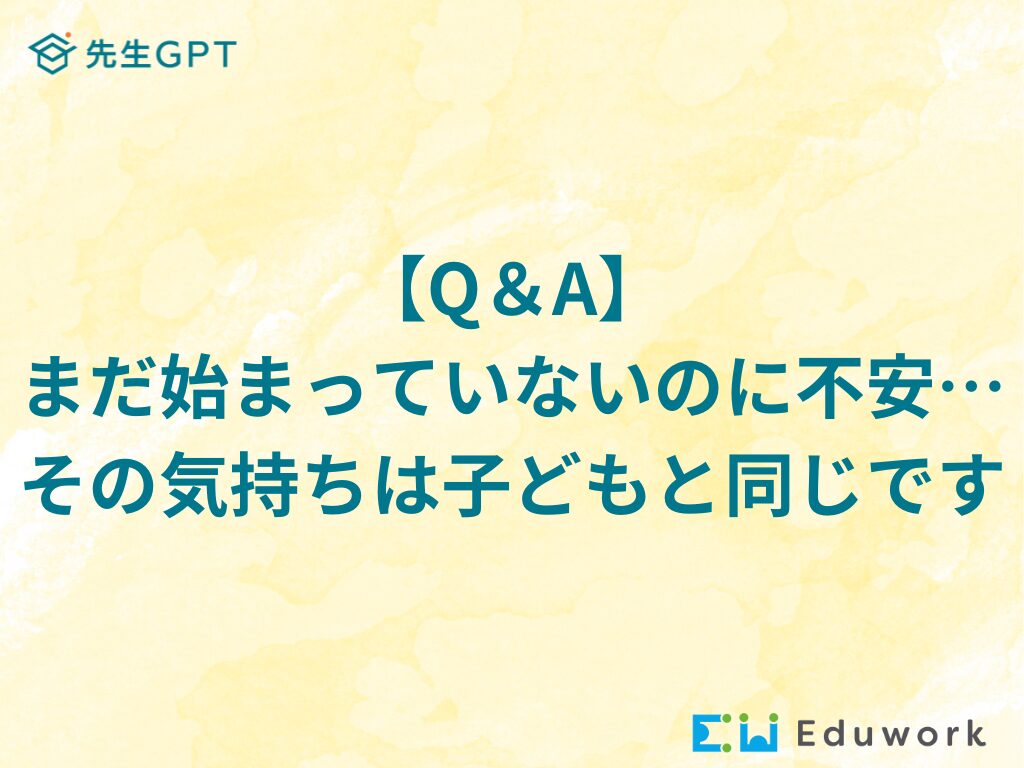
少しずつ学校の動きが本格的になってきました。
先生方からもいろいろな声が届いています。
新しく担任になった先生だけでなく、新しい校務分掌や役職に就いた先生からも、
「ちゃんとやれるか不安でいっぱいです」
「引き継いだはずなのに、何をしていいかわかりません」
「管理職になりました。役職としてはなったのですが、私に務まるのか…」
というお話をよく聞きます。
今回は、そんな不安の気持ちに関するご質問を取り上げます。
⸻
Q:クラスがまだ始まってもいないのに、不安でいっぱいです。
ちゃんと担任が務まるのか、自分にできるのか…。
気がつくとため息ばかりついてしまっています。(20代女性・担任2年目)
⸻
A:その気持ちは、先生だけではないです。
先生の目の前に来る子どもたちも、同じ気持ちを抱えています。
担任になると、どうしても「自分がなんとかしなければ」という気持ちになります。
うまく学級経営できるかな、子どもたちと信頼関係が築けるかな、保護者対応は大丈夫かな…。
まだ子どもたちと出会ってもいないのに、心がざわざわしてしまう。
でもその不安、裏を返せば「いい先生になりたい」という想いの表れです。
本気で向き合おうとしている証拠です。
子どもたちも不安です。
知らない教室、新しい担任、新しい友だち。
学校という環境のすべてが変わっていく中で、誰もが少なからず緊張しています。
大人になると、慣れた業務の中で生活する時間が長くなり、
「新しいことに挑戦する」機会は減ってきます。
でも、子どもたちは違います。
彼らにとっては、毎日が新しい学び、新しい経験の連続です。
子どもたちは「毎日、不安と向き合っている」状態です。
だからこそ、先生自身が今感じているこの「不安」という感覚は、
子どもたちに寄り添う上での大切な“共通点”にもなります。
よく「慣れることが大事」「慣れすぎには注意」などと言われます。
確かに、年度当初は生活のペースを整えたり、スムーズに仕事をこなせるようになることも必要です。
でも、慣れすぎてしまうと、大切な感覚を見失ってしまうこともあります。
不安を感じられる先生というのは、子どもたちの気持ちに敏感になれる先生でもあります。
それに敏感であることは、決して弱さではなく、信頼につながる強みです。
年度当初、すぐに「よし、やるぞ!」と気持ちが切り替えられる人もいれば、
なかなかエンジンがかからないという人もいます。
どちらも、ありのままの姿です。
焦らず、一つひとつの準備に向き合いながら、
「少しずつ」自分のペースを作っていってください。
そのペースに合わせて、子どもたちも同じように少しずつ慣れていくのではないかと思います。
また、気持ちの切り替えが難しいという場合には、朝玄関を出た時に深呼吸をしてみてください。
朝の光を浴びることで分泌されるセロトニンは、心を安定させ、前向きな気持ちを引き出してくれる脳内物質です。
これ、脳科学の先生から教えてもらった時に「ウソだろ」と思いながら、何回か試すと、思いの外にいい感じでした。
玄関を出た時に10秒くらい深呼吸。
今では10年以上続くルーティーンになっています。
