「出会いの一言」と「初日の段取り」で1年が変わる
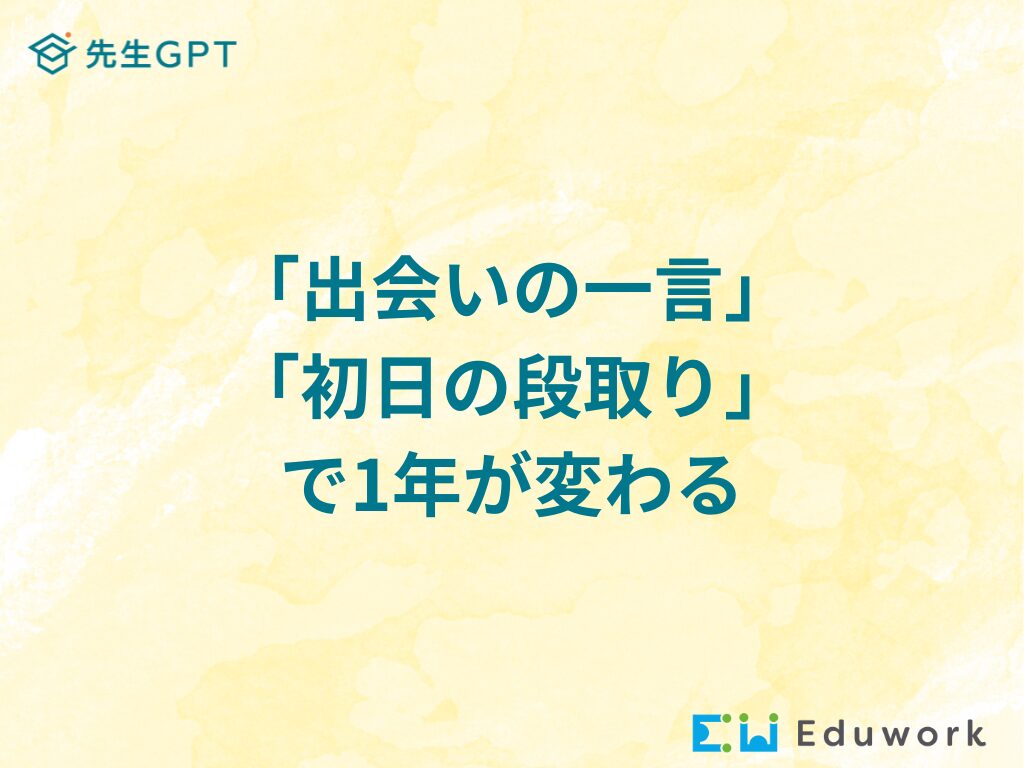
今日か明日のいずれかが始業式という学校が多いのではないでしょうか。
新年度のスタートは、先生にとっても、子どもたちにとっても特別な日です。
「初日がうまくいくかどうか」で、その年の空気感が決まってしまう。
そう言っても、過言ではありません。
でも、はじめての教室、はじめての顔ぶれ、時間が足りないスケジュール…。
とにかく慌ただしい1日になることもまた、事実です。
■初日は本当に“あっという間”です
4月の初日は、朝からバタバタが続きます。
ベテランでも、初心者でも、それは共通です。
予定していたことができなかったというのも珍しくありません。
担任発表、新しい教室に入り、教科書や配布物を渡しながら、名簿の確認、持ち物のチェック。
「あれも伝えなきゃ」「これも渡さなきゃ」と思っているうちに、気づけばもう下校時間。何も準備していないと、初日にほぼ何も伝えられないまま終わってしまいます。
だからこそ、「当日の動き」を事前にイメージしておくことが大切です。
■私が大事にしていた「初日段取りメモ」
始業式の日は、時間がありません。
なので、段取りをあらかじめ決めていました。
教科書配布を例にすると次のようなことです。
1.教科書の運搬は誰に頼むか
→先頭から10人と決めていた年もありましたし、不登校傾向や発達に課題があるお子さんがいる場合はこちらから指名していた年もありました。人数としては10名くらいが適正です。
2.教科書の配り方
→学年主任に質問しても「適当に」のように返されてしまうケースが多いです。
しかし、正確に配布されないとトラブルが起きるのが教科書配布です。
例えば、列の先頭に、その冊数を置いて、後に回していく。
配り終えたら、合計で何冊あるのかを確認する。
こうしたルールを守らせ、それに対して評価する。
このようにすると漏れがありませんし、褒める機会にもなります。
3.記名
小学校中学年程度までは、配り終えてから教科書への記名をさせていました。
配布と記名。同時処理をした方が早いのですが「配る」と「名前を書く」という2つの作業を同時並行でさせると、それだけで混乱するお子さんもいたからです。
結果的にバラバラでした方が早く終わる年があり、そのように切り替えました。
教科書を配ったら、
『教科書を開きやすいようにクセをつける→名前を書く→名前が書いてある裏表紙を上にして乾かす』
という流れをつくっておく。
これは簡単なようですが、これでも3つの作業があります。
こういった作業は板書して順番がわかるようにしておくと安定して進めることができます。
初日から失敗をさせないようにするための細やかなテクニックです。
■最初に伝えるメッセージは「勉強」と「仲良く」だけで十分
出会ったその日に全部を話そうとしないことが大切です。
子どもは緊張していて、ほとんど頭に入っていません。
私は毎年、最初に2つだけ伝えていました。
「学校は、2つのことをがんばる場所です。1つは、勉強をがんばること。もう1つは、友だちと仲良くすること。先生も、この2つを皆さんと一緒にがんばります。」
たったこれだけです。でも、この2つを大事にすると、1年間の基本がブレません。
■挨拶は「爽やかに」「にこやかに」
「初日はとにかく元気に!」と思われがちですが、にこやかで落ち着いた挨拶のほうが効果的です。
大きな声で「おはよう!」と張り上げるよりも、優しい笑顔と、よく通る声で「おはようございます」と伝える。
声を張るよりもよっぽど子どもたちは安心します。
“元気すぎる挨拶”が苦手な子もいます。
声の大きさよりも、表情と空気感を大切にしてみてください。
初日は、「子どもたちと出会う日」であると同時に「限られた時間の中で、何をどう伝えるか」を問われる日でもあります。
・配布物・チェック物の動線を、事前に段取りしておく
・挨拶は、爽やかににこやかに
・学校は「勉強するところ」「仲良くするところ」だけをまず伝える
この3つを意識するだけで、初日の余裕はぐっと変わります。
先生も子どもも、安心して始められる“いい空気”をつくっていきましょう。
