「学校が嫌だと思うサイン」を見逃していませんか?
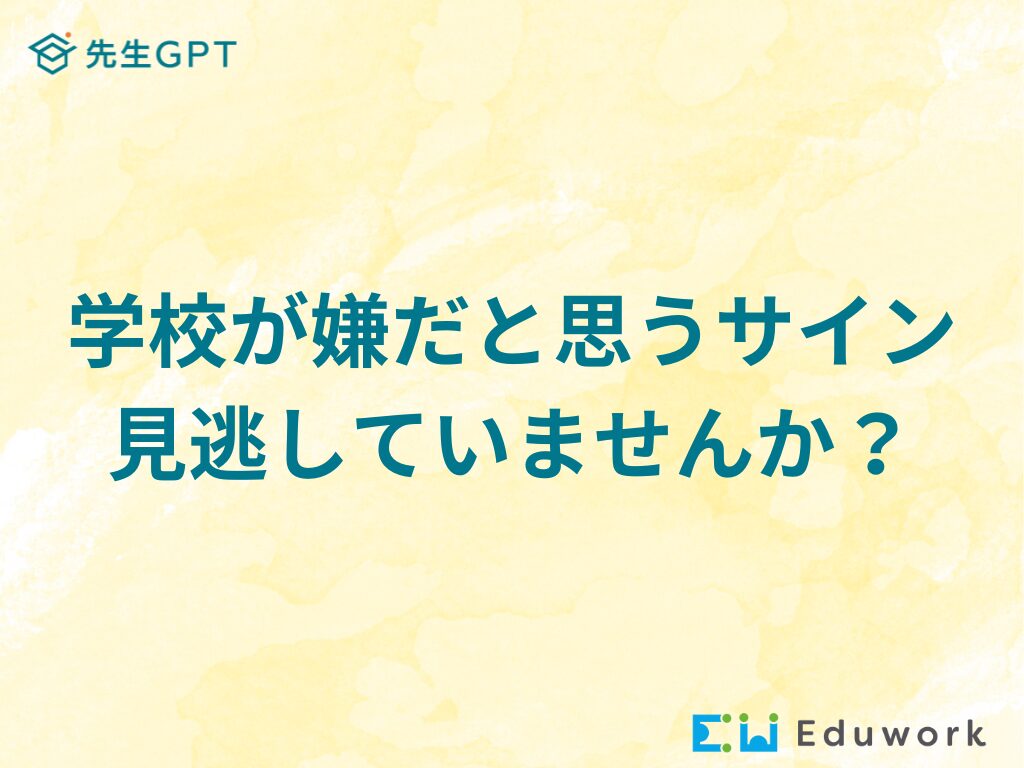
新年度が始まり1週間が経ちました。少しずつ、子どもたちの表情や行動に変化が出てきます。
見逃しやすいのは、いわゆる「おとなしい」と言われる子どもたちです。
走り回ったり、不規則な発言をする方に目が向き、静かにしている子たちには、なかなか目が向きません。
気がついたら欠席をするようになっていたということにならないようにしていきましょう。
■「小さなサイン」を見逃さない
学校に行きたくないという気持ちは、子どもにとって簡単に言葉にできるものではありません。だからこそ先生が、言葉にならないサインをどれだけキャッチできるかが大切です。
こんな変化が出ていたら、少しだけ気にしてみてください。
・朝の支度が遅くなる(ランドセルを背負いたがらない、学校についてもランドセルを開くのが遅い)
・教室で一人でいることが増えた
・「お腹痛い」「眠い」など、体調の訴えが増える
・「うん」とか「はい」しか言わなくなる
・給食の準備や片付けで動きが鈍る
・帰る直前だけやたら元気になる
ひとつひとつは小さな行動ですが、気持ちのサインが、こうした日常の中でにじんできます。
■声かけは「干渉」ではなく「見守り」で
こうしたサインはほんのわずかです。ちょっとした違和感しか感じ取れません。それが正解かどうかもわからない位です。そこで、そうしたサインに気づいた時、どのような行動を取るのかに迷ってしまいます。
私の経験では、まずは少し距離をおきつつ「見守り」から始める方がうまくいくことが多いです。
・配り物を「お願い」と任せてみる
・一言だけ「最近どう?」と聞く
・帰り際に「また明日!」と軽く声をかける
そして、その反応を確認する。
このくらいの近づきすぎない距離が、子どもたちにとって「気にしてくれてるけど、詮索はしてこない」という安心感になります。
■周囲の子との関係性を活用
本人には言いにくくても、周囲の子が気づいているケースもあります。こちらもほんのちょっとのことです。
・前から後ろにプリントを配っていく時に、対応が遅れ「もらって!」という声があがった。
・おかわりしないの?といった声がある
・遊びのグループが固定化したと思ったら、別のグループができた。
本人たちですら気がついていないような変化であることもあります。
■ズレは育っている証拠
年度当初は、緊張とがんばりでうまくやっていた子どもたちも、少しずつ本音が顔を出す時期になります。
それは決して悪いことではありません。
クラスになじもう、合わせようとがんばったからこそ出てくるズレです。
そのズレが大きくなりすぎる前に、先生が少しだけ気にかけてあげる。それだけで、雰囲気が軽くなります。
4月は、表面上は落ち着いて見えても、内面では揺れやすい時期です。だからこそ、ちょっとした違和感に気づく先生の目が、大きな支えになります。
子どもたちの「小さなサイン」、見逃さず、でも急かさず。一緒に、じっくり育てていきましょう。
