【Q&A】「注意するのが苦手です…」それでも注意しなくちゃいけない理由、ありますか?
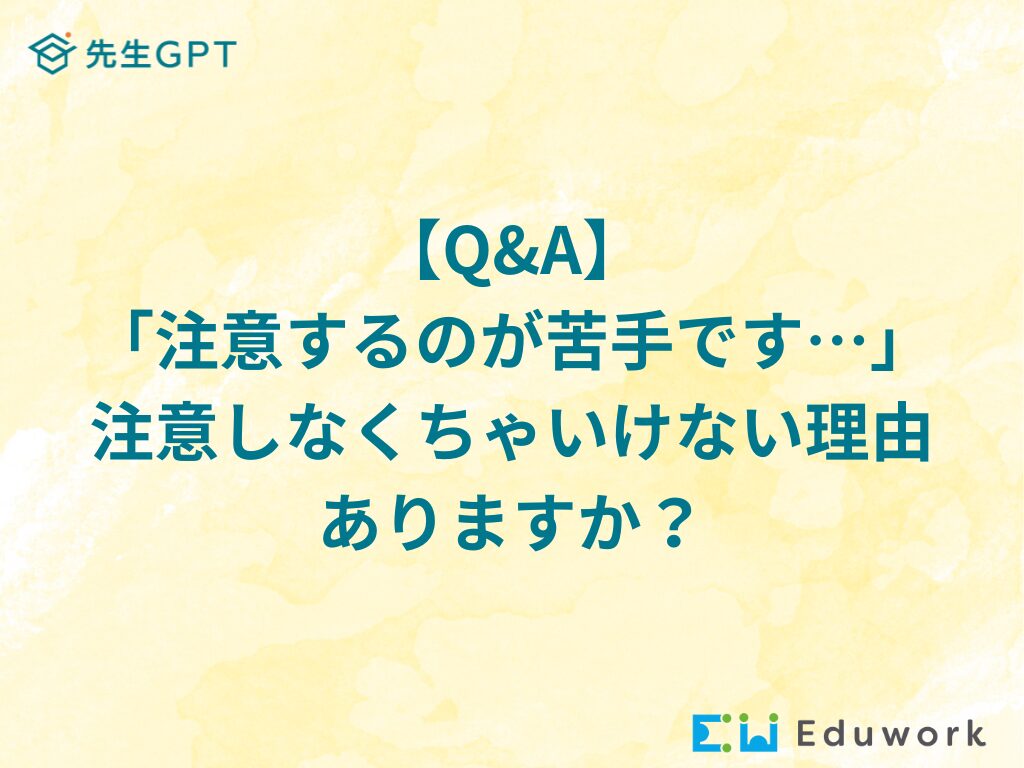
Q:最近、少しずつ子どもたちの緊張もほぐれ、学校生活にも慣れてきたように感じます。ただ、その分、気になる行動も目につくようになってきました。
注意しなきゃと思うのですが、「雰囲気が悪くなるのが怖い」「嫌われそうで心配」と、ついためらってしまいます。
上手に注意するコツってあるのでしょうか?(30代・女性・担任)
A:とてもよくいただくご相談です。
結論から言うと、注意した方がいいです。子どもたちの成長の大きなきっかけになるからです。ただし「伝え方」には工夫が必要です。
4月の後半、子どもたちは少しずつクラスに慣れ、自分のペースを出してくる頃です。そのタイミングで出てくる行動のズレに、先生がどう向き合うか。それは、これからの信頼関係にも大きく関わってきます。
■「怒る」ではなく「伝える」ことが信頼につながる
注意が苦手な理由の一つに、「注意=怒る」となってしまっていることが挙げられます。
でも本来は「注意=怒る」ではありません。
それが混ざってしまうと、怒られただけになってしまい、伝わらない形になってしまいます。
伝わらない形なのに、学校でよく見る場面は「長い話」です。これは避けた方がよいです。『理由』を聞いた時に長くなる傾向があります。
・なんで走ってしまったの?
・どうして片付けしないの?
・パッと動けないのはどうにかならないの?
こうした言葉掛けからスタートし、延々と続く話になっていく。段々と怒りが込み上げてきて、気が付いたら数十分…
理由を聞くことは不要です。
走っちゃったり、片付けができなかったり、といった行動にたいした理由はありませんから。先生ご自身が、大人として考えてもそうではありませんか?
なので「希望する行動」を伝えることで注意をします。
・走りません。
・片付けます。
・動きましょう。
このように「未来の行動を促す言葉」で伝えることで、子どもたちの反応も大きく変わります。
■言ったところで伝わらない
そうしたお話をすると「言ったところで伝わらない」という話をよく聞きます。
当然といえば当然です。
私たち大人だって、言われてできるなら苦労しません。サッカーやバレーボール等のスポーツや、華道や書道等の文化的活動に置き換えたらわかりますが、言われたところでできないのです。
だったら、言った後に、一工夫が必要です。
・一緒にやろう。
・やってみせるね。
といったことを先程の例に当てはめていきます。
・一緒に歩いていこう。
・片付けさせて。
・動き、見ててね。
お手本があれば、ちょっとずつでも変わっていきます。
■それでも、まだまだできません
できないことができるようになるには、一度の経験では足りません。それまでに何百回という失敗経験から誤った「型」を覚えているからです。
一度伝えた。
一度やってみせた。
これではもちろんできませんし、数回でうまくできるようにもなりません。
一年経ってほんの少し成長したら万々歳といった感じです。
先生が、こうした考え方を持てるようになるとイラッとする回数自体も減りそうですよね。それでも、人間ですから、どうしても腹が立つ時はあるとも思いますが…
■うまくいったら褒める。失敗してもフォローする。
そうした注意した後は、「見守って褒める」ことが大切です。
・少しでも歩いたら「うまい!それがお手本になる」
・片付けが少しでもできたら「言われてできるのが立派」
と、ポジティブに声をかけていく。これが褒めですり
■注意できる先生は、信頼される先生です
注意を怒ることと同じ意味にしない。
この一点を気をつけることができれば、注意できる先生は信頼される先生になります。
注意と褒めることがセットになりますから。
その繰り返しの中で、その子自身も、クラス全体もよい形になっていくかと思います。
