「マンガ禁止」にモヤモヤした話
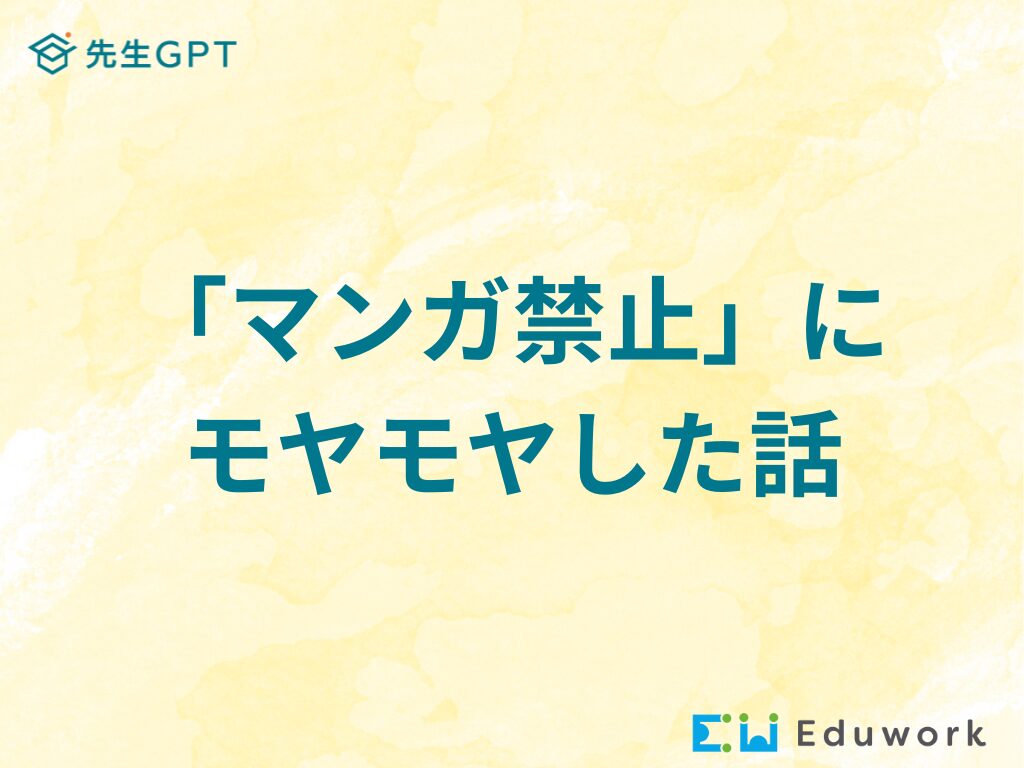
教室の後ろや横の棚に、学級文庫を設けている先生も多いと思います。
図書室からまとめて本を借りたり、自前で買った本を置いたり。
子どもたちが自由に手に取れるコーナーとして、空き時間や読書タイムに大活躍する学級設備です。
さて、この学級文庫にマンガを置くかどうかで、ちょっとした校内トラブルが起きることがあります。
■「教室にマンガ?いかがなものか」という声
私自身は、「可能であれば積極的に置く派」でした。
理由は単純で、子どもたちの読書量がまるで違うからです。
「読書の時間です」「本を読んでおいて」
このときに子どもたちが手に取るのは、やはりマンガ。
こちらが驚くほどの集中力で読みます。
結果として、そのマンガから知識を得ていたり、表現に感動したり、友達と語り合ったり。
私が教室に置いていた主なラインナップは次のようなものでした:
・火の鳥
・ブラックジャック
・三国志
・はたらく細胞
・ちはやふる
・風の谷のナウシカ
・宇宙兄弟
・サバイバルシリーズ
いわゆる「教養系マンガ」から、「アニメ化された人気作品」まで、ジャンルは広めに。
でも、この行動に対して、高確率で指導が入ります。
「学校でマンガを読むのはよくない」
「教育マンガならいいが、娯楽マンガはダメ」
「自費購入の書籍を教室に置くのはNG」
「隣のクラスと差が出るからやめてくれ」
中には、「何を言っても認められない」というケースもありました。
■ 私が試した“妥協案”いろいろ
なんとか折り合いをつけようと、いろいろなことをやってみました。
・「家に置けないので…」と持ち込みではなく“一時保管”として置く
・他の学年にも貸し出して“みんなの本棚”化する
でも、どうやってもダメな場合もあります。
管理職や学年主任によっては、「学校にマンガは不適切」という考えが絶対なのです。
そのたびに、「本当にそれでいいのかな?」とモヤモヤしながら、本を持ち帰りました。
■ この年齢で出会っておかないと、一生出会えない本もある
私は今でも、「教室にマンガを置く価値」はあると思っています。
もちろん節度をもってですが、読みたくなる本に出会えることが、将来の読書習慣につながるからです。
たとえば「火の鳥」や「ナウシカ」は、大人になって読むと見え方がまるで違います。
でも、小学生の頃に「なんとなく読んで面白かった記憶」がある子は、再読をします。
その学びは決して小さくないと思っています。
一方で、そうした入口を与えないままに「難しい本を読め」と言っても、そもそも本に近づこうとしない子もいます。
■ 皆さんの学校では、どうですか?
「学級文庫にマンガを置いている先生」はどのくらいいるのでしょうか?
逆に「ルールで禁止されている学校」もあるかもしれません。
「読書の自由」と「学校教育の一貫性」のバランス。
難しい問題ではありますが、「子どもたちが本と出会うきっかけをどうつくるか」という観点は、忘れずにいたいものです。
私の考えが正解とは限りません。
ただ、「子どもたちが夢中になれる本が、たまたまマンガだった」
それを問題とするのか、チャンスとするのか。
そんなことを、ふと思い出して書いてみました。
皆さんは、どう思われますか?
