【Q&A】授業の開始時から集中力がありません
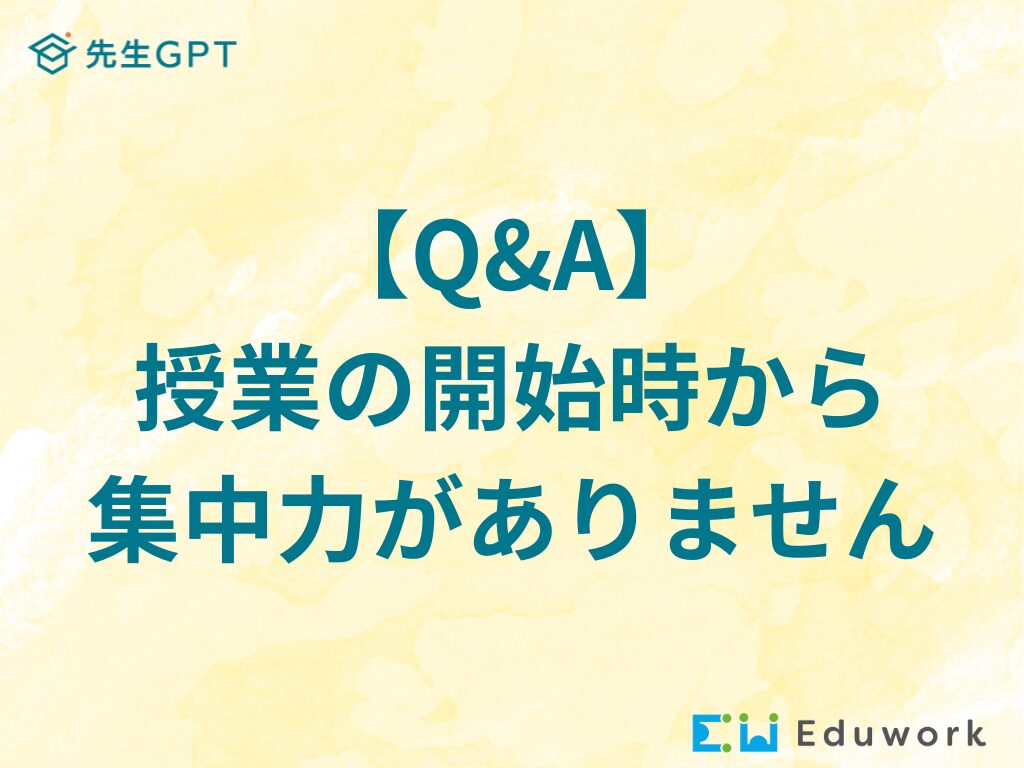
Q:授業の開始時から子どもたちの集中力がありません。その流れのまま、1時間ダラダラと過ごしてしまうこともあります。どうしたら授業をスムーズに始められるでしょうか?(20代・男性・3年目)
⸻
A:とてもよい視点をお持ちの先生だなと感じました。
この先生とは少しお話をさせてもらいました。
授業の始まりに、遅れて教科書を開く子がいる。
外を見ていたり、ぼーっとしている子がいる。
注意はするけど、すぐに怒ってしまう。
そんな状況に悩んでおられました。
でも、多くの先生はこのような状況を「子どもたちが落ち着かないから」と片づけてしまいがちです。
学級をつくるのは、あくまで担任の工夫。
そのことに気づき、自分から変わろうとしている姿勢がすばらしいと思いました。
授業の入り方を工夫することで、学級全体のリズムが変わっていきます。
今日は3つの観点から“スムーズな授業スタート”のヒントをご紹介します。
■ 工夫1:あえて“挨拶”をやめてみる
「これから3時間目の授業を始めます。よろしくお願いします」
授業のたびに交わすこのやりとり。
もちろん教育的な意味はあるのですが、「毎回同じ」だと、子どもたちにとっては“やらされごと”になってしまうことも。
そんな時は、“学習としての作業”から始めるのが効果的です。
たとえば、
・国語なら音読からスタート
・算数ならノートに月日とページ数を書く
といった流れにしておくと、自然と手が動きます。
形式よりも中身を優先する。
それがスムーズな導入につながります。
■ 工夫2:「発問」は“全員が答える形”に
「わかる人?」
「〇〇さん、答えてみようか」
こんなやりとりはよくありますが、それ以外の子は“答えなくていい人”になってしまいます。
そうならないためには、全員が関わる声かけに変えてみましょう。
・「全員で一緒に答えましょう」
・「3人で声をそろえて言ってみましょう」
・「〇〇のところまで、クラス全体で読んでみよう」
そうすることで、“聞いていないと置いていかれる空気”が自然と生まれてきます。
授業の入り口にこうした発問が入っていると、集中が高まりやすくなります。
■ 工夫3:「確認の動き」を入れる
どんなに声をかけても、動けない子はいます。
忘れていたり、まだ気持ちが乗っていなかったりする子もいます。
そんな時に叱るのではなく、“さりげなく巻き込む動き”を入れてみましょう。
・「隣の人と声をそろえています」
・「できた人は、班の人に見せてください」
・「終わったら静かに立って待ちましょう」
こうした“チェックポイント”があることで、子どもたちの行動にメリハリが出てきます。
1回では定着しません。
でも、繰り返すことで“クラスの習慣”になっていきます。
■ 授業は“雰囲気”で始まって、“習慣”で育ちます
授業の始まりに先生がどう動くか。
それは、その授業だけでなく、その日のクラス全体の空気を左右する大事な要素です。
ポイントは「どんな行動をしてほしいか」を明確に伝え、それを子どもたちと一緒につくっていくこと。
「この先生の授業は、こういう始まり方なんだな」
「気がついたら、みんながやっているな」
そんな空気ができてくると、毎回のスタートがとてもラクになります。
■ まとめ:授業の最初の5分は、1時間の価値がある
どんなにいい教材でも、どんなに面白い展開でも、
“始まりがぼやけている授業”では、なかなか力がつきません。
逆に、授業の最初の5分がシャキッとしていると、
それだけで「集中して受けるぞ」という空気が生まれます。
「どうせ始まりがうまくいかないから…」
と諦めず、今日から一つだけでも試してみてください。
きっと、少しずつ変化が出てくるはずです。
