何パターン知っていますか?子どもたちを指名する方法
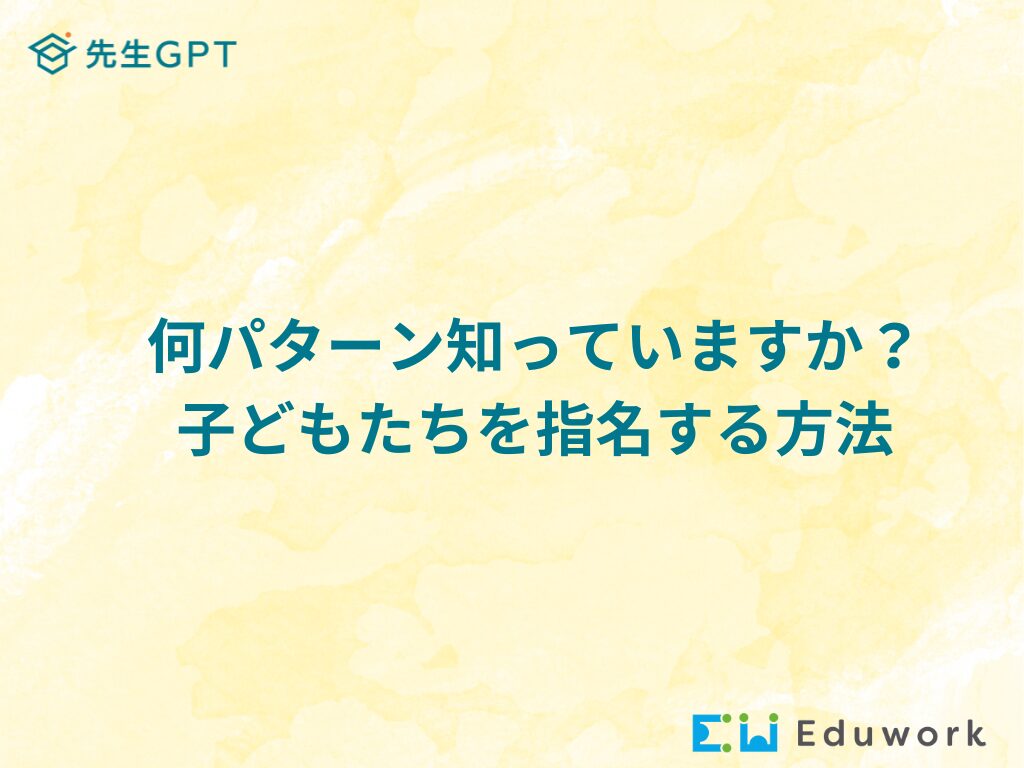
研究授業や授業参観で、他の先生方の授業を見る機会があります。先生が発問を出し、児童生徒が答える。本来であれば、ここに様々なパターンが考えられます。
しかし、2つのパターンで行われることが多いです。
最も多いのが、1人だけを指名する。次のような感じです。
「先生が1人を指名し、その子が答える。『正解』といって次に進む」
次に多いのが、何を答えても正解になるような質問を出し、複数人を指名する。ちらは、次のような感じです。
「主人公はどのような気持ちだったでしょうか?」
「悲しい」
「寂しそうだ」
「悩んだと思う」
特段の根拠が求められないような発音ですので、何を答えても正解。何かを話させるための指名方法です。
前者は、先生とできる児童生徒だけで授業が構成されます。後者は、一見盛り上がっているようには見えますが、内容的な深まりはありません。
もちろん、これらの方法を使っていけないと言うわけではありませんが、もっと他にたくさんの方法を使えた方が授業としては質がよくなります。
例えば、次のようなものです。
1.列指名
「この列の人全員立ちましょう。同じ答えになっても良いから全員答えます」
普段手を上げない児童生徒がいる場合でも、発言させることができます。考えていても発表できない場合や、他のことに気をとられて、そもそも考えていない場合でも授業に参加させることが可能です。
2.手を挙げた人全員指名
「手を挙げた人は全員に発表します。わかりやすくするために立ちます。発表した人から座ります」
先生から指名をされなければ発表することができないというのが一般的な概念です。こうした方法を使うことによって、意欲がある児童生徒全員が授業に参加することが可能となります。
この方法は、少し工夫をするとうまくいきます。
それは『次々に発表をさせること』です。
先生が、次はAさんのように指名をしたり、発表すべてにコメントを入れていると時間が長くかかります。
そこで、「自分たちで順番を考えて、できるだけ隙間を開けないように発表をしていきます。先生は最後に喋りますね」のように説明をしてスタートさせます。
はじめての時はなかなかうまくできませんが、数回繰り返す中で上手にできるようになっていきます。
3.隣の人を指名
「ではこれについて隣の人に説明しましょう。(説明をさせる)隣の人が言ったことを発表します。よい意見を言ったなぁと感じたら、手を挙げましょう」
自分自身が考えた内容を発表するのではなく、隣の人が考えたことを発表する形です。
はじめの頃は、自分自身の解釈が入ってしまい、隣の人の話した内容を上手に説明することができないと言う場面が多く見られます。聞いたことを伝える、といった力も育むことができます。
こうした指名方法は、組み合わせで使ったり、応用させて使うことで、より授業が盛り上がっていきます。様々な方法を取り入れて、学校の中で1番過ごす時間である「授業」をよりよいものにできたらいいなと感じます。
