教室で話したくなる紫陽花のヒミツを5つの教科で読み解く
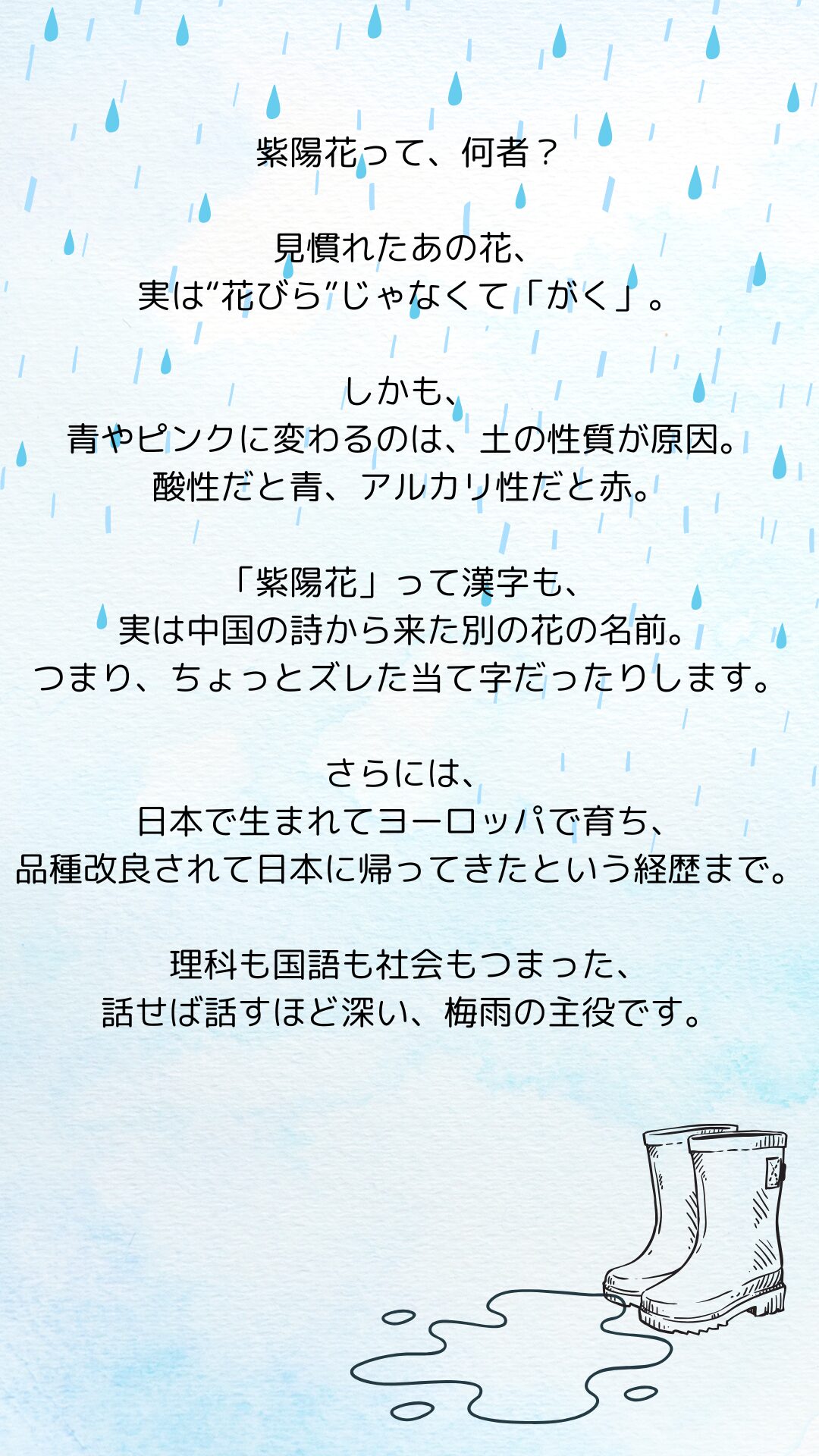
もうすぐ6月。
雨が続くこの季節といえば紫陽花です。
でも、よく見かける花なのに、「意外と知らないことが多い」花でもあります。
この紫陽花。
子どもたちと一緒に話すのにぴったりな豆知識が、様々な教科にまたがっています。
今回は、理科・国語・社会・生活・文化の5つの視点から、
「先生、知ってる?」と子どもに聞かれても応えられる、紫陽花の話をお届けします。
【社会の視点】
紫陽花のルーツは日本。
特に「ガクアジサイ」という品種が、もともと山の中などに咲いていた原種です。
紫陽花の“花”はどこにあるか知っていますか?
江戸時代、長崎に来ていたシーボルトが日本の紫陽花をヨーロッパに紹介し、そこで品種改良された「西洋アジサイ」が、のちに日本に逆輸入されました。
今、私たちが公園や学校で目にする「こんもりと丸い紫陽花」は、『日本生まれ・ヨーロッパ育ち・日本帰り』というユニークな経歴を持っています。
【国語の視点】
「紫陽花」って、漢字で見ると優雅なイメージを感じませんか。
でもこの漢字、本来のアジサイとは関係ないです。
「紫の陽の花」と書きますが、これはもともと中国の詩で使われていた漢字。
それが、日本でアジサイに当てられたと言われています。
中国語でアジサイを「紫陽花」と書かない理由とは
本来の語源には、「集真藍(あづさあい)」=青い色が集まった、という説があります。
つまり、音と意味が別ルートからきた、ちょっと不思議な名前の花です。
【理科の視点】
紫陽花の色が青だったりピンクだったりするのには、理由があります。
土の性質で色が変わるためです。
・酸性の土 → 青っぽくなる
・アルカリ性の土 → 赤っぽくなる
これは、紫陽花が土の中のアルミニウム成分を吸収するかどうかに関係しています。
酸性の土ではアルミニウムをよく吸収するため、青くなるという仕組みです。
土を変えると花の色が変わる紫陽花。
理科の実験みたいです。
【図工・生活の視点】
「この花びら、きれいだね〜」
そう思って見ている部分、実は花ではありません。
紫陽花の“花びら”に見える部分は「がく」と呼ばれる部分。
本物の花は、その中心にある小さな粒のような部分です。
がくが大きく目立つのは、虫に気づいてもらうための進化。
見た目だけで判断できない、裏方が主役になっている植物です。
現在は品種改良が進み、3000種類以上にもなったと言われています。
【外国文化の視点】
日本では、紫陽花は梅雨の風物詩として愛されていますが、
海外では少しイメージが異なることもあります。
ヨーロッパでは、紫陽花のひんやりした印象から、「冷たい愛情」や「無関心」といった意味で使われることもあるそうです。
実際に、お葬式の花として使われることも。
一方でイギリスでは、「はかない美しさ」「変化する命の輝き」など、詩的に表現されることもあり、文化によって印象が異なる花なのです。
紫陽花の話は、理科にも、国語にも、社会にもつながります。
子どもたちの生活や心に寄り添う話題にも繋げられます。
「雨ばっかりでつまんないな〜」という声が聞こえてきたら、ぜひ紫陽花の話をしてみてください。
そして、そんなちょっとしたやりとりが、学びにも、人間関係にも、静かに効いてくる季節なのかもしれません。
