「水筒OK」のその先へ:意味ある水分補給を考える
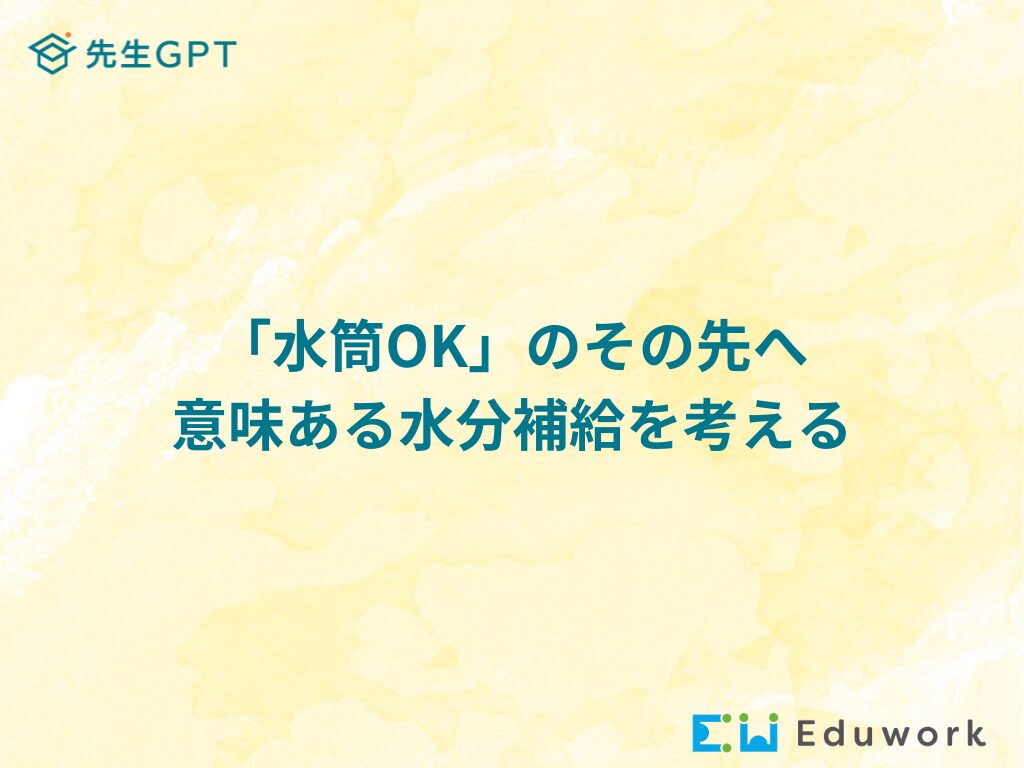
「水筒OK」のその先へ:意味ある水分補給を考える
水やお茶を学校に持って行く。
欠かせない習慣です。
以前は休み時間だけだった水分摂取が、今では授業中でも推奨となっているところが多いです。
「授業中に水?」のように指導対象だったのですが、今では机上に水筒を置くことも珍しくなくなりました。
体がまだ小さく、汗腺の発達も未熟な子どもたちは、気づかないうちにどんどん体内の水分を失ってしまいます。
「のどが渇いた」と感じるときには、もうすでに脱水が始まっているとも言われます。
だからこそ、こまめな水分補給は「予防」であり「習慣」でもあるのです。
でも、なぜ「水」と「お茶」なのでしょうか。
気になって調べてみました。
これは大きく3つの理由があるようです。
1.体に吸収されやすい
水やお茶には、糖分や添加物、カフェインなどがほとんど含まれていません。
消化を必要とせず、胃腸に負担をかけずにすぐに吸収されやすいという特徴があります。
水分は主に小腸から吸収されます。
糖分や塩分が多すぎると、かえって腸の中の水分バランスを崩し、
「体内に取り込むまで時間がかかる」「お腹がゆるくなる」といったことも起きます。
また「飲み物の温度」も吸収に大きく関係しています。
人の体温に近い「15〜20℃前後」が、もっとも吸収効率がよいそうです。
冷たすぎると胃腸をびっくりさせて吸収を遅らせ、
熱すぎても体温調節に負担がかかると言われています。
そのため、常温の水やお茶、もしくは少し冷たい程度がベスト。
氷をたっぷり入れたキンキンの水は体にとってあまり効率的ではありません。
でも…私、個人的にはキンキンの水がいいです。
この辺りはバランスなのかも。
2.のどの渇きだけでなく、体温調節にもつながる
人は汗をかくことで体温を調整しています。
その汗の90%以上は水分で構成されており、体内の水分が不足すると、
「うまく汗がかけなくなる=体温を下げにくくなる」という状態になります。
つまり、水を飲むことは、単にのどの渇きを癒すだけでなく、
体が「自分の熱を下げる力」を保つためにも不可欠な行為です。
また、体内から冷やすという意味でも、水やお茶の摂取はとても効果的です。
とくに運動後や炎天下の後には、冷やしすぎない水分を数回に分けて飲むのが理想的です。
3.学習や集中力の維持にも関係する
「体重の1〜2%の水分を失うだけで、脳機能に明らかな影響が出る」というデータも報告されています。
《引用》Hydration and Cognitive Function in Children(英文ページ)
たとえば体重30kgの子どもであれば、わずか300〜600mlの水分不足で、記憶力・注意力・判断力が低下しやすくなるのです。
これにより、下記のようなことが起きる可能性があります。
・授業中の集中力の低下
・イライラしやすい、落ち着きがない
・書き間違いが増える、うっかりが目立つ
・理由なく「やる気が出ない」
これらは性格や気分ではなく、軽度脱水が原因の見えにくい不調である可能性があります。
また、喉が渇いていると感じると、注意が内側(自分の不快感)に向いてしまうため、
目の前のやるべきことに集中できなくなるとも言われています。
4.清涼飲料水が適さない理由
「ジュースでもいいのでは?」「スポーツドリンクのほうが飲んでくれるし…」
という声もありますが、日常的な水分補給としては以下の理由で推奨されません。
・糖分過多による吸収遅延と血糖値の乱高下
→一時的に元気になったあと、逆にだるくなったり眠気が強くなったりすることがあります。
→慢性的な摂取は虫歯や肥満、食欲低下の原因にも。
・飲みすぎてしまう味の誘惑
→甘いものは飲みすぎにつながりやすく、1日で1リットル以上飲んでしまうケースも。
・腸での吸収に負担がかかる
→糖濃度が高いと、水分が腸にとどまりやすくなり、結果として「のどが渇きやすくなる」という逆効果に。
日常的な飲み物としては、やはり「水」または「麦茶・ほうじ茶などのノンカフェインのお茶」が最良の選択肢となります。
水とお茶を飲むことは、「ただの水分補給」ではなく、からだのためのケアであり、こころの安定にもつながっています。
仕事の中で休み時間や体育の後に行っている「水分摂りなよ〜」といった声かけ。
より意味を理解した上で伝えていくと、熱中症防止に効果が高くなりそうです。
