先生を辞めても生活していくことができるのか
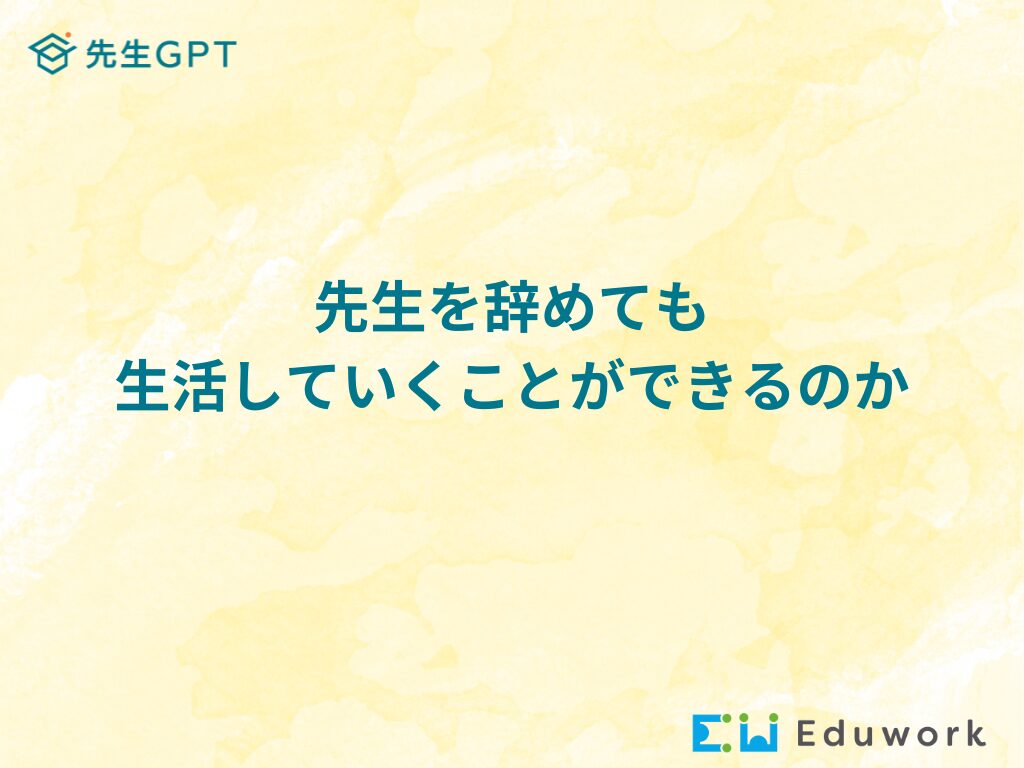
先生を辞めても生活していくことができるのか
現役学校教員の方から、時々相談があります。
以前は知り合いの先生が多かったのですが、最近は数回会った程度の先生や、全く知らない状態で「初めて連絡を…」という方もいらっしゃいます。
そういった先生の最も大きな悩みは「辞めても生活していけますか?」です。
私が、もともと教員で、今は会社を経営していて…という経歴を講演会やネットなどで調べて連絡をくださいます。
で、生活していけるか?という質問。
極論すれば、どんな形でもよいのであれば可能です。でも、そういった意味ではなく、質問の意図としては、
現在の生活水準を維持することができますか?
です。
あまりにご相談が多いので、一度整理をしておこうと思います。
1.結論
現在の生活水準は人によって違うが、それを調整すれば概ねやっていける、です。
また、逆に考えると、先生の場合は給与規定に決まりがあります。努力次第でそれ以上のお金が目指せるのも民間の魅力です。
2.お金と福利厚生からみた「現在の生活水準」
学校の先生をしている方の生活水準は、民間企業の方と比較すると高い傾向があります。平均年収から差が出てきます。
年収に関しては、様々なデータがあるのですが、一例を挙げると、次のような感じです。
民間企業 平均年収 約540万
先生 平均年収 約660万
月に10万位の差が出ます。
貯金をほぼしない状態で給与をほとんど使っている先生であれば、生活水準は下げる必要があります。
反面、毎月数万円以上貯めている先生であれば、その額を調整すれば、生活水準をほぼ下げる必要はなくなると考えられます。
また、生活水準は、お金の面だけではありません。福利厚生の観点からも考える必要があります。
公立学校では、有給休暇の付与日数が20日間です。多くの中小企業では、年次休暇は10日程度です。
そのように話すと、先生方は「学校ではなかなか取ることができない」とおっしゃいます。両方経験した感覚では「それは学校の世界ではね〜」と思います。
学校はかなり取りやすい環境です。当日の朝に有休申請を出しても通ります。長期休暇ではまとまって取ることと可能ですし、放課後に1時間だけ取るといったこともできます。
「代わり」がいるからです。
転職先が、企業であれば、無計画な有休を繰り返したら、きっちりと査定に出てきます。それだけではありません。周りから白い目で見られることもあります。
もちろん、子育て中で子どもが熱を出したなどの理由であれば、比較的理解は得やすいとは思います。それでも先生よりははるかに取りにくいっていうのが実感です。
労働者の権利ではありますが、人数が少ない分、周囲への影響が大きいためです。
そうした今の『先生』としての働きぶりを照らして、現在の『生活水準』を検討する必要があります。
3.転職をするのか、独立をするのか
こうした相談をされる先生は、ほぼ100%「独立」を前提に話をされます。
自由が欲しいから
です。
思っていた先生像と違う、管理職の顔を伺わなければいけないことがしんどい、自分が正しいと思うことをさせてもらうことができない…
これらは、公務員から民間企業の社員になったとしても全く同じです。
自由を求めるのであれば「独立」は正しい選択肢だと私も思います。
そのような選択肢になった時、まず1番にある大きな壁は家族です。
本当に生活をしていくことができるのか、という不安は当然です。それを、
「どうしても説得することができないんです」
と相談される先生の多くがおっしゃいます。
詳しく話を伺っていると、当然だと思います。
何をするのか、いくらかかるのか、赤字の期間はどれぐらいなのか、黒字になったらいくら入るのか、将来的にはいくらを目指すのか、それは何のためにするのか。
学校であれば、職員会議提案をデータで用意します。事前に要となる先生に話を通しておくといった調整も欠かせません。
それなのに、学校よりも大切な家族のために何の資料も準備せず、思いと勢いだけで押し通そうとするのであれば理解を得るのは難しいです。
また、そうした資料を準備しても、まだ理解を得ることはできません。家族からの、
「あなたには、それを実行するための知識や経験があるのですか?」
という質問に「はい」と回答ができないからです。これは誰にもできません。やったことがないからです。
そこで出てくるのが、信頼できるサポーターです。「この人から伴奏支援をしてもらうから大丈夫。この人はこういう人だから」のようにして理解を求めていきます。そうした人を探して、学ぶ。それも家族に伝える。
一度でできることではありません。
何度も話をして理解を得る。
この段階で半分くらいの方があきらめます。
そのほうが良いと思います。
自分のことを理解してくれているはずの家族から協力を得られないようであれば、独立をしたとしてもうまくいかない可能性が高いからです。他者から理解を得るというのが独立をするための条件になってきます。家族にわかってもらえない方が、それをすることは困難です。
4.仕事の条件と放課後等デイサービス
辞めることを考えている先生やその家族にとって、条件を並べていくと、仕事の幅はある程度限定されていきます。
例えば、次のような条件があるのではないでしょうか。
・現行給与以上を維持したい。
・自分や家族の時間を大切にしたい。
・仕事に対しての決定権を持ちたい。
こうなってくると「経営者」の道が大きくなってきます。選ばれた人だけがなれる役職なのかというとそんなこともありません。日本の生産労働人口の2%は経営者だといわれています。
では、何の仕事をするのか。
例えば、弊社では、下記のようなことをしています。
・放課後等デイサービスの運営
・企業や行政機関との伴走支援→ここに放デイの支援も入ります。
・学校教育向け教材開発
・教員向けアプリの開発
この中だけで考えると、最も成功率が高いのが「放課後等デイサービス」です。6歳から18歳の障がいや発達に課題のある児童生徒を療育する施設の運営です。
成功率が高い理由が2つあります。
一つは、多くの成功事例があるからです。皆さんのご自宅や学校の近くにもいくつかの放課後等デイサービスがあるのではないでしょうか。
それだけの数が運営されている実績があるのは、収益部分がシステム化されていることが理由です。国なり、自治体なりのルールに従って、自分自身のオリジナル療育や教えてもらった魅力ある療育を提供すれば、決められた点数の収益が入ってくる。
お医者さんのシステムと似ています。〇〇をしたら〇点となり、いくらいただく。
こうしたシステムに学校の先生は慣れているため、なじみやすいです。
もう1つの理由が資格です。放課後等デイサービスを運営するのに必須の資格が「児童発達支援管理責任者」です。この資格、取得ハードルかかなり高いです。実際に働いたという実務経験が必要になるからです。ところが、先生という仕事をしている場合は、実務経験としてカウントをされます。
放課後等デイサービスの運営であれば、先ほど挙げた、
・現行給与以上を維持したい。
・自分や家族の時間を大切にしたい。
・仕事に対しての決定権を持ちたい。
といった部分はかなり担保されます。
やり方次第では、それ以上も視野に入ります。
5.じゃあやろう、の前に…
多くの先生が、勤務をする前に教育系大学で4年学んでいます。初任者研修で1年間指導をされています。それ以外でも定期的に研修講座を受けています。
そうしたものは「役に立たない」とおっしゃる方もいますが、そうではありません。
それらの学びの中で、少しずつでも、知識や経験を深めて今があるのだと思います。
職業を変える。
これは、仕事の仕方、人との付き合いの仕方、お金への考え方、就く仕事のルール…
そういったものが全て変わるということです。
学ばないで進めば必ず事故ります。
誰かから教えてもらうことが必須です。
それは、経験をしたことがない人ではダメです。
やっていない人は、あれやこれやを言って「だから無理」で終わらせます。
相談相手は、必ず経験をして、かつ、うまくいっている人にすることを強くお勧めします。
弊社に相談をするのでも構いませんし、もしお近くにいるのでしたら、その方に聞かれるのが1番良いかと思います。
自分で採用した仲間と仕事ができること。
自分で決断したことを進められること。
自分で稼いだお金で次の選択肢を取ること。
責任は大きいですが、やりがいはあります。私の場合は…というケースにはなりますが、以前よりもより自分が好ましいと思う教育ができるようになりました。もちろん、学校教員だからこそできるものもあります。それでも、私にとっては転職してからの方がよかったかなと。
これは人によって違うと思います。
学校の先生を続けた方がよい方もいますし、そうではない方もいます。
どちらがよいという話ではなく、それぞれの人に合った仕事があり、それをした方がよいと考えるからです。
「決断は短く、端的に」は大切ですが、それと、同時に「深く考えること」も必要です。
答えを決めて考えるのではなく、様々な道を考えて、その上で選択されるとよいのではないかなと思います。
