“守る”のか“育てる”のか
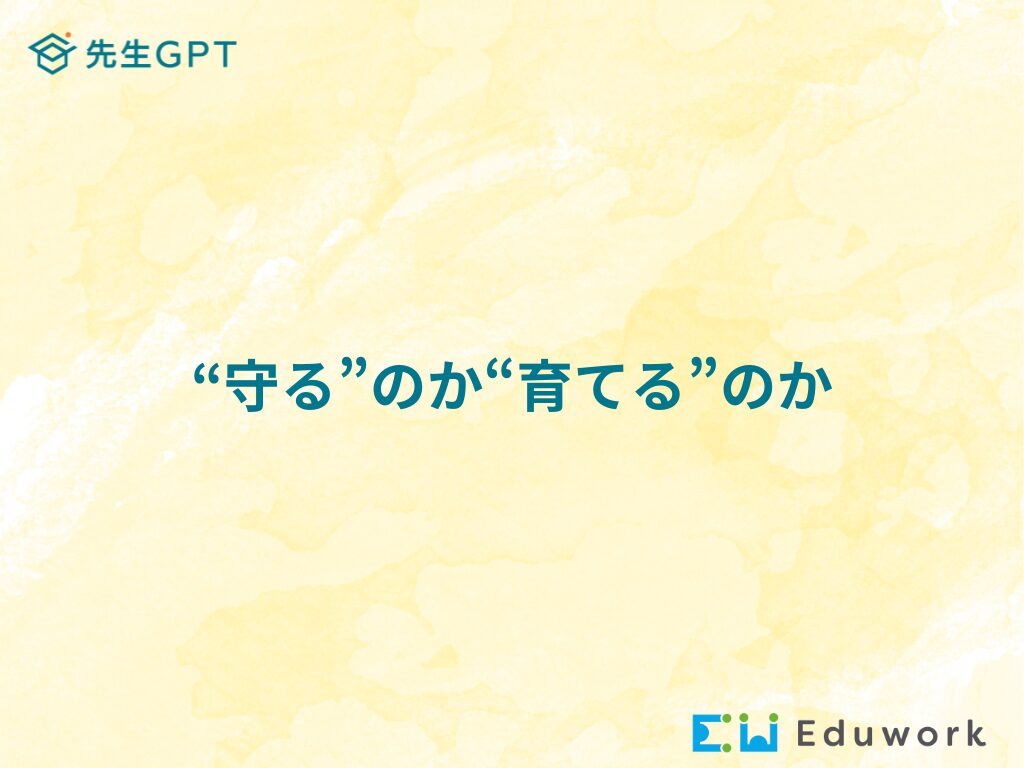
最も「働くことが難しい」と言われる重度知的の方たちが多く働く株式会社ハートコープきょうとに弊社社員と見学に行きました。
古紙、内袋(ビニール袋)、発泡トレイのリサイクル
コープの通い箱の洗浄
などを行っている企業です。
学校現場にいる時、重度知的の方たちへのイメージはかなり偏ったものでした。
横たわっている
暴れている
指示が通らない
話が聞けない…
これ、私だけではなく、多くの先生方が思っているイメージなのではないかと思います。
こうした見学で現場に行くと、その考えは払拭されます。健常の方との判別がつかないくらい、むしろ彼らの方が働く、となります。
そして、質疑に上がるのは、どうやったらあれだけのことができるようになるんですか?という質問です。
回答はどこに行っても類似したものになります。
「始めからできるわけではなかった」
でも、これっていわゆる健常の方でも全く同じ。初めてその職場に行っていきなり戦力になれるわけではありません。いくばくかの時間が必要で、その時間で得た知識や経験を得て「使える」ようになっていく。
もちろん障がいがある場合の方が時間がかかるケースは多いですが、それでも一度できるようになればきちんと継続します。
離職しない。
これが結構難しく障がい者雇用でも離職問題はあります。しかし、ハートコープきょうとでは、それが著しく低いことも教えていただきました。
これ、「福祉のプロ」の仕事ではないということを強調されていました。
今までコープの店で仕事をしていたいわゆる普通の会社員が始めた特例子会社です。
もちろん、プロのサポートも受けてはいますが、メインプレーヤーは障がいに対して知識も経験もなかった方たちが10年かけてこの会社を運営してこられました。
障がいだから…ではなく、人と人なんだよな、と改めて感じさせられました。
就職に向けて障壁になることは?という問いの回答は、弊社やよく話をする企業とやはり同じようなものでした。
保護者、です。
実際に働いてもらう企業としては「できる」と思う。
送り出す学校や放デイとしても「できる」と思う。
でも、かわいさあまり、守ってあげたいと思う考えが強すぎるあまり保護者が止めたり、健常だろうが、障がいだろうがありえる乗り越えなければいけない壁に対して「クレーム」という形で出して成長を止める行動をしてしまう。そんな保護者が多すぎる。
最近話した学校ではそれが多すぎて、就職支援が難しくなっているという話がありました。
もちろん、障がい者全員が働けるとは思いません。逆も一緒。全員が働けないとも思いません。でも、等しく訪れるのは『親亡き後』です。
その時に向けた1人じゃないという自立、お金の面での自立、お手伝いしていきたいなぁと改めて思いました。
