夏休み明けに向けたメンタル準備あれこれ
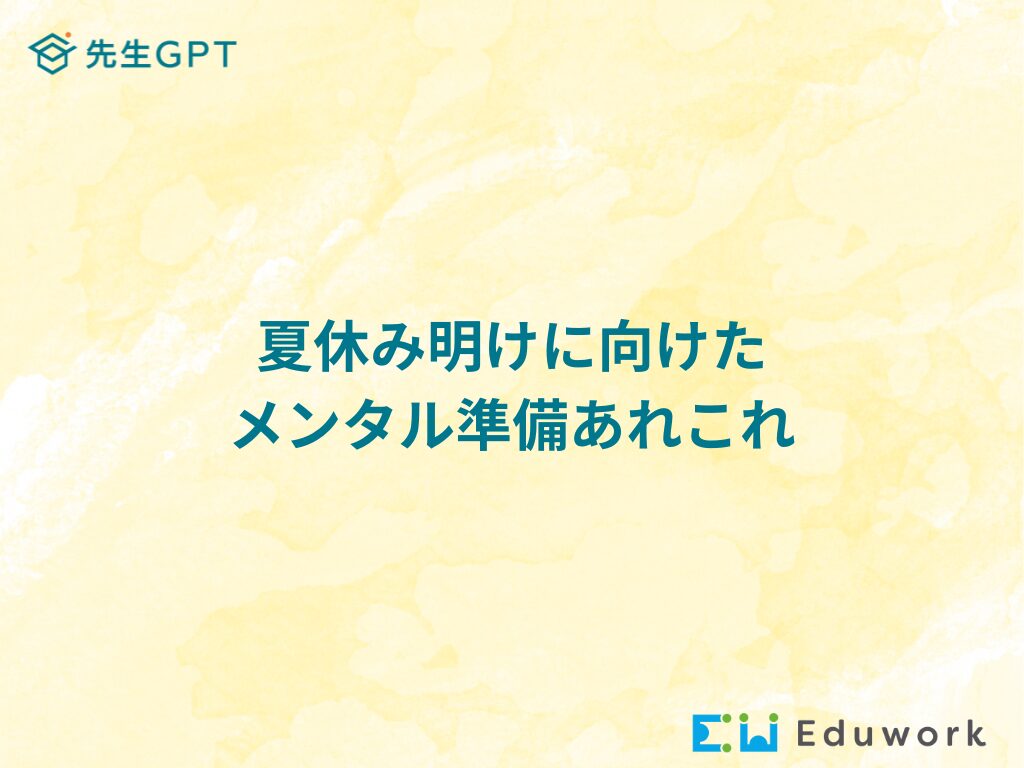
お盆も終わりました。今週末や来週から学校というところも多いのではないかと思います。
先生の立場で1ヶ月も子どもたちと会わないと、寂しくも思いつつ、でも、ちょっとホッとするという期間かと思います。とはいえ、まもなく始まる2学期。
どのように準備をしていけばよいのでしょうか?
私の場合はこうしていたというのをいくつか紹介します。
【1】休む
やる気を出すために休みます。
打ち合わせや会議、研修が入っていて、なかなか休むことができません。このようなお話がたくさんいただきますし、私の周りも休めない方が多かったです。
それでも、子どもたちが学校に来ている期間よりは、はるかに休みやすいです。
年休が余ったまま、繰り越し、消えていく、のような若手時代もありましたが、ある校長先生と出会って変わりました。
その校長先生は次のように話されました。
「会議や研修、たくさんあります。立場的には出ていただきたいです。特に、対外的なものに関しては、欠席率を見られるケースもありますので。でも、個人的には休んでいただきたいです。私が若手の頃は、先輩教員から休め休めと言われて年休消化をしていました。その期間で相当なリフレッシュができたことも自覚しています。休めるならば休んでください。もちろん2学期以降でも申請をしていただいたら、権利ですので休むことはできます。それでも夏休み中の方が休みやすいので」
それからは、遠慮なく休むようになりました。
【2】食事
それでも、学校に行って研修や仕事をしなくてはならないという場合もあります。そうした時は、食事に出ていました。日常的には給食で、なかなかランチをする機会はありません。こういう機会にと、できるだけ先輩や若手を誘っていくようにしていました。
その時の注意点は「時間を守る」です。
教頭先生の中には「普段なかなか時間が取れないから、ゆっくり行ってきてよい」と送り出してくださる方もいました。
この言葉を拡大解釈して、2時間、3時間と帰ってこない学年もありました。そういう学年は、ランチから帰ってくると、大抵疲弊しています。特に若手が。話をしたい教員が話し、聞く側は数時間にわたり同じような話をされ続ける。しかも、そういう場合の多くは愚痴。疲れてもおかしくありません。
もし行くなら帰りの時間をハッキリさせて、がオススメです。
【3】学年会
担任をしていると、学年の中にベテランから若手までがいるケースがあります。
学校あるあるで『学年内で揃えて』宿題を出したり、指導法を合わせたりすることがあるのですが、これは不評です。私はこうやりたいのに!と不満が上がります。
私が学年主任の時は「学年内でバラバラでもよいので、学習指導要領の範囲内で自分のやりたいようにやってください」とお伝えするケースが多かったです。
しかし、これも不満がよく上がりました。自由に、って言われたって困る!という不満です。
どうすれば!?の世界ですが、多くの先生が考えているのが「私のやり方にみんな合わせて欲しい」なんだなと理解しました。
学年会はそれを合わせれる場なのだろうと考え、そのようにするとうまくいきやすくなりました。
夏休み明け前の学年会は、こうした話をするのにちょうどよい時間があります。他の先生方の希望する指導法や考えていることを聞く時間にしてもよいのかなと感じます。
