爪切りの誕生から現代まで
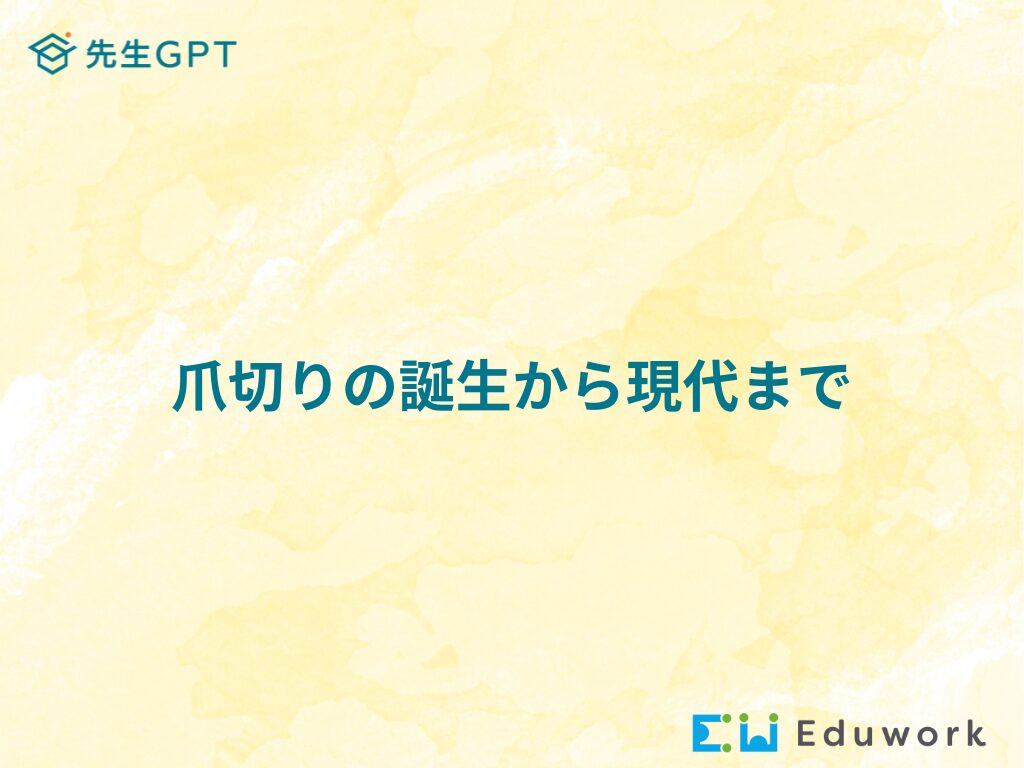
爪切りを嫌がる子どもたち、いませんか?
昔からそうなのかなーと思って調べてみました。
好きとか嫌だとかはなかったのですが、ちょっと面白かったので簡単に整理してみました。
こういう話を教室ですると、興味深く聞いてくれたりしますよね。
爪を整える行為が記録を探っていくと、古いのは古代エジプトの紀元前3000年頃のものがあるそうです。
ちょうどその頃の古代中国でも「爪を長く伸ばして身分を示す」と言ったことがあったそうです。ちなみにこちらは爪を赤色や金色で染めることによって地位の象徴を示していたとのことで、現在のネイルにもつながっていきそうな話です。
ただし、当時はもちろん爪切りのような精密な道具はなく、小刀や石製のやすりで爪を削っていました。
日本では、平安時代の貴族が小刀を使って爪を整えていたと記録されています。
この時代には、爪を切ることに「身を清める」という意味合いもありました。
さらに、切った爪の扱いには大きな注意が払われていました。
捨て方を誤ると災いが降りかかると信じられていたため、燃やしたり土に埋めたりすることで「厄を避ける」という風習がありました。
爪は体の一部、魂のかけらと考えられ、軽々しく捨てるものではなかったのです。
今のティッシュに包んで捨てる、のような文化ではなかったようです。
現在、私たちが慣れ親しんでいる「テコ式の爪切り」が生まれたのは19世紀末のアメリカです。
小さな金属パーツを組み合わせて片手で使えるようにした仕組みは画期的で、すぐに世界中に広まりました。
日本には明治時代に伝わり、その後は国内メーカーによる改良が進みます。
戦後には貝印やグリーンベルといった企業が切れ味や安全性を工夫し、日本製爪切りは世界的に高い評価を得るようになりました。
「日本のお土産」として海外に持ち帰られることも多く、今では精密な刃物文化の一端を担っています。
一方で、爪にまつわる文化的なエピソードも数多く残されています。
「夜に爪を切ると親の死に目に会えない」という迷信は有名です。
これは、夜に明かりの少ない中で爪を切るとケガをする危険性があったことから生まれたとも言われています。
江戸時代の人々が切った爪を大切に処理していたことからも、爪を「ただのゴミ」とは考えていなかったことが伝わってきます。
近代に入り、爪切りはさらに多様化してきました。
巻き爪用の特殊なカーブをもつ刃、赤ちゃん専用の小型爪切り、足の爪専用に設計された大型タイプなど、用途に合わせて選べる時代になっています。
また爪やすりや爪磨きとセットになった製品も多く、爪切りは「身だしなみツール」としての役割を強めています。
さらには「高級爪切り」が登場し、ギフトや海外向けのプレミアム商品としても人気を集めています。
精密さと実用性が評価され、「日本の爪切りは切れ味が違う」と評判になることも珍しくありません。
こうして振り返ってみると、爪切りは単なる生活用品ではなく、人々の文化や価値観を映す鏡のような存在です。
爪を整えるという行為には、「清潔さ」「礼儀」「厄除け」といった意味が込められ、さらに技術革新や産業の発展とも結びついてきました。
こんな話をしても、爪切りを好きになるとまではいかないかと思います。
それでも少しでも子どもたちが興味を持ってくれたらいいなと考えています。
・国立国会図書館レファレンス協同データベース「昔の人はどうやって爪を切っていたのか?」
https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000284680&page=ref_view
・note「小さな道具の大きな歴史」
https://note.com/history_taro/n/n7f31a0bdfee7
