学級文庫に置いておく本の工夫
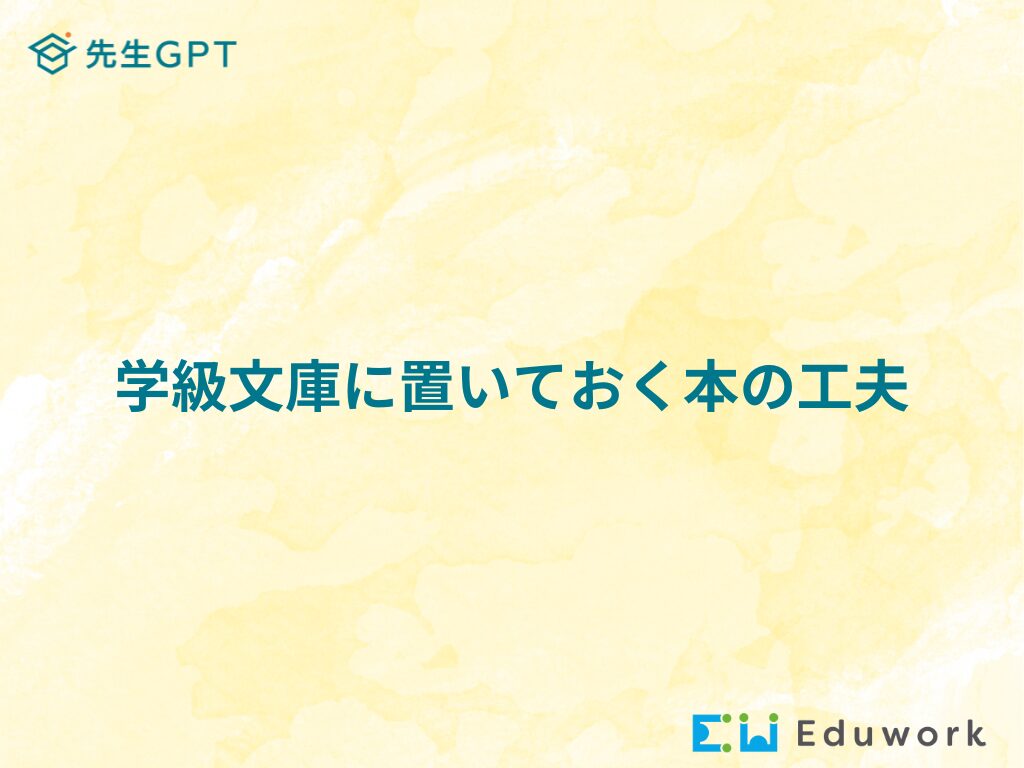
教室の後ろのスペースを使って書籍を置く。
これだけで学級文庫の完成です。
子どもたちが本を手に取る学級文庫にするためには、2つ工夫が必要です。
1つは冊数です。子どもの数の2倍ほどの本を入れておくとよいです。私は50冊ほど入れるようにしていました。こちらがオススメだと思って入れた本でも読まれないケースが多々あります。それでも、50冊あるとそういった読まれにくい本のことも吸収できます。
もう1つは、入れ替えです。1ヶ月に一度程度入れ替えると新鮮さが薄れないので、手に取られる学級文庫になっていきます。
自費で書籍を揃えるのは大変です。そこで学校図書館や公立図書館を活用していました。
校内にある図書館でも、行かない子どもは行きません。教室の後ろにあるから手に取るという場合も多いです。
また、蔵書が圧倒的に多いのが公立図書館です。多くの市町村では、学校のクラスごとのカードを作ってくれます。それを使うと数十冊の書籍を貸してくれます。
こうした取組をしようと考えると時間がハードルになります。そこで私は隔月で学校図書館と公立図書館を使い分けていました。
学校図書館を使う場合は、中間休みや昼休みなどに子どもたちを連れて行きます。休み時間に子どもたちと一緒に50冊ほど選び、彼らに運んでもらい、教室の後ろに並べてもらいます。いつもは教室で絵を描いたり、本を読んでいたりする子どもたちが積極的に手伝ってくれます。
公立図書館を使う場合は、放課後に会議等がない日の勤務時間中に行っていました。初めは1人で行っていましたし、公立図書館の司書さんからも「学校の先生がこうやって借りに来るのは、とても珍しい」と言われていました。しばらく続けるうちに、興味を持ってくださった他の先生方と一緒に行くようになりました。隔月くらいのペースだとリフレッシュにもちょうどよいです。
読書の秋。
手間をかけずに、こういった取り組みをしてみると、本好きの子どもたちになっていくかもしれませんね。
