燃え尽き症候群を予防する
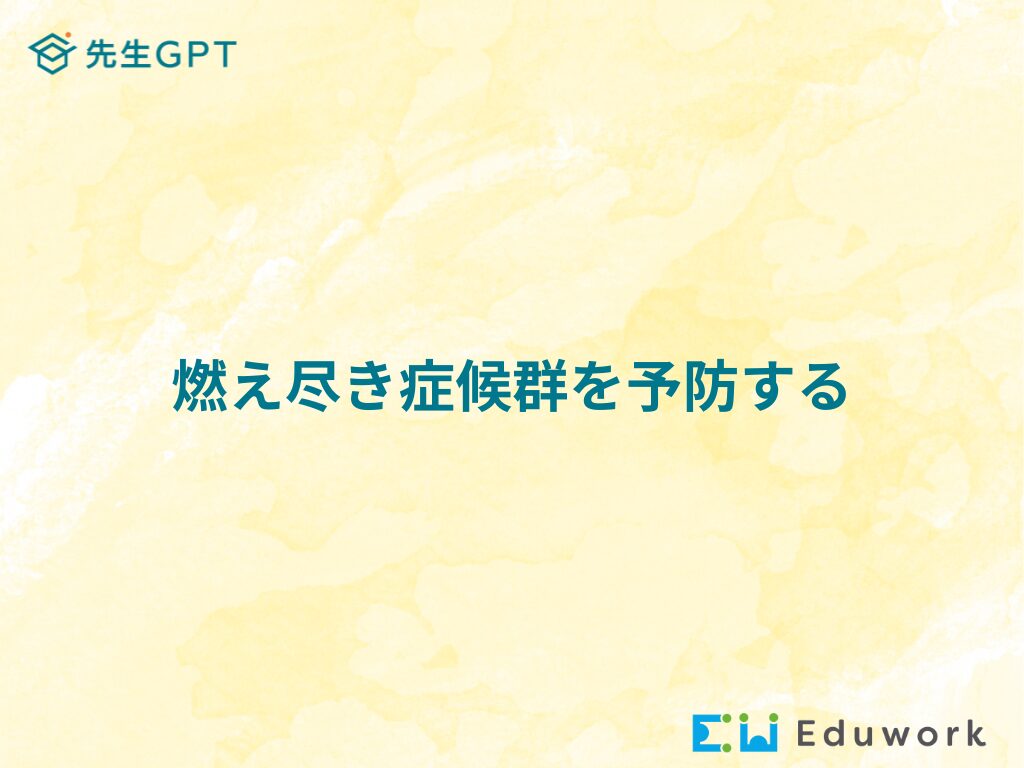
運動会や合唱コンクールのシーズンになりました。
この時期によく言われるのが「燃え尽き症候群」です。
大きなイベントが終わって、ほっとして、クラスがガタガタと崩れていくという相談が多いです。
「どうしたらいいのか?」
と話がある頃には、かなり悪くなっている印象があります。
きちんと『魔の11月』に向かっている形です。
それを避けるために、どのようにしたらよいのかを紹介します。
まず、多くの場合、先生自身がそのガタガタを引き起こしています。自分はそんなつもりがなくても、児童生徒たちには「今から崩れてきなさい」と指示をしています。
例えば次のようなことを伝えていないでしょうか。
「運動会(合唱コンクール)が終わって、ホッとしたのではないでしょうか。気が抜けやすい時期ですが、しっかりと勉強やクラブ活動を頑張っていきましょう」
ホッとしたのも、気が抜けたのも、先生です。大きなイベントが終わってひと段落。気持ちは分かります。
でも、これって児童生徒に『ホッとする、気が抜けるというのが仕方ない時期』と教えています。
こうした話を抜きにして、さっと授業に入った方が安定します。
次に、終わった後の対応です。
それでもやっぱりクラスに少し落ち着きがないなと感じた場合は、押さえつけないほうがうまくいきます。
「静かにしなさい!」
「いつまでうるさくしているの?」
「静かになるまで〇秒かかりました」
児童生徒の方からしたら『また言ってるわ』です。
こうした行動の初期。そうした行動している児童生徒は一部です。
できている子に対して「早いな」「運動会で身についた力だね」「うれしいな」と伝えたほうがうまくいきます。
悪い子をしたら叱られるではなく、良い行動したら褒められるとなるからです。
先生の叱るという指導の90%以上は、褒めるに転換できます。
また、これは次年度からになりますが、本当は運動会も合唱コンクールもあらかじめ準備をしておくことができます。
表現運動は一つ一つの動きの組み合わせです。4月から2週間に1つずつでも教えていくことができれば、夏休み明けには10の動きを覚えている状態からスタートができます。
合唱コンクールも同じです。夏休みが終わってから毎朝練習をするのではなく、あらかじめ少しずつその意義を伝えたり、練習をしたりしておく。
実際に私もやっていましたが、こうしたことをやろうとすると周りの先生が「早すぎる」「この忙しい時期に?」と止めようとすることが多かったです。
早すぎるから楽になります。
どの時期でも暇ではありません。
段取りの問題です。
一度考えて計画的に進めていけば、無理が出ません。
無理が出ないので、燃え尽き症候群の予防になります。
こうしたことを考えておくと、学級経営がよりスムーズになります。
