ちょんまげ時代からの「ありがとう」
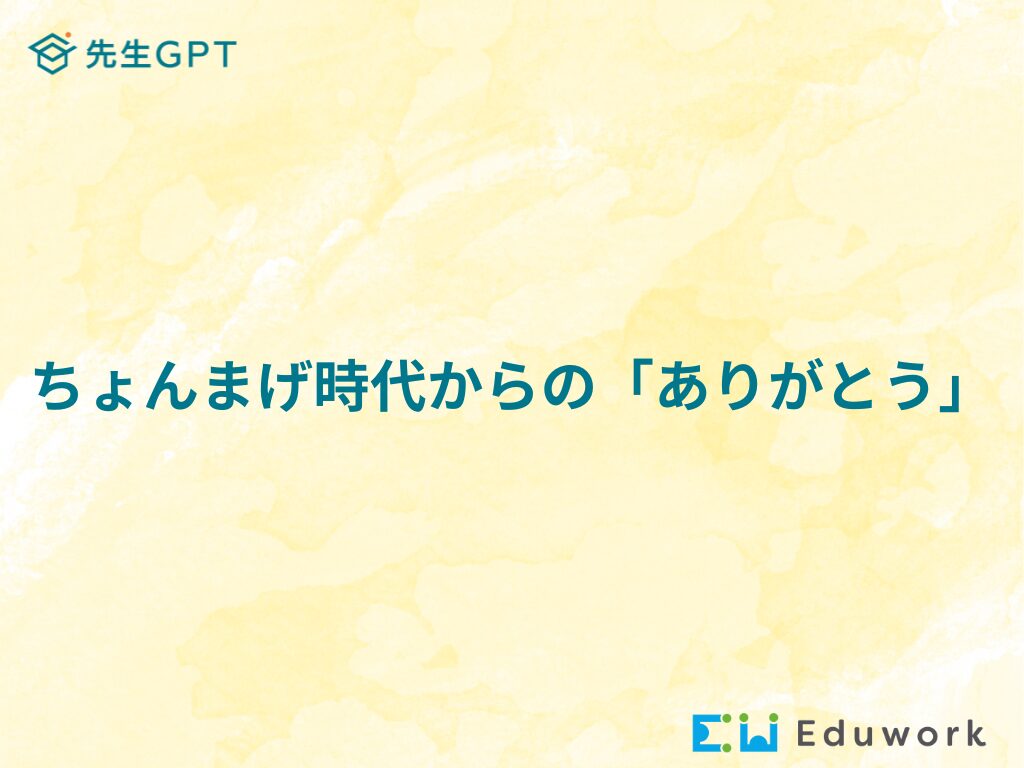
「ありがとう」という言葉は日常的に使われます。
先日、知り合いの和尚さんと話をしている時に「元々は仏教用語」と教えていただきました。
『有難い』が語源なのだそうです。
「めったにない」を「有ることが難しい」と表現し、感謝を伝える意図で使われる言葉だと教えてもらいました。
それから興味を持って調べてみると、
・奈良時代から平安時代
有り難しで使われていた時代。
珍しいことや、めったにないことで貴族などによって使われていた。
・平安時代から室町時代
他の人からの親切に対して感謝の気持ちで使われるようになった。
・江戸時代
庶民にも広がり、現代の「ありがとう」の意味で使われるようになった。
ということは、私たちが今使っている「ありがとう」は江戸時代から使われている意味になります。
もっと難しい現代では伝わらないような言葉を使っていたようなイメージがありますが、町中で普通に「ありがとう」と使われていた江戸時代。
なんだかちょっと親しみが湧きます。
今までこんなことを考えたこともなかったので、和尚さんに「ありがとう」ですね。
