アナログとデジタル、時計の読み方での正解は?
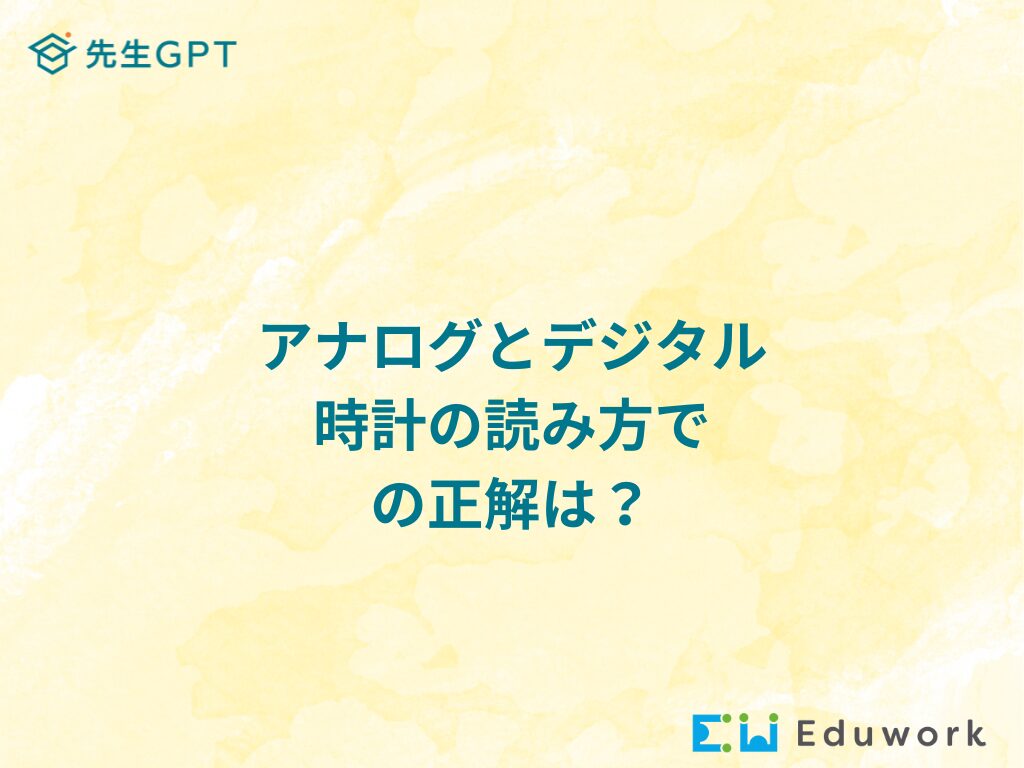
特別支援学校に通う小学部6年生の担任の先生からの相談がありました。
「アナログで時計を教える必要があるのかわからないお子さんがいる。どうしたらよいか?」
現状を聞くと、次のような状態とのことです。
・知的障がい
・量感はあやふやだがわかる
・数字は20くらいまでならなんとか
・決められた時間なら何時何分と言える
・1つのことを教えるのに、かなりの時間がかかる
・ゲームは好き
教えられそうですか?と伺うと、難しいのではないかと周りの先生と話しているとのことでした。
それなら「まずは1つ」です。
アナログから教えていくことが多い時計の読み方。それでもデジタルからということは、その児童がいくらかデジタルで処理をすることができている場面を見たのではないでしょうか?
こんな質問をすると、そうだとのこと。学校でもタブレットのゲームを触るそうで、そこではデジタルで処理をしているとのことでした。
それでしたら、まずはデジタルです。
健常といわれる方が10だけ覚えられることを、彼らは7とか8までしか覚えられないかもしれない。
それならば覚えられそうなことで、必要なことから教えていく。
就労現場でも、時計は配慮してもらいやすい項目です。初めからデジタルのところも少なくはありません。そんなお話を写真や実例でお見せすると安心しておられました。
教育の現場との連携、こちらとしてもとてもありがたいです。
