冬の味覚を伝えよう!
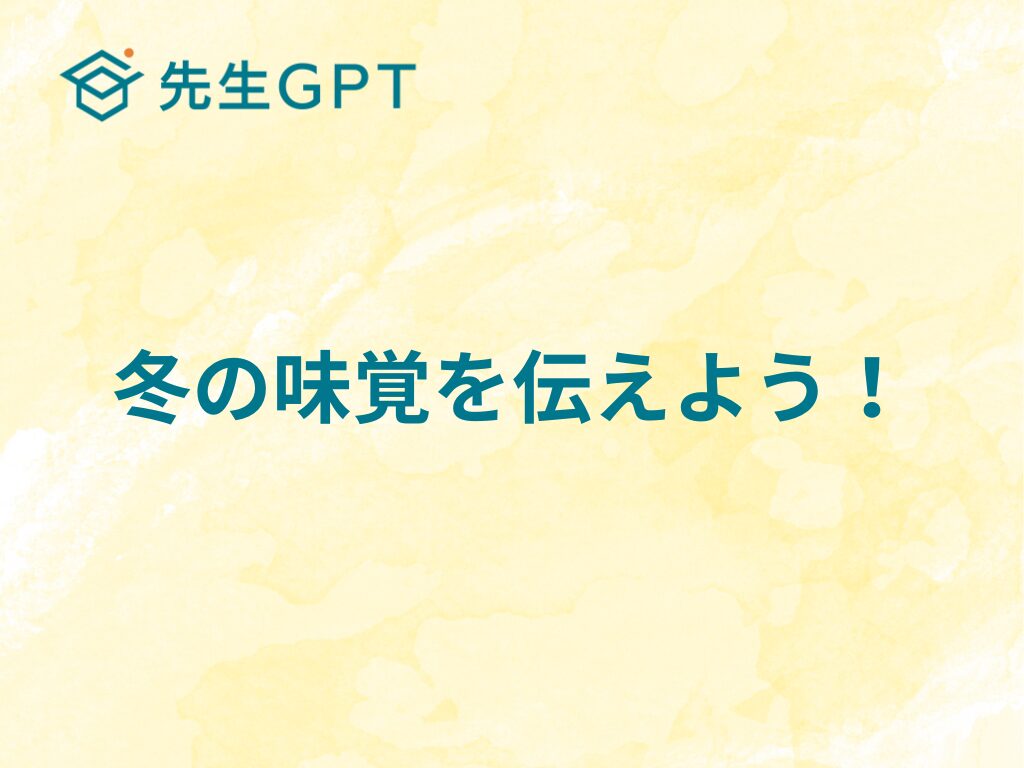
▪️先生GPTを使用されている皆様へのメルマガです。
業務改善はもちろん、生徒指導や授業のこともチラホラ。
ご利用されている方限定情報もありますが、こちらでは一部抜粋ということでご覧ください。
▪️寒い季節になると、旬の食材が美味しさを増します。
でも、子どもたちは結構『季節の食べ物』について知りません。
家庭でも、学校でも、そういった話をしないからです。
学期内の学習やテストが終わってきたこういう時期に、そういった話をしてみると盛り上がります。
【大根】
冬が旬の大根は、煮物やおでんにぴったりの野菜です。
寒さにあたると甘みが増し、じっくり煮込むと柔らかくなります。
元々、大根は奈良時代に中国から日本に伝わりました。
昔は「辛味大根」のような小ぶりで辛い種類が主流でしたが、江戸時代には現在のような大きくて甘い品種が作られるようになりました。
また、保存食としての「切り干し大根」や、漬物としても活用されてきています。
江戸時代の人々にとって、大根は冬の貴重な栄養源でした。
【白菜】
鍋料理には欠かせない白菜。
煮込むと甘みが引き立ち、冬の食卓の主役になります。
この白菜は、19世紀末に中国から伝わり、明治時代に日本で本格的に栽培されるようになりました。
それまでは冬に食べられる葉物野菜が少なかったため、白菜の登場は画期的だったと言われています。
また、漬物としても大活躍し、韓国ではキムチ、日本では「浅漬け」として親しまれています。
【長ネギ】
鍋料理や焼き鳥の具材としても定番の長ネギは、冬になるとさらに甘さが増します。
長ネギは古代中国から日本に伝わり、平安時代にはすでに食べられていた記録があります。
江戸時代になると、関東地方で現在の「白ネギ」が発展しました。
一方で、関西地方では青い部分も食べられる「九条ネギ」が主流です。
また、長ネギは体を温める効果があると言われており、昔から風邪の予防にも使われてきました。
【柿】
ちょうど今頃、スーパーでよく見かける柿。
熟した甘柿はそのまま食べても美味しいですが、干し柿にすると保存性が高まり、甘みが凝縮されます。
この柿は日本でも非常に古い果物で、縄文時代の遺跡から種が発掘されています。
平安時代には「干し柿」が貴族の間で珍味として人気でした。
江戸時代になると、農民たちが保存食として干し柿を作り始め、寒い冬を乗り切るための食材として活用されました。
地方によって独自の干し柿文化があり、長野県の「市田柿」や山梨県の「枯露柿」が有名です。
【ぶり】
冬の魚といえば「寒ぶり」。
脂がのって刺身や鍋物、焼き物にぴったりの食材です。
名前が成長に応じて変わる(ツバス、ハマチ、メジロ、ブリなど)ことから、「出世魚」としても知られています。
特に北陸地方では、冬のぶりは特別な贈り物として扱われ、年末年始の祝事には欠かせない存在です。
また、江戸時代には保存食として「かぶら寿司」が発展し、現在でも地域の名物料理として親しまれています。
どの食材にも、それぞれの味わいや歴史があります。
ただ、食べ物として伝えるだけではなく、歴史的な部分も話してあげると、教室はもちろん、家庭での子どもと親御さんとの会話にもつながっていきます。
