子どもの学びにどう使う?先生GPTの「活用」と「参考」
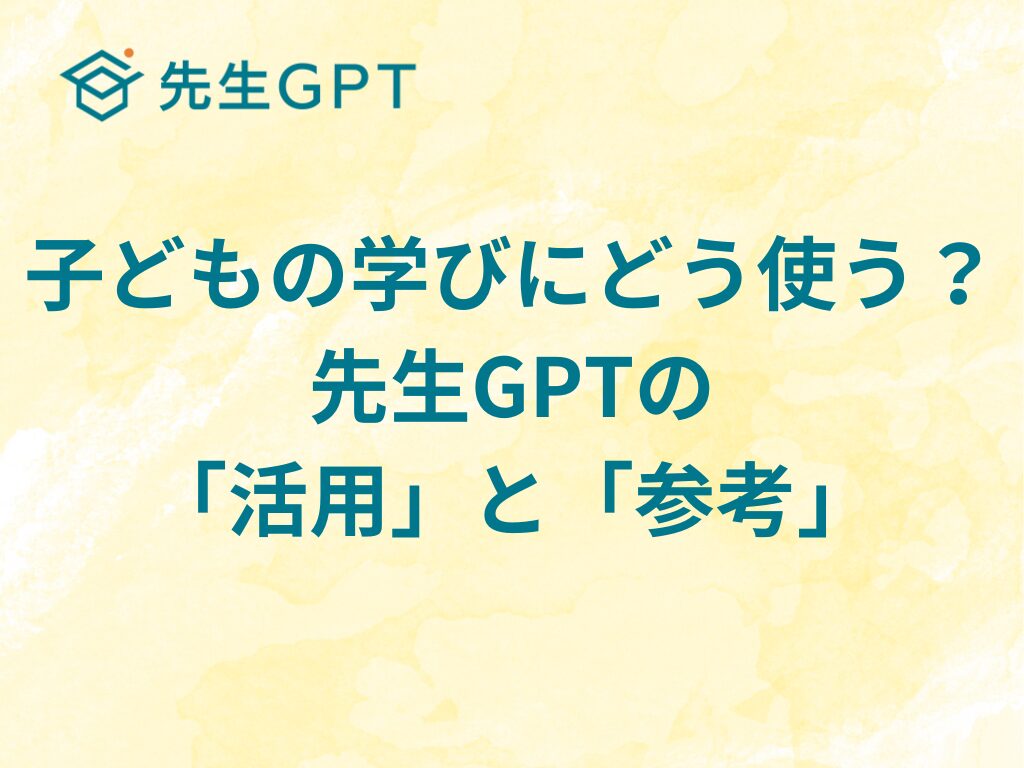
▪️先生GPTを使用されている皆様へのメルマガです。
業務改善はもちろん、生徒指導や授業のこともチラホラ。
ご利用されている方限定情報もありますが、こちらでは一部抜粋ということでご覧ください。
▪️先日、先生GPTを使った先生から、こんな感想をいただきました。
—
息子の宿題で「標語」を考える課題があり、先生GPTにテーマや条件を入れたら一瞬で例を出してくれました。
息子が『入賞しそうなのを出して!』と頼んだところ、さらに整った標語が出てきて面白いなと思いました。
ただ、その時にふと『これ、使っていいの?』と親子で迷いました。
結局、例を参考にしているうちに、自分で入れたい言葉を思いついて、再度入力して調整。
文字数を合わせるためにいくつか例を挙げてもらい、その中から選びました。
—
このエピソードには「生成AIをどう使うか」という大切なポイントが含まれています。
学びの場では、先生GPTが出した例を「参考」にすることが大切です。
参考例から表現や構成のヒントを得ることで、子ども自身が考え、工夫する力が育つからです。
一方で、大人が仕事や日常生活で先生GPTを時短目的に使うことは十分あり得ます。
しかし、学習の場合、丸写しでは本来の目的を果たせなくなってしまいます。
何のために使うのか、という視点が重要です。
先生GPTを学びのツールとして使う場合、次のような流れを意識すると効果的です。
1.先生GPTにテーマや条件を入力して例を出してもらう
2.その例を参考にしながら、自分の言葉やアイデアを考える
3.文字数や表現の調整をサポートツールとしてGPTに依頼する
例えば、作文や標語作成の課題で最初にヒントを出してもらい、その後に子ども自身がアレンジや調整を行う流れです。
生成型AIではなくても、友だちの作品や過去の入賞作品を参考にすることはよくあります。
同じように先生GPTから出た例も「参考」として使うなら問題はありません。
ただし、子どもたちが「自分で考える機会」を奪わないようにすることが重要です。
生成AIは便利なツールです。
だからこそ何のために使うのかを意識しながら、子どもの学びの質を守る使い方が求められます。
先生GPTを使うことで生まれる新しい学びや発見を、ぜひ子どもたちとの関わりの中で活かしてみてください。
