桜はソメイヨシノ?4月に話したい豆知識
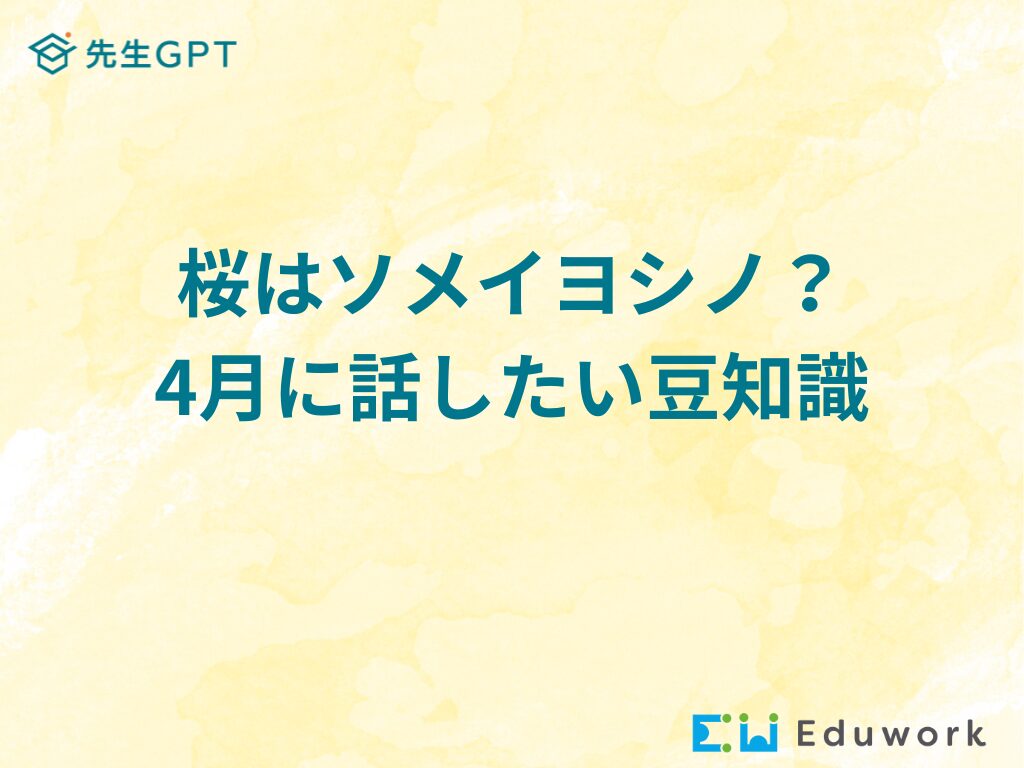
「咲き始めましたね」と話題にのぼる桜。毎年のこととはいえ、開花予想や満開予報が出ると、やっぱり気持ちがそわそわしてきます。今回は、そんな「桜」にまつわるちょっとした豆知識を集めてみました。
子どもたちとの雑談ネタや、新学期の学級通信の一コマに。話のきっかけとして使っていただけたらうれしいです。
■昔は「花」といえば「桜」ではなかった?
前回の「梅」で紹介しましたが『花=梅』を指していた時代もありました。奈良時代の『万葉集』(759年頃成立)では、梅の歌が桜よりも多く詠まれています。
ですが、平安時代の『古今和歌集』(905年)以降になると、桜を詠む歌が一気に増えてきます。そこから徐々に「花といえば桜」へと、時代の中で定着していったようです。
■桜の種類、何種類あるか知っていますか?
日本には野生種として10種類ほどの原種の桜がありますが、
それらをもとに交配された園芸品種を含めると、その数なんと600種類以上。
桜専用の検索サイトもありますので、タブレット学習のスタートにめくってみてもいいかもです。
↓
公益財団法人日本花の会「桜図鑑」
ちなみに学校や公園などで一番多く見られるのは、よく聞く「ソメイヨシノ」。江戸時代末期に、染井村(現在の東京都豊島区)で生まれたといわれています。
■なぜソメイヨシノが全国に広がったの?
ソメイヨシノは、挿し木で増やせるため、全国に同じ遺伝子を持つ個体を大量に植えることができました。
「一斉に咲いて一斉に散る」姿は春の風物詩。
入学式や新学期の始まりにぴったりということで、戦後の学校建設ブームとともに一気に広まったとされています。
ところが最近では、ソメイヨシノの寿命や病気への弱さから、別の品種を植える動きも出てきています。
■最近よく植えられているのは「ジンダイアケボノ」
東京都調布市の神代植物公園で見つかった「ジンダイアケボノ(神代曙)」という品種。
ソメイヨシノよりも少し濃いピンク色の花を咲かせ、病気にも強いと言われています。
近年では、地方自治体や学校の新しい桜の植樹に選ばれることも多くなってきました。
桜前線のニュースで「ジンダイアケボノ」と聞いたら、ちょっと得した気分になるかもしれませんね。
■花見のはじまりと、桜湯の文化
花見というと「お酒を飲んでにぎやかに」というイメージがあるかもしれませんが、
起源は奈良・平安時代の貴族たちが、桜を愛でながら和歌を詠んだ「雅な文化」が始まりとされています。
江戸時代には徳川吉宗が庶民のために桜を植え、庶民文化としての花見が広まったのだとか。
ちなみに、お祝いの席で出される「桜湯」に使われるのは“八重桜”の花を塩漬けにしたもの。
1輪ずつ手摘みで収穫され、丁寧に加工されているため、実はとても高級なものなのです。
このページ、面白かったです!
↓
さとまち「春のお菓子やお料理に使われる桜花の塩漬け」
■実は「国花」じゃない?
「日本の国花は桜と菊」なんてよく言われますが、
日本には法律で定められた国花は存在しません。
とはいえ、学校や公園、硬貨のデザインなど、桜は日常のあらゆる場面に登場します。文化として、私たちに最も身近な象徴なのかもしれませんね。
「花が咲く」「花が散る」
そうした自然の移ろいを大切にしてきた日本人の感性を、少しでも子どもたちにも伝えられたらいいなと思います。
