【Q&A】教科書を配っただけで終わらない。最初の1週間で教えること
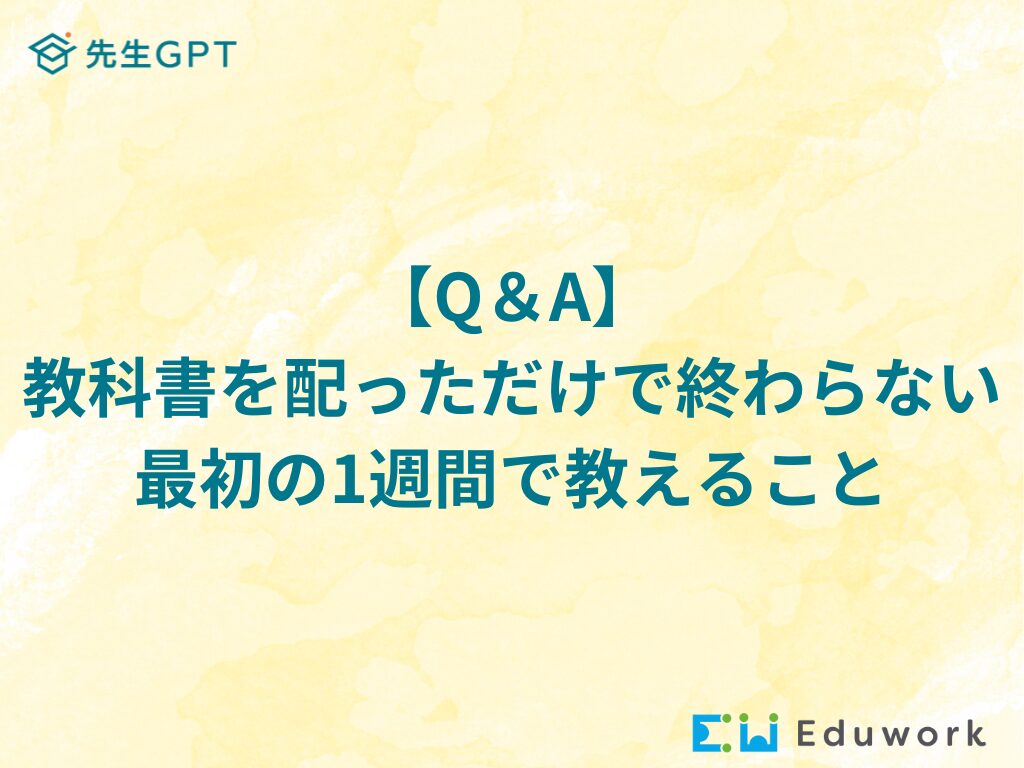
Q:子どもたちとの新しい1年が始まりました。
ですが、最初の1週間に何をどう進めたらよいのか迷ってしまいます。
教科の授業も始めていいのか、それとも学級活動を優先すべきなのか…。
最初の1週間って、どんなふうに過ごせばいいのでしょうか?(20代・女性・2年目講師)
A:とてもよくいただくご質問です。
年度当初のこの時期、教科書は配られたけれど、まだ時間割は暫定的。
行事も多く、授業が思うように進まないこともあります。
そんな中、「この時間、何を教えたらいいんだろう」と不安になる気持ち、よくわかります。
ただ、答えはとてもシンプルです。
この1週間でやるべきことは、授業の中で土台を整えることです。
学級開きの時期というと、つい学活やレク中心で進めたくなりますが、「授業そのもの」を通して学級づくりをすることが大切です。
たとえば、次のようなことをこの1週間で授業で教えていくと、クラスの動きが整っていきます。
1.ノートの使い方を教える
国語や算数など、最初の授業でノートを使うときがチャンスです。
・ページの使い始めは「新しいページから」
・日付、教科、タイトルは毎回書く
・1行空けて書くと読みやすい など
最初に習慣化させることで、1年間のノートの質が決まります。
これは後々、保護者面談のときにも成長の証として使える武器になります。
2.話す・聞くの姿勢を育てる
発表というと、大きな声、まっすぐ挙げた手、はきはきとした話し方…と思われがちです。
でも、教室には様々なお子さんがいます。
声が小さい子も、姿勢が崩れている子も、緊張して「忘れました」を連呼する子も。
そんな中で共通してできることは「どの子の声にも耳を傾ける姿勢」を育てること。
手を少しだけ挙げた子や、小さな声で話した子の発言に対して
「今、◯◯さんの話。聞こえた人?」
「すごいな、3人もいた。こういうのを『聞く姿勢』といいます。それがあるクラスは伸びるんですよね」
こんな感じで毎回のように話をしていくと、クラスの聴き方が育ちます。
3.授業スタイルの「型」を体験させる
最初の1週間は、授業のリズムを感じてもらう期間でもあります。
・先生の話を聞く
・一人で考える
・友だちと話す
・全体で発表する
こうした流れを少しずつ体験させておくだけで、2週目以降の授業がとてもスムーズになります。
班活動・スクール形式・全体発表などの机の移動も、1週間の中で意識的にバリエーションを入れていくと、「このクラスの授業はこんな風に進んでいくんだ」という感覚を子どもたちが持てるようになります。
4.当番活動や係活動を動かしてみる
「話し合って決めた」だけでは、子どもたちにとってはまだ実感がありません。
実感がないということは、機能しないのと同義です。
できなくても普通の状態です。
配膳の手伝い、清掃の役割分担など、実際に動かしてみることが重要です。
できるたびに評価する。
褒めたり、承認したり、認めたり。
「さすがだね」
「ありがとう」
「助かるな」
「よく気がついたね」
こうした言葉の一つ一つが、当番活動がうまくいくように進む第一歩になります。
始まりの1週間だけがんばることではなく、定期的にしていかないといけないことでもあります。
5.教材や配り物の整理・管理も授業の一部
教科書を配るときに、1人ずつ名前を確認するのか、机の上に並べておいて取りに来させるのか。
プリントは毎回手渡し? それとも係に任せる?
流れをつくるという意識で、授業と生活の導線をつくることで、時間のロスが少なくなり、子どもたちの見通しも安定します。
私の場合は、列の先頭の子に来させて「5枚です」のように言うように指示をしていました。
そうすると、移動するという過程がなくなりますので、毎日のように続く配布物の時間が短くなります。
6月くらいになると「日直さん、配っておいて」と渡すだけでできるようにしていきました。
このように、最初の1週間は教科の内容を進めるよりも、教科を通して「学級の土台」をつくるという意識を持つとよいです。
最初の1週間は、担任としての最初の腕の見せどころ。
ですが、完璧である必要はまったくありません。
必要なのは、「どんな1年にしたいか」を授業の中で、少しずつ形にしていくことです。
子どもたちは、先生の「ふるまい」から学びます。
そのためにも、この1週間の過ごし方が1年を大きく左右するのです。
焦らず、丁寧に。
授業をしながら、学級をつくっていきましょう。
