「隣のクラス、ちょっと怖い…」と思ったとき、どうすればいい?
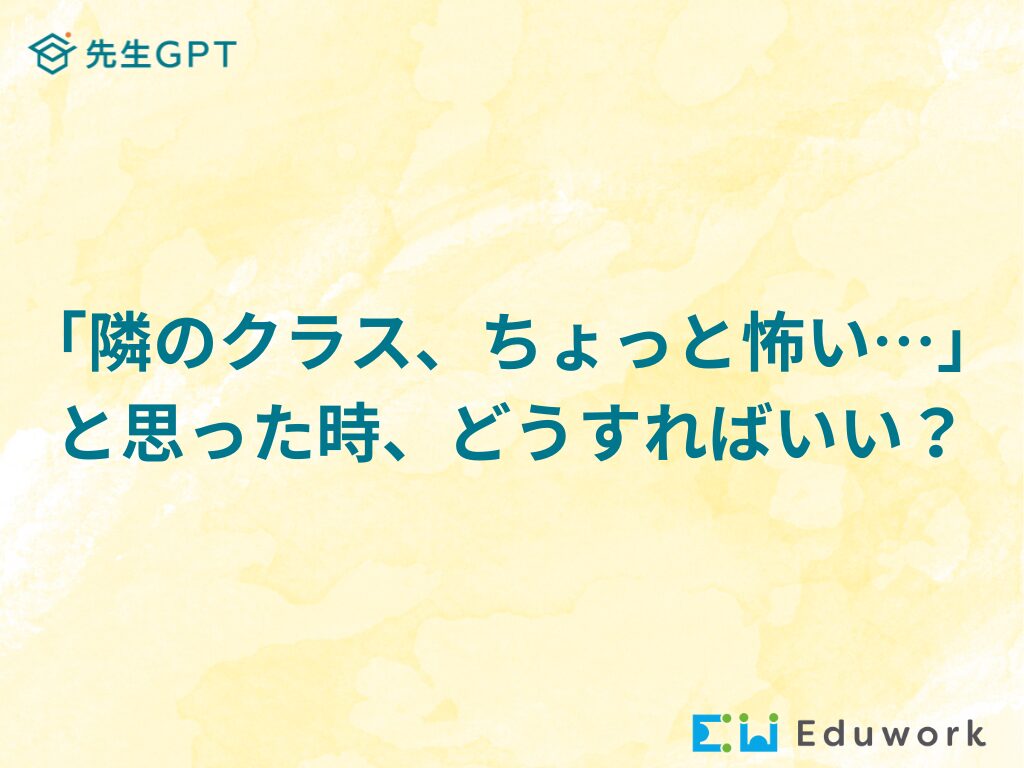
「隣のクラスの先生が、毎日のように怒鳴っていて、子どもを立たせて叱る姿もよく見かけます。子どもたちからも怖いクラスという声が出ていて、気になってはいるのですが…。自分がどう関わればいいのか、迷ってしまいます」
こういった相談。珍しくありません。
学校という職場では、先生同士の関係や指導スタイルが密接に関わり合っているため「気になるけど、口出しするのはちょっと…」という葛藤を抱える場面も多くあります。
でも、もしその指導が行きすぎたものだったとしたら?
「見て見ぬふり」では済まない問題に発展する可能性もあります。
1.どこからがハラスメントや体罰になるのか?
「叱る」「指導する」というのは、先生として避けられない仕事の一つです。
でも、強すぎる指導が毎日、しかも何度も続くようであれば、それは体罰と受け取られる可能性もあります。
たとえば、文部科学省が示すガイドラインでは、以下のような行為は通常、体罰に該当するとされています。
・帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
・立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
・別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
・宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。
どれも、教育的意図があったとしても肉体的苦痛を伴う場合は体罰と判断される可能性があります。
たとえ「その場を落ち着かせたい」という理由があっても、やり方を誤れば、学校側の責任が問われる事態になりかねません。
2.気になったとき、どう対応する?
「直接言うのは気まずい」
「他人のクラスには口出ししない方がいい」
そう思うのは自然な感情です。
でも、次のような対応であれば、負担も少なく、行動に移しやすくなります。
・複数の先生と「共通の違和感」として話題に出してみる
→「最近ちょっと気になる場面があるんだけど…」と、感情ではなく事実ベースで共有することが第一歩です。
・子どもの声を記録しておく
→「○○先生のところ、怖いって言ってた」などの声をメモしておくと、相談や報告時の客観的材料になります。
・信頼できる管理職や養護教諭に相談する
→「チクリ」ではなく「子どもたちが安心して過ごせる環境づくり」の一環として、報告・相談するスタンスが大切です。
3.正義感ではなく「チームとしての配慮」で
大切なのは「その先生が悪い」と糾弾することではありません。
でも、もしその指導によって誰かが傷ついているのだとすれば、学校全体で共有すべき課題になります。
「少し気になるな」
「ちょっと心配だな」
そんな小さな違和感も、先生同士が支え合うことで、子どもたちや教職員みんなが安心できる空気に変わっていきます。
必要であれば、先生GPTでもこうした場面での対応の文章、保護者への説明文などの作成をサポートできます。
一人で抱えず、いつでもご相談ください。
