【学級通信例文付】音読が学力を底上げする理由
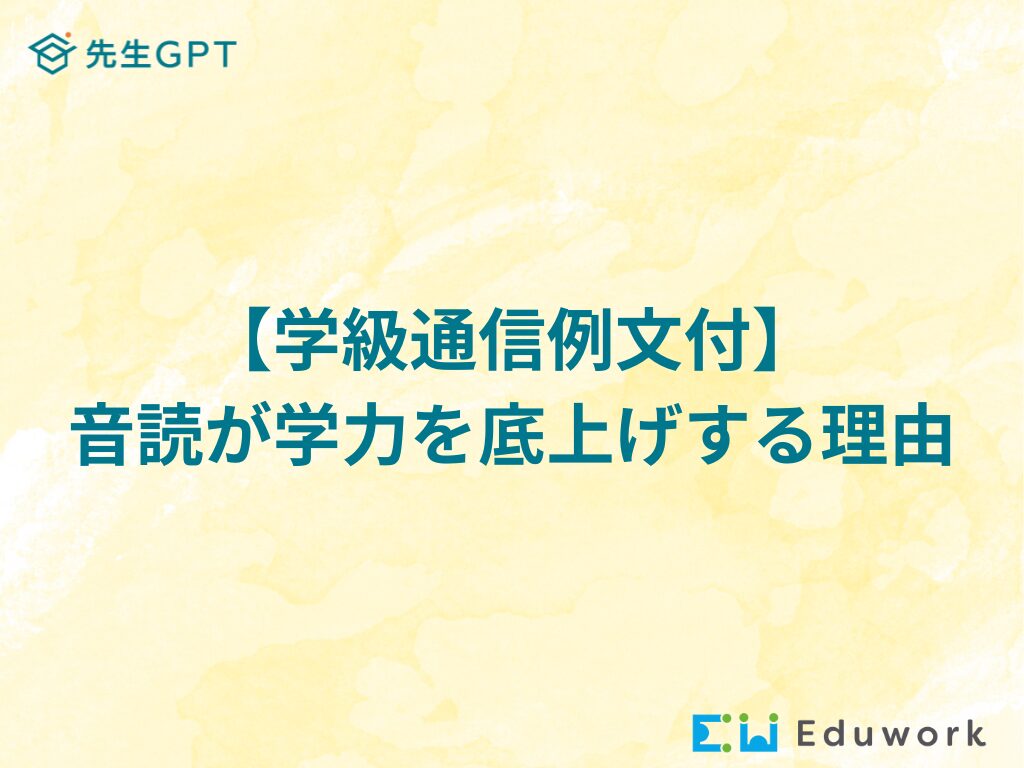
国語の宿題といえば、音読が定番の一つかと思います。
それでも『毎日同じ文章を読んでいるけれど、本当に意味があるのか』と思ったことはありませんか?
音読。
脳科学的にもとても理にかなった学習方法です。
音読をすると、目で文字を追い(視覚)、声に出して読み(運動野)、自分の声を耳で聞く(聴覚)、さらにその意味を理解する(前頭葉)というように、脳の複数の領域を同時に使います。
「脳の総合トレーニング」です。
特に学び始めの年代にとっては、読む・話す・聞くという体験を繰り返すことが、言葉のネットワークを作る上でとても重要です。
また、音読をすることで、文章中の「ひっかかり」に気づくことができます。
黙読では流してしまうような語句や言い回しも、声に出すことで「あれ?」と感じる。
この「ひっかかり」が理解につながっていきます。
あとは「型」です。
言葉の使い方の「型」が身につきます。
教科書を何度も声に出して読むことが効果的です。
音読は、国語にとどまらず、算数の文章題や理科・社会の語句、英語の音読にもつながります。
「音読ができる=学びのスタートが丁寧になる」ということです。
以前私が保護者向けに出した学級通信の一節をご紹介します。
【学級通信より:音読の大切さ】
おうちの方も子どもの頃、宿題で音読を「やらされた」のではないでしょうか。
積極的にやっていたのは1年生の初めの頃だけ?
学年が上がっていくにつれ「とりあえず読む」のようになっていった音読。
これには効果があるのでしょうか。
学校では、この「音読」を非常に重視していて、授業内では国語だけではなく様々な教科で行なっています。
文字を目で読み、声に出し、自分の耳で聞くという行為を同時に行います。
この3つの働きが連動することで、脳が活性化し、学習効果が高く望めるからです。
科書の持ち方、声の出し方、引っかからないで読むことを指導しながら、内容理解に向けて学習を進めています。
「ご家庭」の場合。
もちろん、そこまで丁寧にできればありがたいですが、なかなかそうはできません。
おうちの方からすると、ずっとついているわけにはいきませんし、子どもたちだってそれは同じです。
音読カードもありますが、大切なのは「どのようにやったか」ではなく「やったか否か」です。
『学習習慣をつける一環』として無理なく行ってくださればと思います。
学校の授業で「どのようにやったか」の質の部分は頑張りますので。
また、音読でもお気づきのところがありましたら、越智までお知らせください!
