知ってるようで知らない『浦島太郎』の小噺
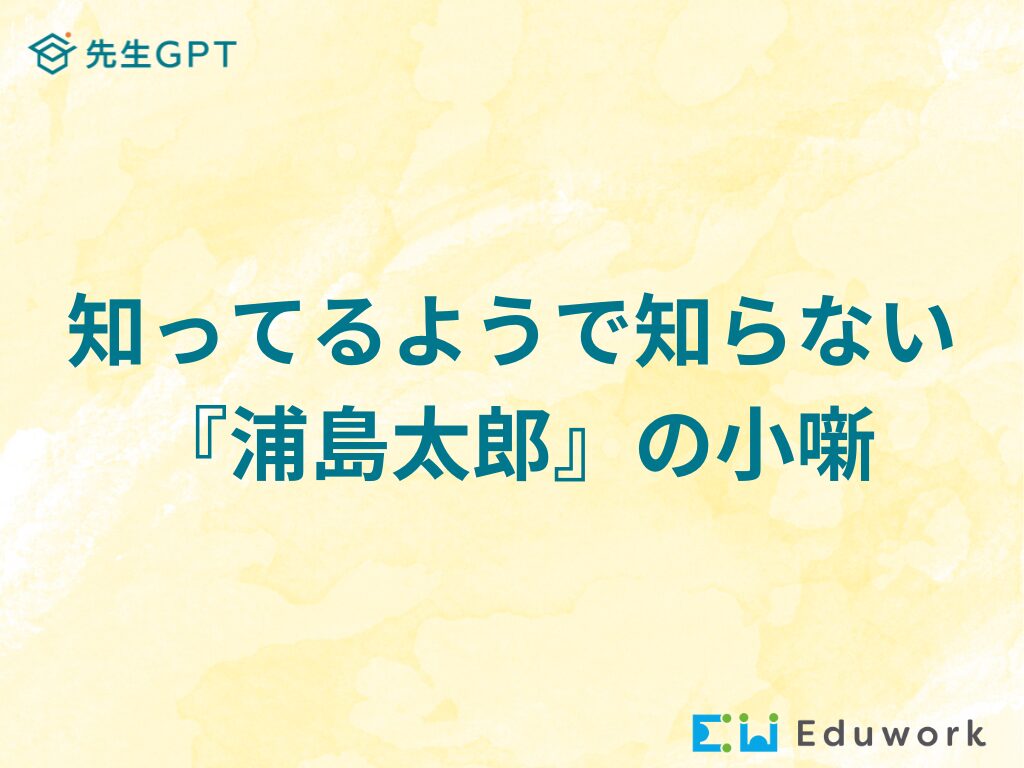
誰もが知っている昔話に「浦島太郎」があります。
でも、それを授業にできますか?
誰もが知っていることでも深掘りしていくと、面白い内容になることもあります。
4月の国語や授業参観などで活用できる形で紹介します。
1.浦島太郎、知っている人は手を挙げます。
→ほぼ全員が知っています。手の挙げ方が上手な児童等を褒めると、それが全体に波及していきます。
2.では、その浦島太郎。何年前からある昔話でしょうか?
→約1300年前。日本書紀に初めにできます。ここら辺は学年によって「50代前のひいひい…おじいちゃんとおばあちゃん」のように伝えてもいいですね。
3.その当時の浦島太郎には、今、みんなが知っているものが出てきません。何だと思いますか?
→玉手箱と竜宮城です。何人かの児童等に発表させて、その話し方のよいところや言えたこと自体を評価すると、それも教室に波及していきます。
4.その当時は、海に行ったきり帰ってこなくて、帰ってきたらお年寄りになっていたというお話だけです。
5.浦島太郎は、どこの話だと言われていますか?
→いろいろな地名を発表させます。正解を出すことに価値があるのではなく「話せたこと」に価値を出すようにしていくと、教室の発表が積極的になっていきます。
ちなみに、日本全国に浦島太郎の話があります。
6.浦島太郎は、日本全国にそのお話があります。例えば京都府京丹後市や神奈川県横浜市では、浦島太郎の玉手箱や釣竿が残されています。
では皆さんが住んでいる〇〇では、浦島太郎の話があると思いますか?
→ぜひ先生GPTで調べてみてください。多くの都道府県に浦島太郎のような「海に出て、しばらく帰ってこなかったが、帰ってきたら長い年月が経っていた」という物語が残されています。
7.それだけではなく、トルコやイタリア、ロシアなどの海外にも浦島太郎のような物語がたくさんあります。
→海に出て行方不明になり、時空を超えるような話は、世界各国に点在しています。
8.浦島太郎のようなお話を「昔話」といいます。もう一つ近い話に「神話」があります。この2つの違いは何だと思いますか?
→神話は「因幡の白兎」のように、地名や誰がという部分がはっきりしているケースが多いです。昔話は「昔々あるところに」という形で始まるように、どこで誰が、が不明瞭なケースが多いです。
9.多くの昔話に共通しているのが「行って帰る」ところです。浦島太郎もそうですが、桃太郎もそうですね。他にもアニメや映画などでもあります。ドラゴンボールやネバーエンディングストーリーは、行って帰る過程で様々なことがあるお話です。
昔話のお話の作り方に習って作られています。
10.誰もが知っていたはずの浦島太郎。それでもちょっと違う角度から見ると、様々な面白いところが見えてきます。今年の勉強、今まで知っていたことを元にして新しいことを学んでいく1年間にしていきましょう。
いかがだったでしょうか?もし授業の中で取り入れられるようなことがありましたら、ほんの少しでも使っていただけたらと思います。
