「連絡帳で済ませる?電話した方がいい?」保護者への連絡、迷ったときの判断基準は?
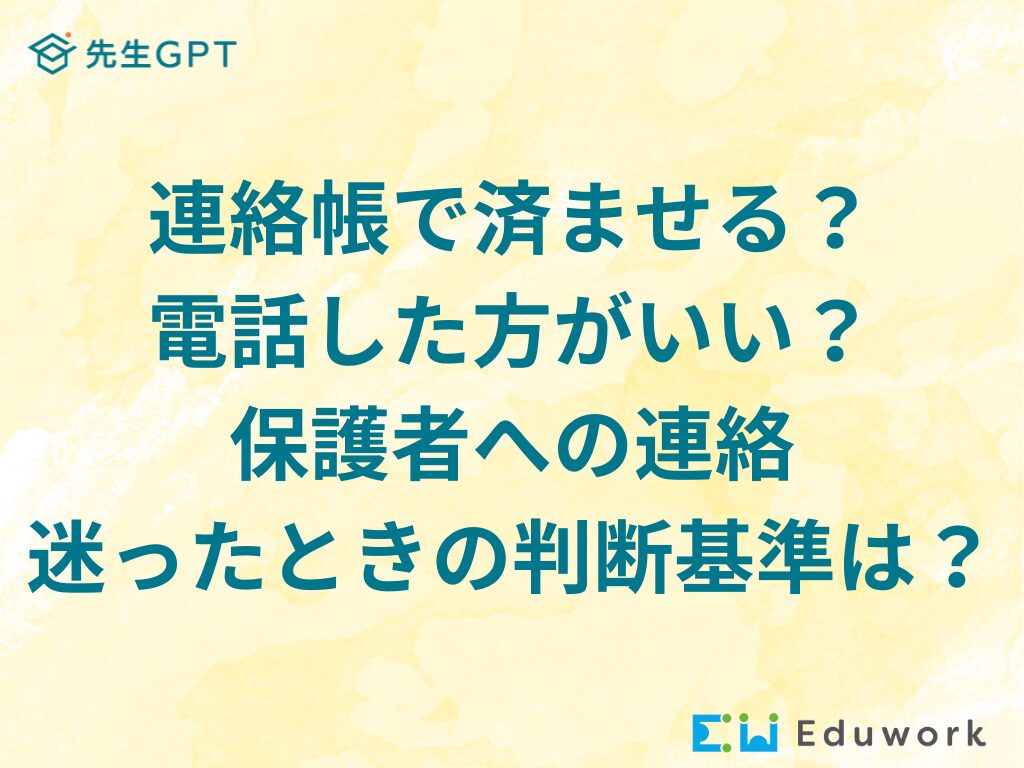
【質問】今まで一般企業で勤めていて、この春から教員になりました。早速、加減で難しいなと思っているのが保護者との連絡です。大人だったら伝えなくてもいいかと思うことも、念のために伝えておくことが必要だと学年主任から教えてもらいました。ツールとしては電話か連絡帳しかないと言うことでしたので、それらをどういった判定で、どちらのツールを使うのかっていったことを教えてくださればと思います。(30代男性教員)
【回答】一般企業にこれまでお勤めだったケースですと、予定されていた時間にリアルでお会いしたり、オンラインミーティングをしたりといったことが一般的だったのではないかと思います。
学校の特性上、保護者に連絡を取るのは突発的な事情であることが多いです。突発的である以上、対応を間違えると「クレームの種」のようになってしまいます。そこで私は次のような判断基準で対応するように心がけていました。
1.迷ったら連絡をする。
一応連絡をしておいた方が良いかな?と感じたことは伝えるようにしていました。というのも、その事象が子どもから保護者に伝わると、本人目線になります。その子にとって都合のよいフィルターがかかるのです。実際にあった事象よりも盛られて話すことも少なくありません。
自分を守るためと考えるとこうした子どもたちの動きは当然です。大人だって、自己防衛をすることはありますから。
そこで、教員が何らかの方法で保護者に連絡をすることまでは確定させておくと安心です。
2.ツールは「会う」「電話」「連絡帳」の順
どちらかというと、マイナスのイメージの保護者連絡。保護者の気持ちの揺れ動きなどによって、こちらも伝え方に気をつける必要があります。それが「その場の判断」で行える順に対応するようにしていました。
そう考えると、上記の順番が最も安定しやすいかと思います。
3.日常的に『よいこと』で連絡をしておく
なかなか時間は取れなくても、できると安心して学級経営をできるのが「よいことで連絡をする」です。
すごいことではなくてよいです。
・掃除で雑巾をした
・ゴミ捨てに自ら言った
・低学年に親切をした
・靴を揃えた
・朗らかに友だちと休み時間は遊んでいる
学校生活のほんの一コマを切り取り、実際にあった事実を伝える。30人学級で1日1人そういったことを保護者に伝えたとすると、1.5ヶ月で一周します。
こうした小さな承認をしていると、何かあった時の対応は本当にゆとりあるものになります。
ちなみに、これの順番は先程と逆で「連絡帳」を優先します。よいことは、記録がなかった方がよいからです。
トラブルが起きてからの対応を消極的生徒指導、よいことを伝え未然防止をする対応を積極的生徒指導といいます。
どうしても消極的な方ばかりになりがちですが、4月よいことを伝えることを習慣化してみると、学級経営が以前よりもスムーズになるかもしれませんね。
