学生だった頃の「時給」って覚えていますか?
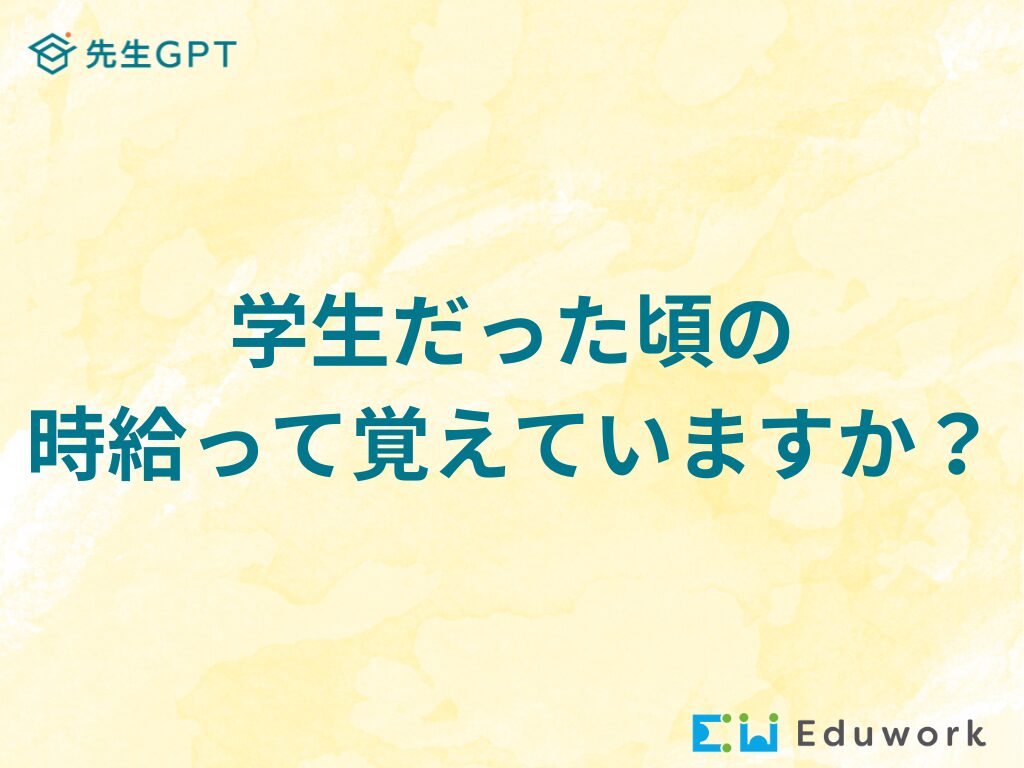
ある先生と話をしていてびっくりしたことがありました。
「え、今ってコンビニバイトで時給1000円超えるのが当たり前なの!?」
そういう感覚なんだと思いました…
最低賃金は私たちが学生だった頃と比べて、かなりの変化をしています。
【全国加重平均の最低賃金の推移】
2024年 → 1,055円
2014年(10年前) → 780円
2004年(20年前) → 665円
1994年(30年前) → 597円
全国加重平均の最低賃金の推移データ(1977年~2024年):バイト求人ネット
こうして並べてみると、この30年で最低賃金は約1.8倍になっています。
特にここ数年は、毎年のように「+40円〜50円」の上昇が続いており、政府としても「年収アップ」を掲げた取り組みの一環です。
■ 見方を変えれば、いろんな立場の声が聞こえる
最低賃金が上がると、どんな影響があるのでしょうか?
身近な例で考えてみましょう。
・高校生や大学生のアルバイトにとって → うれしい!
・主婦のパートやダブルワークの方にとって → 家計が助かる!
・A型事業所などで働く障がいのある人たちにとって → 工賃アップにつながる!
一方で、企業や事業所の側から見るとこうなります。
・人件費が上がるので採用を抑える動きが出る
・地方の中小企業では経営への負担が大きい
・雇用を守るために“時給以外の部分”でのコストカットが求められる
これに加えて、外国人雇用や人材不足といった他の要素も絡み合ってきます。
「雇用される側」と「雇う側」、その両方の視点を知っておくことが大切です。
■ 国際的な視点から見るとどうなの?
厚生労働省が令和元年度にまとめた国際比較資料によると…
・日本の最低賃金(当時)は約901円
・ドイツ:約1,139円
・フランス:約1,237円
最低賃金の国際比較:厚生労働省
物価の違いがあるとはいえ、OECD加盟国の中でも日本は中位クラス。
特に「先進国」の中では、上位に追いつけていないという現実もあります。
■ 教育現場でこの話題
この最低賃金の話、さまざまな場所で活用しやすいネタです。
以下のようなタイミングで活用してみてはいかがでしょうか?
【高校の進路指導】
「働くってどういうこと?」を話すときの入口に。
時給の話は実感がわきやすいです。
【特別支援学校や放課後等デイサービス】
A型やB型事業所の就労支援に関わる先生方にとって、最低賃金は重要なキーワードです。
【キャリア教育】
中学生や高学年の児童にとっても、「バイトの時給」や「働くって?」を考える教材にピッタリです。都道府県ごとの最低賃金を調べて、理由を考える…そんな活動も可能です。
■ あなたが学生だった頃、時給はいくらでしたか?
私はというと…「650円」という記憶が残っています。
当時はそれでも「まあまあ高い方」と言われていたような。
時代は変わり、制度も動いています。
先生方も、ぜひこの話題を子どもたちと共有してみてください。
きっと「えっ先生、安っ!」なんて、笑い話になるかもしれません。
でも、そこから「じゃあ、今と何が違うの?」と問いかけるだけで、
教室が社会とつながるきっかけになります。
