人材確保は難しい?先生だけが足りないわけじゃないので…
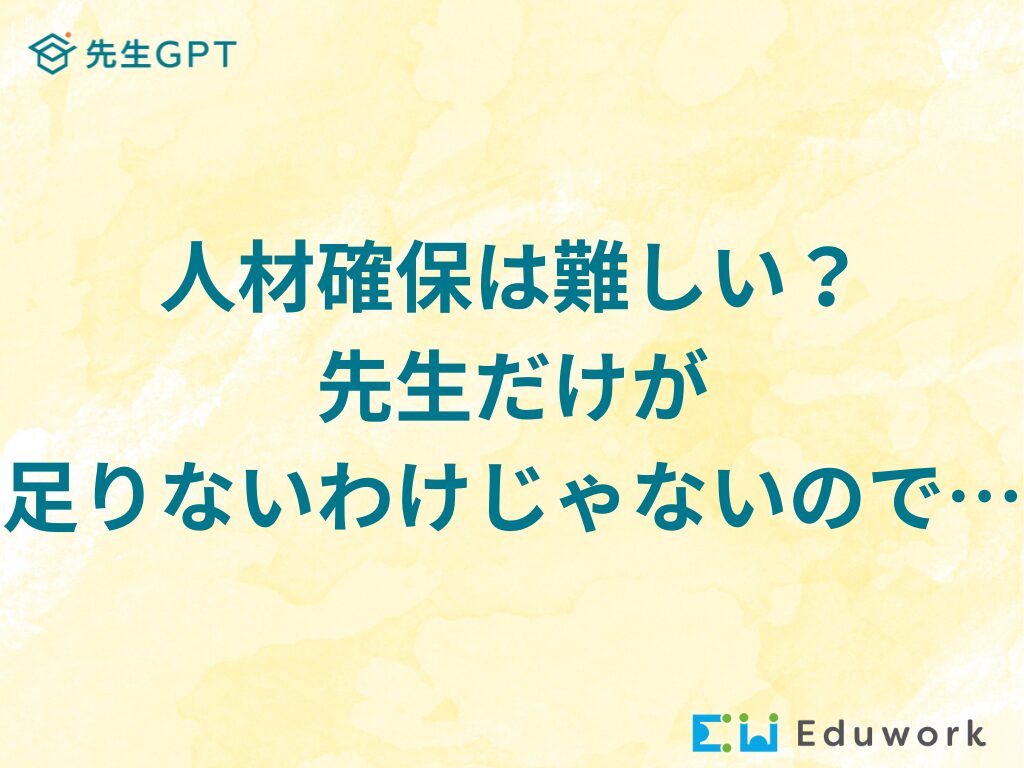
◻︎先生が足りない
教育業界では「先生が足りない」という話を聞かない日がないくらいになりました。
人数が足りないと何が起きるのか。
「担任の先生に本来あったはずの『空きコマ』がなくなる」なんていうのは序の口です。
法律で配置人数が決まっているものが足りないということは「法律に違反している」状態です。
民間なら「罰則」になるようなことが常態化している。
先生の数が足りない
↓
個々の先生の負担が増える
↓
休んだり、辞めてしまう
↓
そのしんどさが先生自身や保護者、メディアによって広がる
↓
先生になろうと思う方が減る
しかも、法律に違反した人数での配置になっている。
悪循環のループ。これは危うさしかありません。
文部科学省や各自治体の教育委員会が打開策を探していますが、根本的なところにはなかなか触れることができないでいます。
◻︎先生だけではない人材不足
教育業界にいると、先生の人材不足が際立っているように思いますが、そうではありません。
より当てはまる言葉に置き換えると「日本全体が人材不足」の状態です。
高齢化が進み、出生率や生産労働人口が減っており、外国人雇用も制限がかかっている。
そもそも、人がいない状態なのですから、充足するわけがありません。
また、これに関しては、かなりの精度で未来予測ができます。「この状態はこれから数十年悪化していく」のは、ほぼ間違いありません。
それは出生率を見れば明らかです。そもそも、子どもたちの数が減っています。また、今0歳の赤ちゃんが成人して、出産する年齢までは時間がかかります。昨今は、多様な生き方への認知が一般化してきましたので、出産するか否かも考えなくてはいけません。
これらの状態を合わせて考えると、劇的に良い方向になっていくという視点は、なかなか持てないのが現状です。
◻︎では、どうしたら?
私の会社も企業規模で考えれば中小です。
例に漏れず、人材不足の波は被っています。
その波を乗り越えるためには「賃金」「働き方」といった観点を、他社よりもよい条件で提示することしかありません。
それがない企業はどうなるのか。
淘汰されます。
これは、公務員だからといって、例外にはなりません。
このまま教員不足に拍車がかかれば、学校そのものの維持が難しくなる時代が来てもおかしくないのです。
◻︎当たり前を変える
こうした話を先生方とするときに「私の力では何ともならない」というお声をよく聞きます。
しかし私は、一人ひとりの先生にできることは「ある」と思っています。それが当たり前を変えるということです。
次のようなことは「教育業界の当たり前」ではないでしょうか?
・8:30にタイムカードを切っているのに、実際は7:30位から勤務している。
・法律上は、昼休憩があるはずなのに、採用してから取ったことがない。
・19:00くらいに帰ろうと思っても、「もう帰るの?」という雰囲気が漂っている。
時間だけで取り上げてもまだまだあります。
それに加えて、児童生徒対応や保護者対応、同僚との人間関係、増え続ける事務仕事…
本来は当たり前の権利として取れるのですから、取ってよいものです。それを、なんとなくの空気感だけで取らない選択肢を選ぶこと自体が未来の教育をつぶしている可能性があるのではないかと思います。
当たり前を変えること自体は怖いことです。でも、できることを少しでもやってみることが先につながっていくのではないかなとも思います。
