子どもたちのお小遣いっていくら?
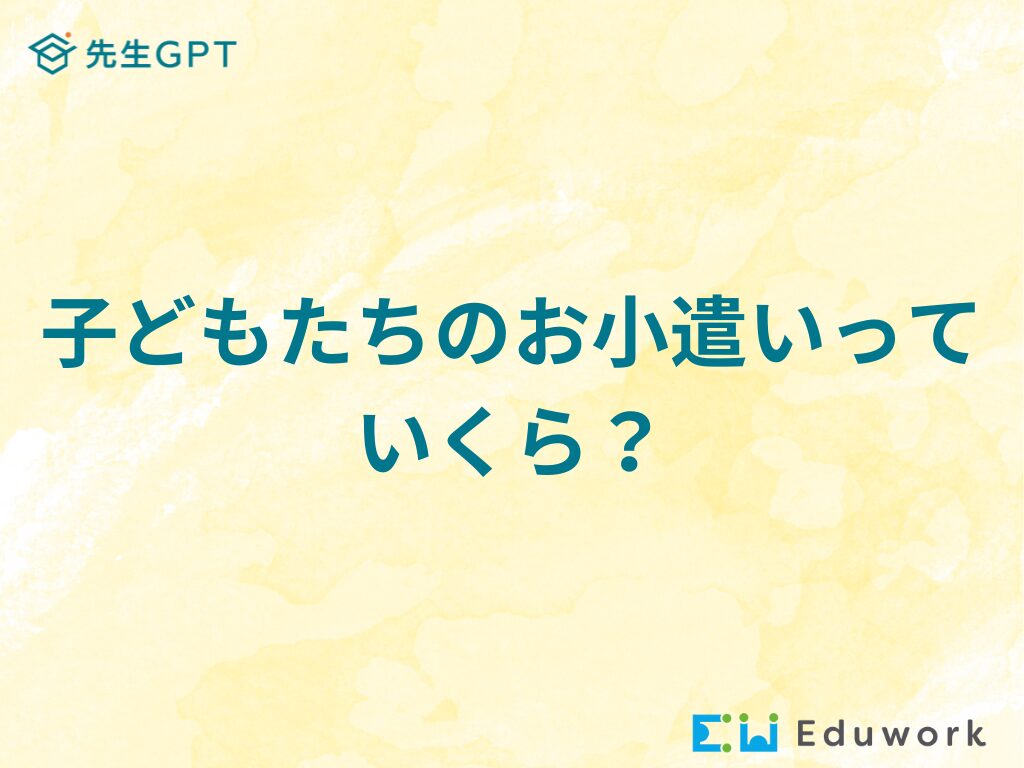
「お金」の問題は一緒に関わります。
ところが、教育や福祉の世界では、ほとんどお金について教える機会がありません。実際にその現場で子どもたちにお金を扱わせることができないからです。
家庭がお金を扱うメインの舞台になります。
では、保護者はお金についてどのように考えているのか。多くのご家庭は、働くことによって、毎月対価を得て、それらを何らかの形で使っています。それがどのような形であっても、その家庭のお子さんにとっては「モデル」になっていきます。
その内容が良いのか、そうではないのかは分かりません。
しかし、世の中の平均を知っていただくことは、材料の1つになるのではないかと思い、時々お金の講座を実施しています。
その中から少しデータを引っ張ってみます。
【お小遣いをあげる割合】
30.4% あげている
68.1% あげていない
1.5% 非解答
これは、教員時代の感覚からしても、そんなものだなぁと思います。
【お小遣いの金額】
小学1年生(7歳)506円
小学4年生(10歳)1,020円
中学1年生(13歳)1,941円
手渡しする金額としては、なんとなくイメージと会う金額です。実際にはこれ以外にも使ってあげているケースが少なくないのかも…とは思います。
家族でお出かけをしたり、買い物をした際に、お家の方から〇〇を買ってもらった、みたいな話はよく聞いていましたので^_^
【お小遣い制はあった方がよい?】
様々な考え方がありますが、私はあった方が良いと思っています。
子どもたちは働けませんので、収入はありません。
しかし、お金には触れる生活をしています。
スーパーマーケットやコンビニなどはよく目にしますし、そこで何がいくらと見ています。ゲームやソフト、習い事や洋服、すべてのものに絡んでいます。
自分自身が欲しいものがいくらなのか。
それは今買えるのか、貯めなくてはいけないのか。
貯めることすらできない金額であれば、誰かに交渉をするのか。それとも諦めるのか。
こうしたお金をどのように使うのか考えるきっかけになるのがお小遣いになります。
併せて「建設的な我慢」を教えることもできます。
親の一言で買うか否かが決定されるのではなく、〇〇を買うためには3ヶ月貯めなくてはいけない、のように我慢するという行為にゴール地点を設定することができます。
これは重要なことなのかなと思っています。
もちろん、この考え方が正解だとわかりません。ご家庭によって考え方は違いますので。
それでも何らかの形で、家庭や学校の一斉授業でも、そうした話をする機会があった方が、大人になってからトラブルが起きにくいのに、とは感じます。
お金の勉強、子どもから大人まで、ずっと必要な学びの1つなのだろうなと思います。
