【Q&A】給食中のおしゃべりが止まりません。注意の仕方に悩みます。
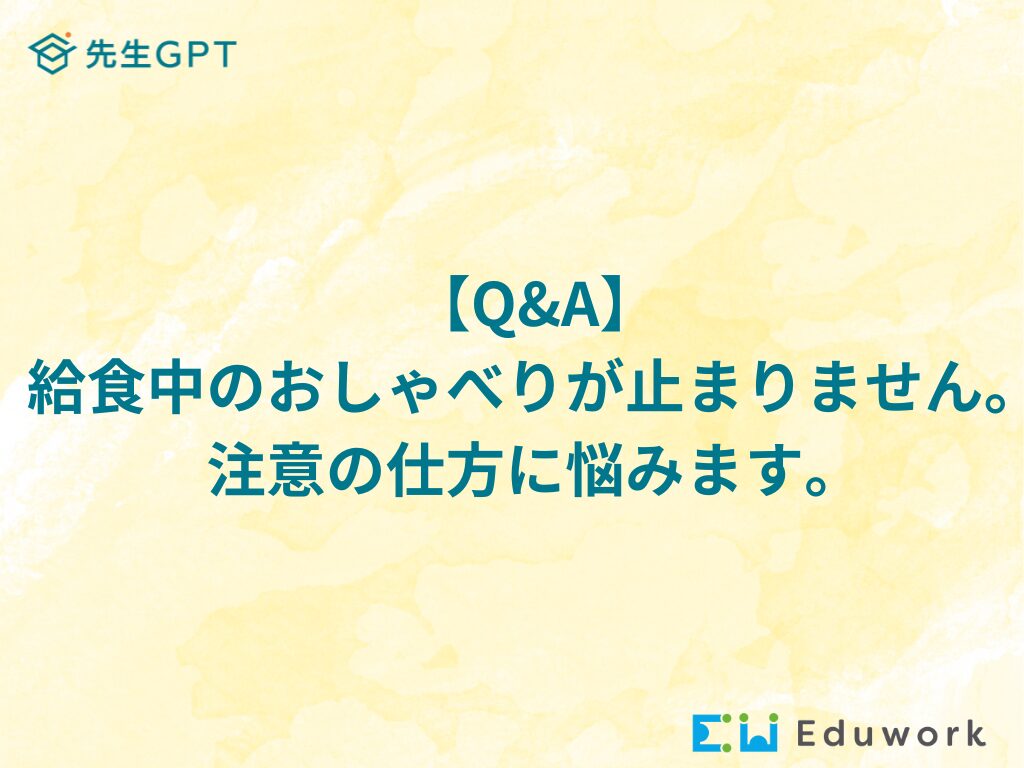
Q:給食中のおしゃべりが止まりません。
注意の仕方に悩みます。
給食の時間は班の形にしています。
でも、友だち同士のおしゃべりが止まりません。
おしゃべりがあってもよいと思うのですが、時間になっても、かなりの量が残っていて、結局廃棄になってしまいます。
どうしたらよいのでしょうか?
A:このご相談、とても大事な問いかけだと思います。
給食中を「静かにさせるかどうか」で判断するのではなく、まずは給食の本来の目的をあらためて確認しておきましょう。
■ 給食の目的とは?
学習指導要領には、学校給食のねらいとして以下のような項目が記されています(抜粋)。
・適切な栄養の摂取による健康の保持増進
・日常生活における食事の正しい理解と望ましい習慣の形成
・食生活を営むために必要な基本的な知識と態度の習得
・学校生活を豊かにし、食に関する体験を通じて人間性を育むこと
「残さず食べること」も、この中では適切な栄養の摂取に関わる要素の一つです。
しかし、『適切に』であって『すべて完食しなければならない』わけではありません。
現場では「給食は残してはいけない」という空気が根強く残っていることもあるかもしれません。
でも、無理に食べさせることは体罰にもつながりかねません。
まずは、先生自身が「残してもいいときもある」という空気をつくってあげることが、安心感につながります。
■ おしゃべりは「悪いこと」ではない
次に、おしゃべりについてです。
もちろん、席を立ってしまったり、全く食べないような状態は問題です。
ですが、「食事をしながらの会話」自体は、むしろ大切なスキルです。
大人の私たちも、カフェや食事の場で会話を楽しみます。
ビジネスの現場でも、食事を交えた対話は人間関係を深める大事な時間になります。
そう考えると、給食の時間に必要なのは「黙って食べさせること」ではなく、「食べながら話す」という文化の中で、どうすれば気持ちよく過ごせるかを学ぶ時間にすることです。
■ 指導のポイントは「静かに」より「うまく食べる・話す」
次のような声かけや工夫で、雰囲気は変わってきます。
・「今は食べる時間。あとでゆっくり話そう」
・「残り10分、みんなのごはんの様子を見て『話すタイミング』を決めるね」
・「話すときは、おはしを置こうか」など、行動の切り替えを意識させる指導
食べることと、話すこと。
どちらも大切だからこそ、「うまく切り替える力」を教えていくことが、これからの食育につながります。
■ 大人になっても役に立つ食の経験
給食を「訓練」のような時間にするのではなく、
大人になっても役に立つ食の経験として育てていくこと。
それが、今の学校給食に求められている姿なのかもしれません。
