集中力を高めるために授業を“細分化”する
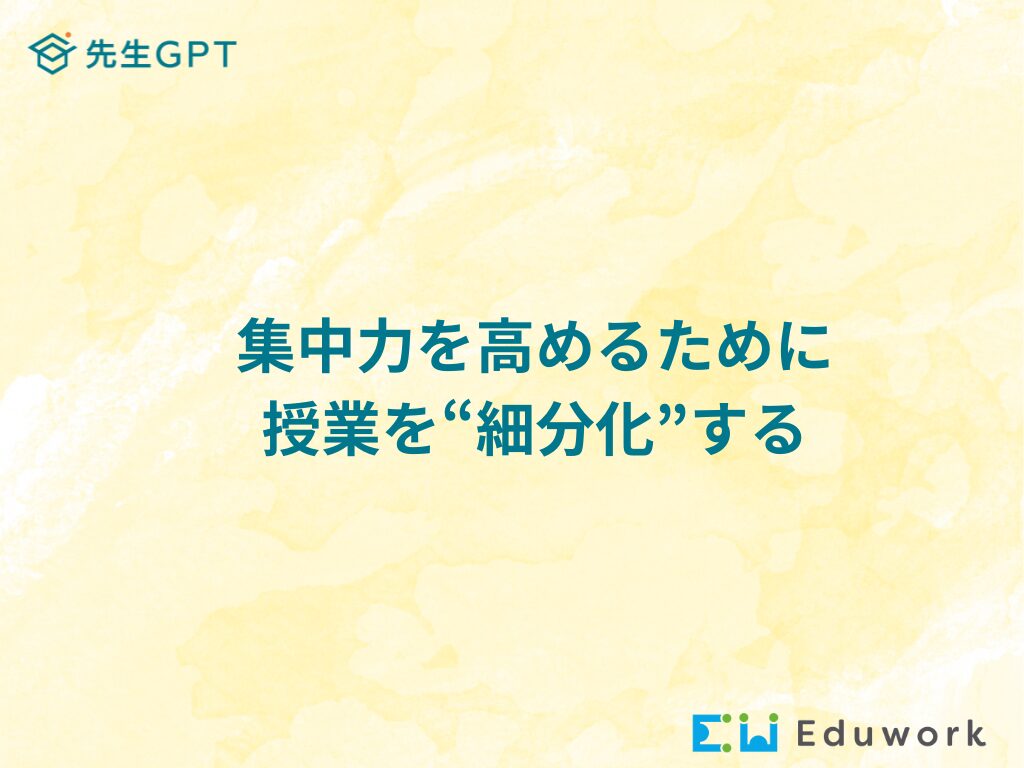
授業時間は、1コマ45~50分。
放課後等デイサービスなどでは、90分以上のプログラムもあります。
これだけの時間、子どもたちが集中し続けるのは、なかなか難しいですよね。
■ 大人でも「集中し続ける」のは難しい
私たち大人でも…
・やり始めたばかりは集中しづらい
・電話や来客で中断されると戻りにくい
・30分以上はもたないこともある
こうした“集中の切れ目”に、子どもたちはもっと敏感です。
外を見始める
席を立つ
ノートに落書きをしている
…など、気づけば「授業どころじゃない状態」に。
■ 叱っても、根本解決にはならなかった
私自身、先生になりたての頃は「集中しなさい」と叱ってばかりでした。
でも、感覚では分かっていたんです。
叱っても集中は戻らない。
それが根本的な解決じゃないことを。
そんな時、先輩から教えてもらったのが【細分化】という考え方でした。
■ 国語の授業を「5つに分ける」と…
たとえば、国語の45分授業を次のように分けます。
1.漢字(10分)
2.音読(5分)
3.板書の整理・ノート記入(5分)
4.発問・意見記入・発表(15分)
5.まとめ(5分)
この“分ける”というのは、ただ分担するのではなく、
「先生自身が、意識して切り替える」ことがポイントです。
そうすると、集中が切れてしまった子が戻ってくる“きっかけ”が、
5〜10分おきにやってくるようになるのです。
つまり、叱らなくても授業に戻れる流れが自然と生まれていく。
■ 細分化は、授業以外にも使える!
この考え方は、授業だけでなく他の活動にも応用できます。
たとえば、放課後等デイサービスでの「料理プログラム」。
一通り終えてしまうと「もうやることがない」というケースがありますが、
それも“細かく分けてみる”ことで解決の糸口が見えてきます。
【料理活動の例】
1.器具や材料の準備
2.作業場の整頓
3.食材を混ぜる
4.火にかける
5.盛り付ける
6.片付け(洗い物・ごみ捨て・整理整頓)
こうして工程を分けることで、
・どこが得意か
・どこで手助けが必要か
が見えてくるようになります。
■ 「集中できる流れ」は、先生がつくる
国語の授業でも、生活単元でも、日常の場面でも。
「今、子どもたちはどんな力を使っているか?」
「次は、どう動けば切り替えられるか?」
それを見通して“細分化”していくことが、
集中力を引き出す近道になります。
叱るのではなく、切り替えのタイミングをつくる。
そういう工夫を、少しずつ積み重ねていけたらいいですね。
