台風と日本の歴史
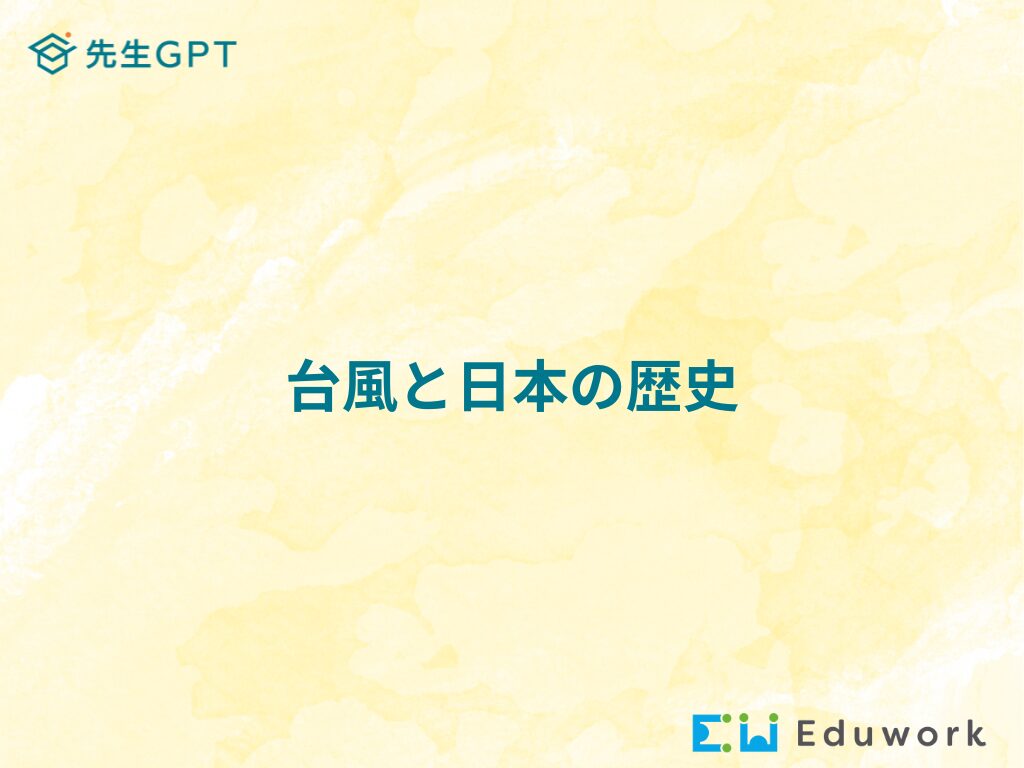
9月は、一年の中でも台風が最も多くやってくる季節です。
日本と台風との関わりは非常に古く、千年以上前の歴史書にもその姿が残されています。
最古の記録は『日本書紀』にまでさかのぼります。
推古天皇21年(613年)の条に「大風(おおかぜ)」と書かれており、これが日本で確認できる最古の台風の記録とされています。
当時はもちろん「台風」という言葉はなく、人々にとってはただ「恐ろしい風」として伝えられていたのです。
自然災害の多い日本では、こうした大風の記録が後世の教訓となるよう、歴史の中に残されていきました。
奈良・平安時代に入ると、『続日本紀』などの史書や貴族の日記にも「大風」「暴風雨」という表現が繰り返し登場します。
京の都を襲った豪雨や洪水、社寺の倒壊などの記録があり、当時の人々にとって台風は暮らしを大きく揺さぶる存在であったことがうかがえます。
特に平安京のような新しい都市では、河川の氾濫や洪水がたびたび起こり、政治や社会生活にも大きな影響を与えました。
江戸時代になると、藩や寺社の史料に台風の被害が詳細に残されるようになります。
寛永18年(1641年)の台風では、長崎を襲った暴風雨でポルトガル船が沈没したという記録があり、台風が国際貿易にも影響を与えていたことがわかります。
江戸後期には「天保の飢饉」などの背景にも、度重なる風雨災害が関わっており、台風は経済や農業を揺るがす存在でもありました。
そして明治時代になると、気象学の発展とともに台風の記録は大きく変化します。
1875年に東京気象台(現在の気象庁)が設立され、気圧や進路などが科学的に観測されるようになりました。
ここで初めて「台風」という言葉が定着し、自然現象としての台風が研究対象となったのです。
この時代以降、私たちは被害をただ受け止めるだけでなく、観測や予測を通じて「備える」ことが可能になっていきました。
また、台風には国際的な名前もつけられています。
2000年からはアジア各国が提案した140の名前を順に使用しており、日本も「やえやま」「くろまる」などの名称を提供しています。
大きな被害を出した台風は名前が抹消されることもあり、自然災害の記憶を後世に残す意味も込められています。
たとえば2019年の台風19号「ハギビス(ラテン語で“すばやい”)」は、東日本を中心に甚大な被害をもたらしたため、その名前が今後使われることはありません。
こうして歴史を振り返ると、日本人は古代から現代まで台風とともに暮らし、その都度学びを積み重ねてきたことがわかります。
記録の残し方は「大風」という素朴な表現から、現代の詳細な観測データにまで発展しました。
9月という台風の季節だからこそ、過去の記録を思い返し、改めて家庭や学校での備えを話し合ってみるのもよいかもしれません。
自然災害は避けられませんが、歴史の積み重ねから学ぶことで、未来の安心を少しずつ築いていくことができます。
【参考URL】
・国立国会図書館レファレンス協同データベース「防災、災害に関する記述のある古典作品」
https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000262234&page=ref_view
・気象庁「台風の国際名」
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-5.html
