テレビから動画コンテンツへの移行
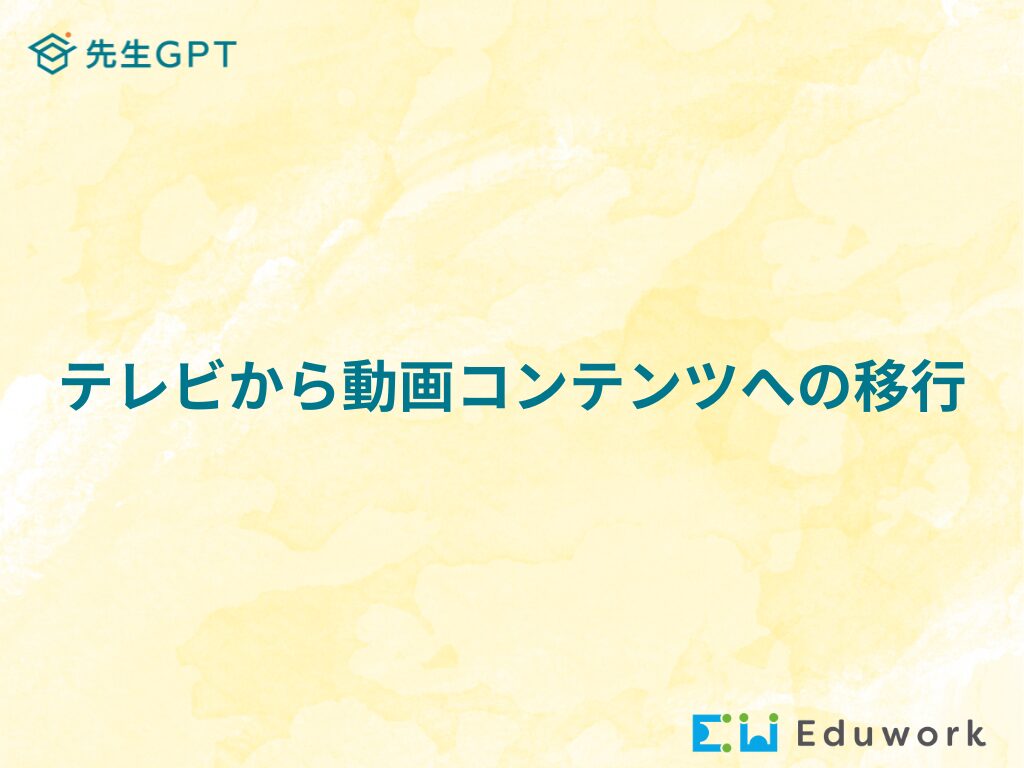
一人暮らしをしているテレビ保有率が下がっているそうです。
10代では5割台後半、20代では7割弱となっています。
高校を卒業して、進学や就労をした世代です。
それらの年代の方たちに聞いていると、メディアに触れていないわけではありません。YouTubeやTikTok、Instagram等の情報を得ています。
また、ゲームをしているケースも多く、授業の合間や仕事での休憩時間にはそれらで時間を使っている様子をよく見かけます。
40代以降の方ですと、テレビや新聞で情報を得ることが一般的だった世代です。
一方、若い世代はそうではない。
情報入手経路が変わっています。
両者の違いは、様々あります。
そのうちの1つが、表出する際に何人の目を通ってきているかです。
テレビや新聞は、多くの方の目を通って報道されています。
各種SNSでは、その人数が圧倒的に少ないです。玉石混合の様々な情報が発信されています。テレビ等では絶対に流れない興味深いものもあれば、人を貶めるようなものまで様々です。
必要になってくるのは選択能力です。
テレビや新聞のようなメディアの場合は、画一的な情報ではありますが、リスクは低いです。
SNSの場合は、どのような情報が自分自身にとって必要なのかを選択する力をつけさせなければいけません。
この力、どうやってつけることができるのか。
基礎的な知識を身に付けることだ、そもそもそういった情報には触れない方が良い、流れてくる情報に有益なものはほとんどない…
様々な情報が錯綜しています。
私自身が放デイや学校で話しているのは「人に会うこと」です。親と先生。ここまでは多くの方が毎日のように会う人です。
では、そこからは?
これは環境によってかなり変わってきます。
習い事、趣味、親の仕事、親戚、友達…
誰と会い、何を話し、考えたのか。
体感にはなってしまいますが、多くの人に会っている方はその中から学んでいるケースが多いです。
いろんな場で、いろんな人と交流をする機会。
持っていったほうがよいなと思います。
テレビ視聴環境の現状と課題(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001013803.pdf
テレビ保有率は全体で9割、単身世帯の若年層では「パソコン」が「テレビ」の保有率を上回る(LINE)
https://lineresearch-platform.blog.jp/archives/42723516.html
