「楽しいから笑う」と「笑うから楽しい」の違い
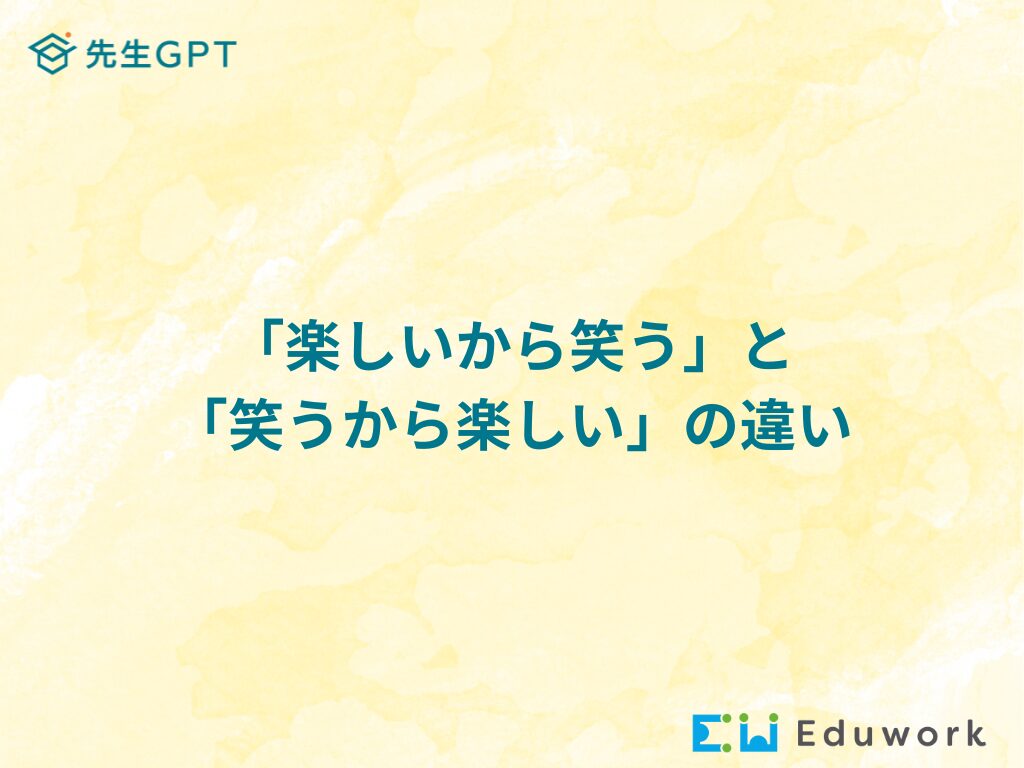
30代前半の女性の先生からの相談がありました。
「教室にあまり楽しい雰囲気が流れていない。こちらもついつい小さなことも叱ってしまう場面がある。どうしたら良いのだろうか」
どんな場面で叱るのですか?と伺うと、例えば、特定の児童が忘れ物をした時と答えました。
それって毎日じゃないですか?と伺うと、そうだ、と。
「また忘れたの?昨日も言ったでしょう?なんで前の日から準備するとか、何かしらできることがあるのに、どうしてしないの?」みたいな感じですかね、と私から伺うと、ほぼそうだとのことでした。
なんで再現みたいなことができるのですかと聞かれたので「あるある」だからですよ、と答えました。
それから次のようにお伝えをしました。
先生だから子どもができるようになってもらいたいという願い自体はわかります。
でも、忘れますよ、子どもですから。
明日から持ってくればよいという考えではなく、年度末には少し忘れ物が減ったのでよかったな、というのが教育かと思います。
であれば、叱らなくてよいです。
叱って忘れ物が減るなら方法の1つですが、効果が低いのは先生がよくご存知かと思います。それよりも、他の子どもたちも萎縮してしまって、楽しくない空気が流れていくのではないでしょうか。
明日も忘れてしまうことはわかっているのですから、その時にどう対応するのかを考えておきましょう。
ニヤリとしながら「そう思って準備しておいた」
遠くを見ながら「次は持って来られるといいなぁ」
普通に「言いにくることができて成長したな」
スルーでもいいと思います。
どんな方法を取ったら、指導もできて、クラスの空気が悪くならないか。
おそらくその児童は、毎日のように忘れ物をするのですから、毎日のようにお試しすることができます。
子どもたちからしたら、クラスで楽しいことがあったら笑います。逆も同じです。
先生の場合は、それだけでは足りません。クラスのリーダーとして教室の雰囲気を作る立場ですから。そのように考えると『先生が笑って、クラスの雰囲気を作り、子どもたちに楽しいと感じさせる』というのが大切かと思います。
私もそのようにしていましたが、自分自身のストレスにもならず、快適に子どもたちと学校で過ごせるようになりますよ。ぜひ試してみてください。
その先生、「早速試してみます!」と明るい表情でした。試してうまくいかないこともあるかとは思いますが、今までと違う前向きなことをするのは、決して悪いことではないと思います。
うまくいくとよいなぁと思いながらzoomを終えました。
