日照時間が短くなる時期の「負担の減らし方」
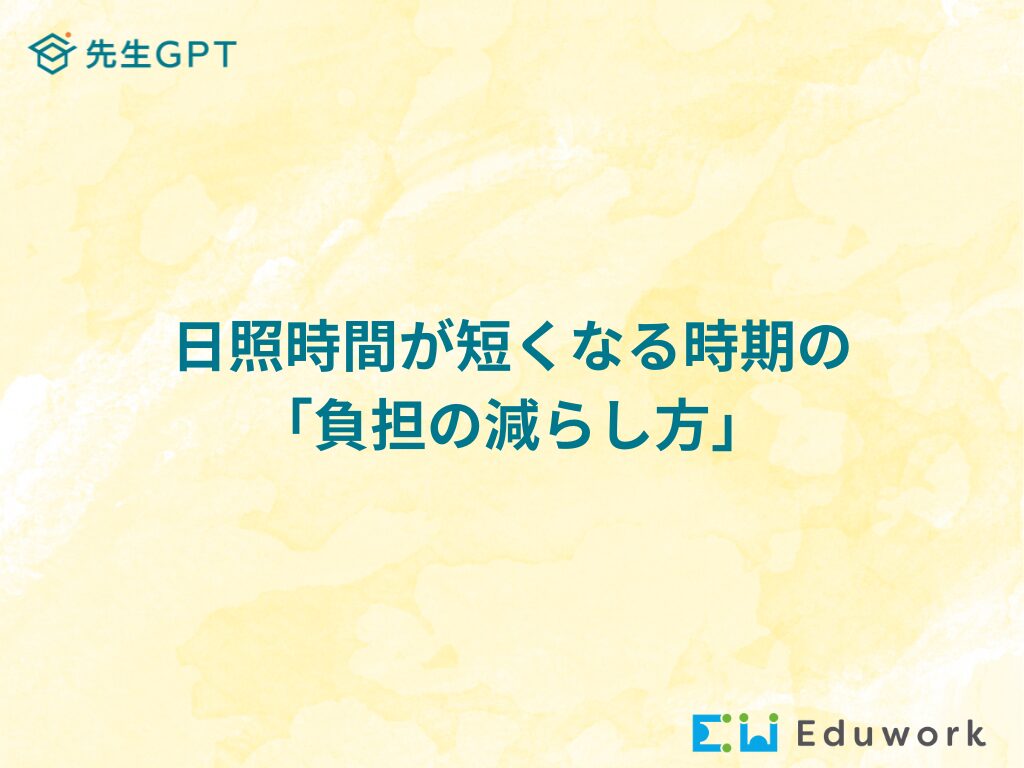
「気がつくと外が暗くなっていた」と感じるような季節になってきました。
それもそうです。
11月の終わりになると、日照時間が年間でもっとも短い時期に近づいていきます。
こうした季節の変わり目は「なんとなくしんどい」「集中しづらい」という声が増えます。これは性格ではなく、はっきりとした生理的な理由があります。
『体内時計の順応』です。
人の体には、脳の「視交叉上核(しかさじょうかく)」という部分が、体内時計の司令塔として働いています。この司令塔は光の量でリズムを調整します。朝の光を受けることで時計がリセットされ、日中の活動がしやすくなります。
秋から冬に日照時間が短くなると、このリズムが乱れやすくなります。
これが、朝のだるさや気分の落ち込みにつながることが多いとされています。季節性の気分変動(いわゆる季節性うつ)も、このメカニズムの延長にあります。
さらに、光の量が減ると、日中の覚醒を助けるセロトニンが低下しやすく、反対に夜に分泌が高まるメラトニンが早い時間帯から出やすくなります。
夕方に眠くなる。
夜にもうひと頑張りできない。
こうした変化は、どちらも光環境によるものです。
つまり、「いつもの自分より疲れやすい」のは、環境によって引き起こされる身体の反応です。こうした状況に合う負担の減らし方は、季節に沿ったシンプルなものになります。
まずは、朝の光をしっかり浴びることです。
曇りの日でも屋外の光は、室内照明の数十倍〜百倍以上あります。体内時計にとっては、この差が大きな意味を持ちます。短時間でも窓辺にいる、外に出る。それだけでリズムが整い、気分や集中が戻りやすくなります。
次に、予定の密度を下げることです。
体が省エネモードに傾きやすい時期です。普段と同じ量をこなそうとすると、結果的に負担が大きくなります。一つだけ予定を減らす。休憩を前倒しする。それだけで、体の消耗がかなり違います。
また、選択を減らす仕組みづくりも、負担の軽減につながります。
体内時計が乱れやすい時期は、判断力・集中力も影響を受けます。朝のルーティンを固定したり、仕事の順番を決めておいたりすると、迷う回数が減り、疲れにくくなります。
最後に、この季節は加点方式で自分を見ることが大切です。体が本来よりエネルギーを使いにくい時期です。「できたことに目を向ける」ほうが、季節の影響と折り合いがつきやすくなります。
とはいえ、忙しい時期。
そうはいってもどうしたら?となりがちです。
私の場合は、教員時代からほんの少しでも前倒しすることを心がけています。
放っておくと仕事は締切間際になります。しかも、いろいろな仕事の締切が重複します。そこで、1つでよいから、前倒ししよう気を付けていました。
今の時期ですと、9月から11月までの出席だけ入れておこう、総合の所見だけは書いておこう、生活の丸は付けておこう、のような感じです。
ひとつできたら、もうひとつ…そんなにうまくいかないこともありましたが、締切ギリギリにはこうした前倒しに何度も助けられていました。
これから本格的な冬シーズン。無理をしないための調整をしながら、準備ができればと思います。
