ハサミって、いつからあるの?
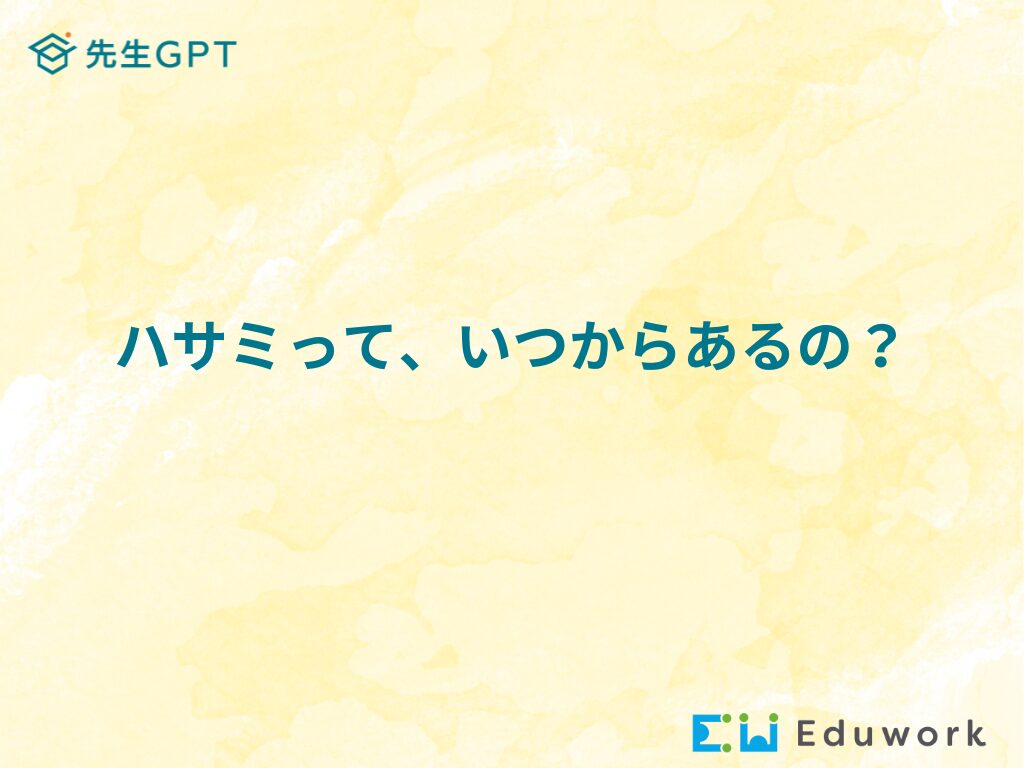
事務仕事も多いので、ハサミをよく使います。
文具屋で並んでいるのを見て、これがいいなぁと思って使っているのですが、今使っているものはいつ買ったのか思い出せないほど昔です。
ちょっと切れ味が?と思ってアマゾンで調べていたら、たくさんの種類が出てきたので、興味が湧き、ちょっと調べてみました。
そもそもは「ハサミって、いつからあるんだろう?」です。
100年前? 江戸時代?
調べるとびっくりするほど昔でした。
⸻
■ 昔のハサミ
いちばん古いハサミは、なんと紀元前1500年ごろのエジプトで使われていたようです。
今から3000年以上も前。
この頃のハサミは、私たちが知っているチョキチョキとはちょっと違います。
1枚の金属を曲げて作った、「バネのような仕組み」。
手で押すと先が閉じて、離すと開く。まるでトングのような形でした。
これを「ばね式ハサミ」といいます。
今でいう「糸切りハサミ」のような感じです。
日本にハサミが伝わってきたのは奈良時代ごろ(8世紀)とされています。
中国から仏教とともに伝わり、「和ばさみ」という名前で知られるようになります。
特に、着物をつくるための「裁ちばさみ」として、大切に使われてきました。
当時のハサミは、すべて職人さんの手作り。鉄でできていて、ずっしり重く、サビやすいものでした。
でも、それだけに「大事な道具」として、何年も何十年も、手入れをしながら使い続けられていました。
⸻
■ 今のハサミ
いま私たちがふだん使っているハサミの形。
指を2つの輪に入れて「チョキチョキ」するタイプです。
この「ねじで2枚の刃をつないだ形」は、ローマ時代(紀元前〜紀元後1世紀ごろ)に登場したと言われています。
そこから何百年もの間、少しずつ改良されながら、世界中に広がっていきました。
特に、19世紀の産業革命の頃から、ハサミは大量生産されるようになり、一般の家庭にもどんどん普及していきます。
20世紀には、ハンドル部分にプラスチックが使われ始めます。
これにより軽くて持ちやすくなり、子ども用や料理用など、いろんな種類が登場します。
⸻
■ 最近のハサミ事情
さて、ここからが最近のハサミ事情。
昔と比べて、いまのハサミは「かるい」「つかれない」「音がしない」という特徴がどんどん加わっています。
たとえば、
・「スッと切れるハサミ」
軽い力で切れるように、刃に「フッ素コート」や「ギザ加工」がされていて、紙が逃げにくい仕組みです。
手が小さい子どもでも安心して使えます。
♪プラス フィットカットカーブ プレミアムチタン
・「1本で多機能」
ハサミ+カッター+定規が合体したような、文房具オタクも驚くようなハサミも登場。
「これ1本で全部できる!」という便利道具になっています。
♪サンスター文具 スティッキールはさみ AKERUNO(アケルノ)
【ハサミの最強おすすめランキング31選。LDKがよく切れる人気商品を比較】
※URL内で複数タイプが比較されています(音の静かなモデルも含む)。
・「段ボール専用ハサミ」
ネット通販が増えたことで登場したのがこれ。厚くて硬い段ボールも、ザクッと楽に切れる特別な刃がついています。
しかも手を傷つけないように刃の出っ張りが少ない設計です。
♪コクヨ 2Wayハサミ〈ハコアケ〉
・「左きき用」や「ユニバーサルデザイン」
右利き・左利きに関係なく、どちらの手でも使えるハサミも増えてきました。
手にやさしいグリップ、開閉しやすいバネ構造など、体の違いに配慮されたデザインです。
♪レイメイ藤井 左手用こどもはさみ
【ユニバーサルデザインのはさみ5つ。みんなが使える優しい文具をご紹介】
♪Craft Design Technology(左右両用・ユニバーサルデザイン)
これらのハサミは、文具店やネット通販で気軽に手に入ります。
授業や教材づくりで試しに使ってみると、「もっと早く知りたかった!」という声もよく聞きます。
⸻
■ 道具は進化する
そんなに複雑な構造には思えないハサミ。
それでも長い歴史の中でなかなかの進化を遂げてきているのが面白いです。
もうすぐ夏休み。
ちょっと文具屋に足を運んで、見比べてみてもいいかもしれないですね。
